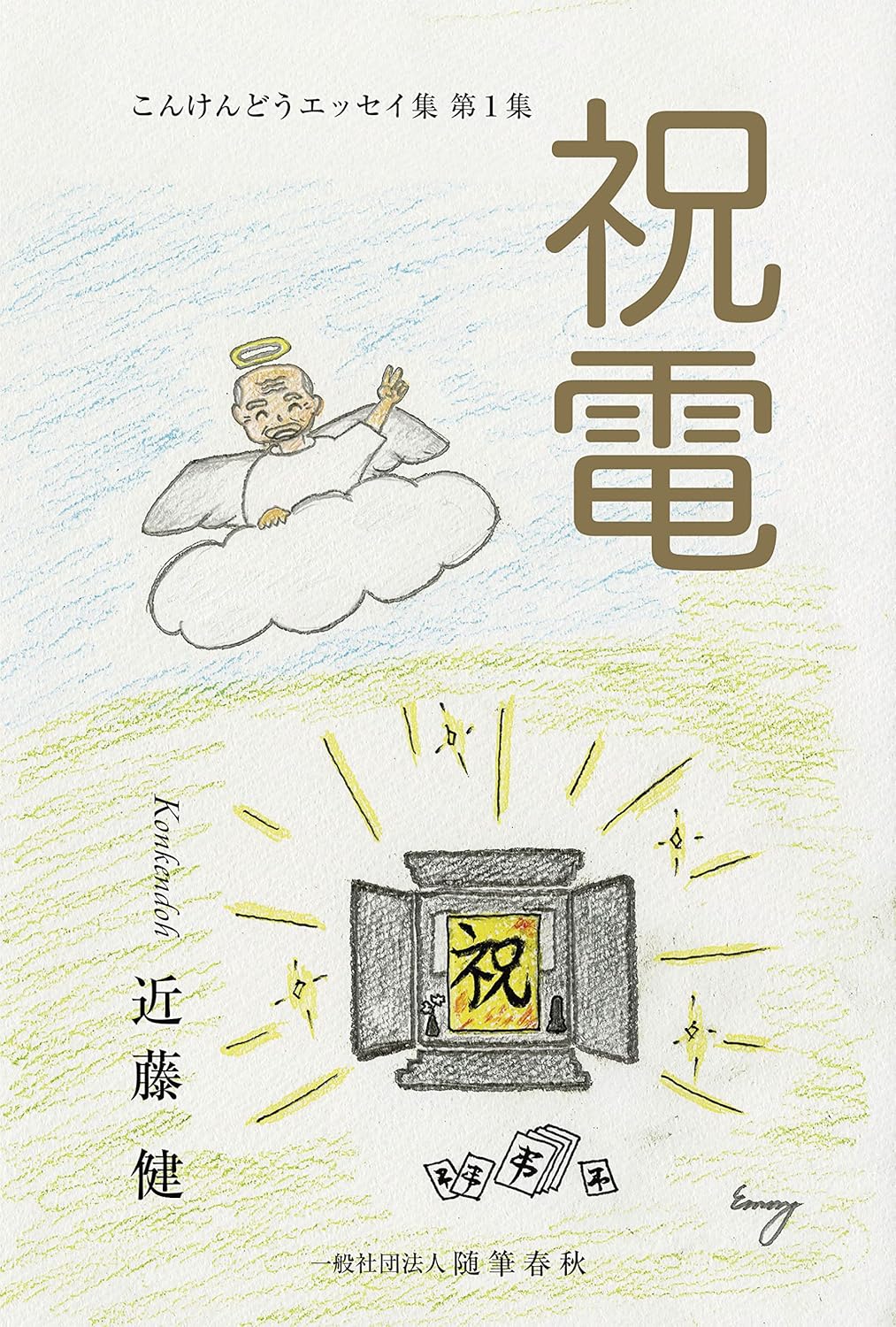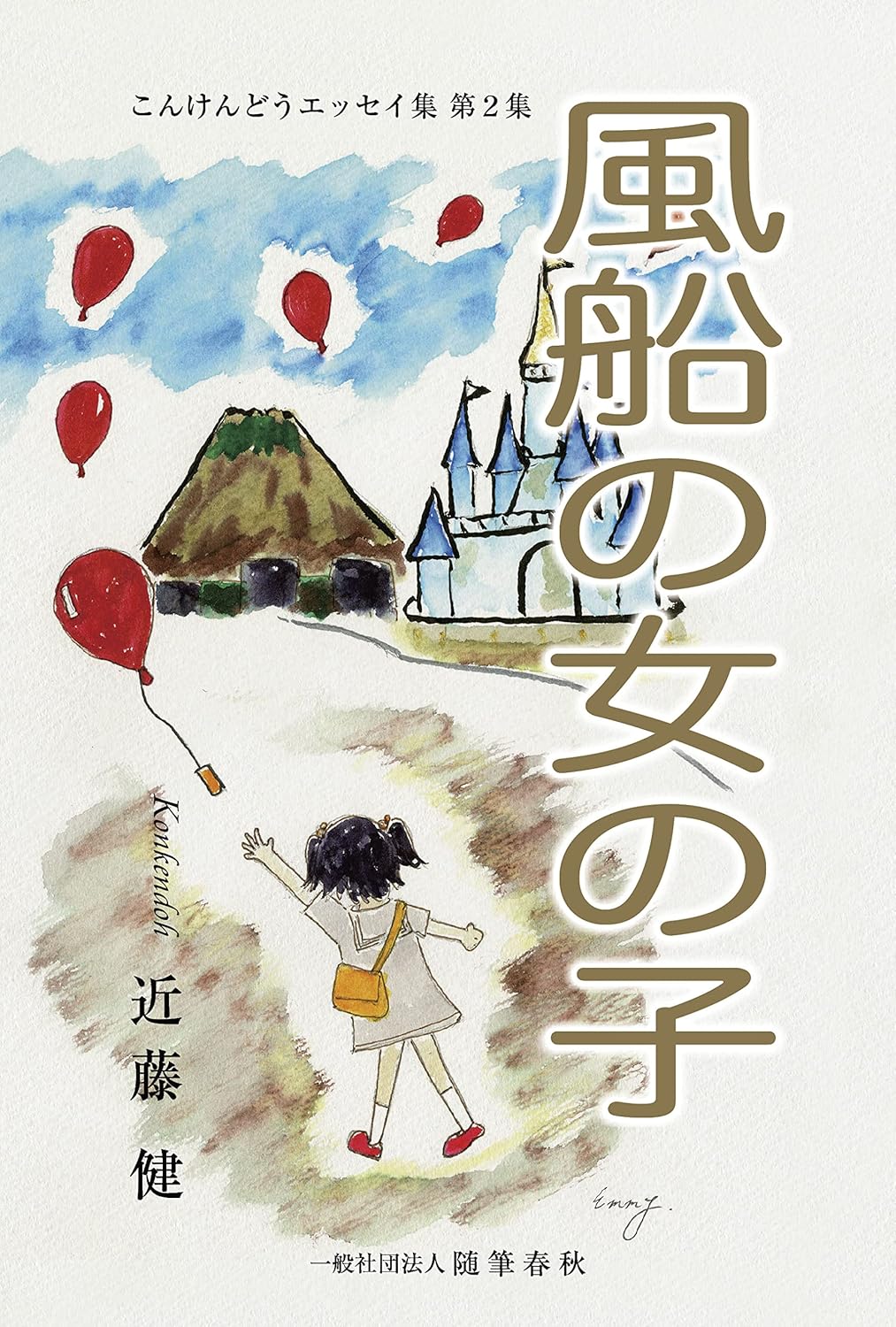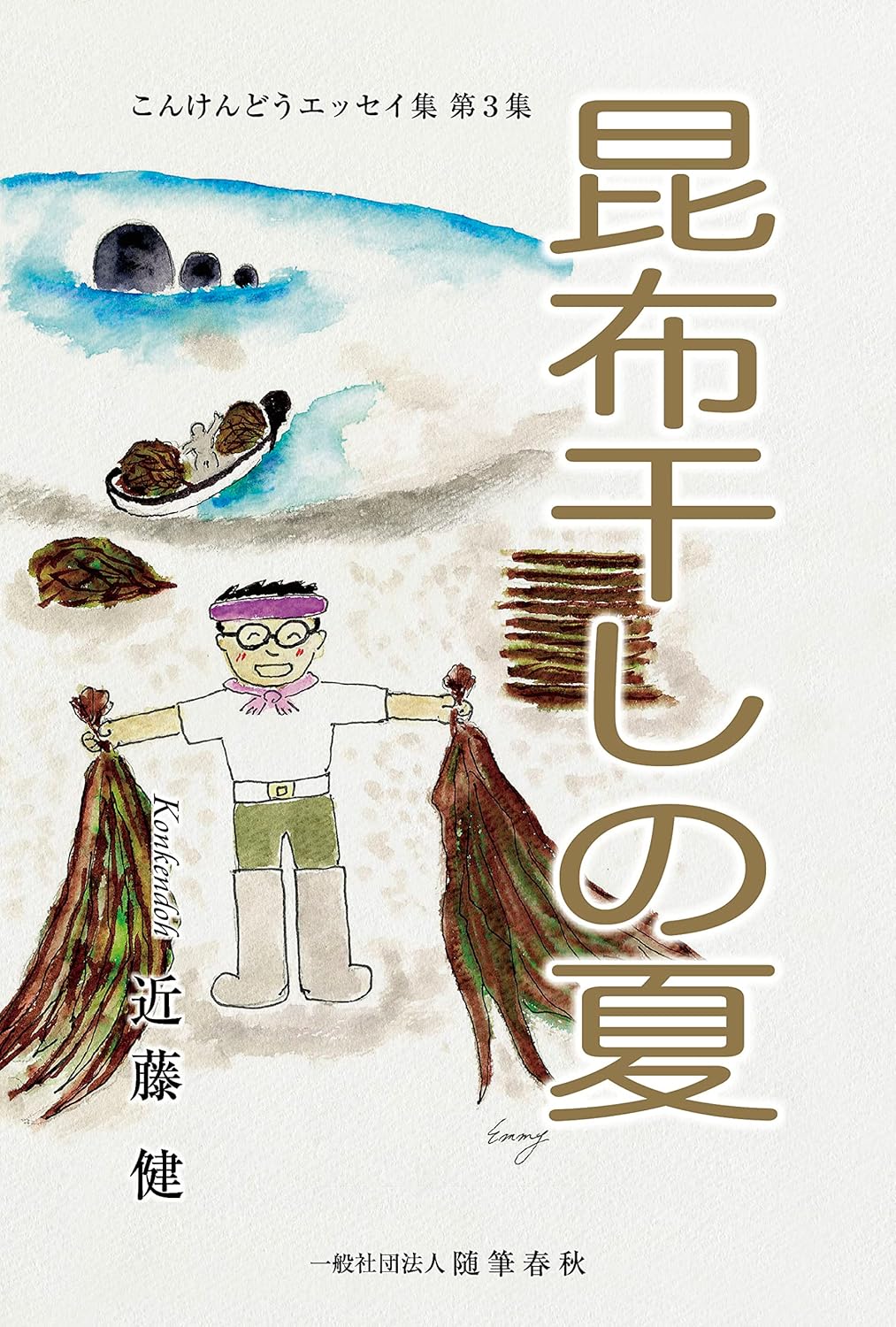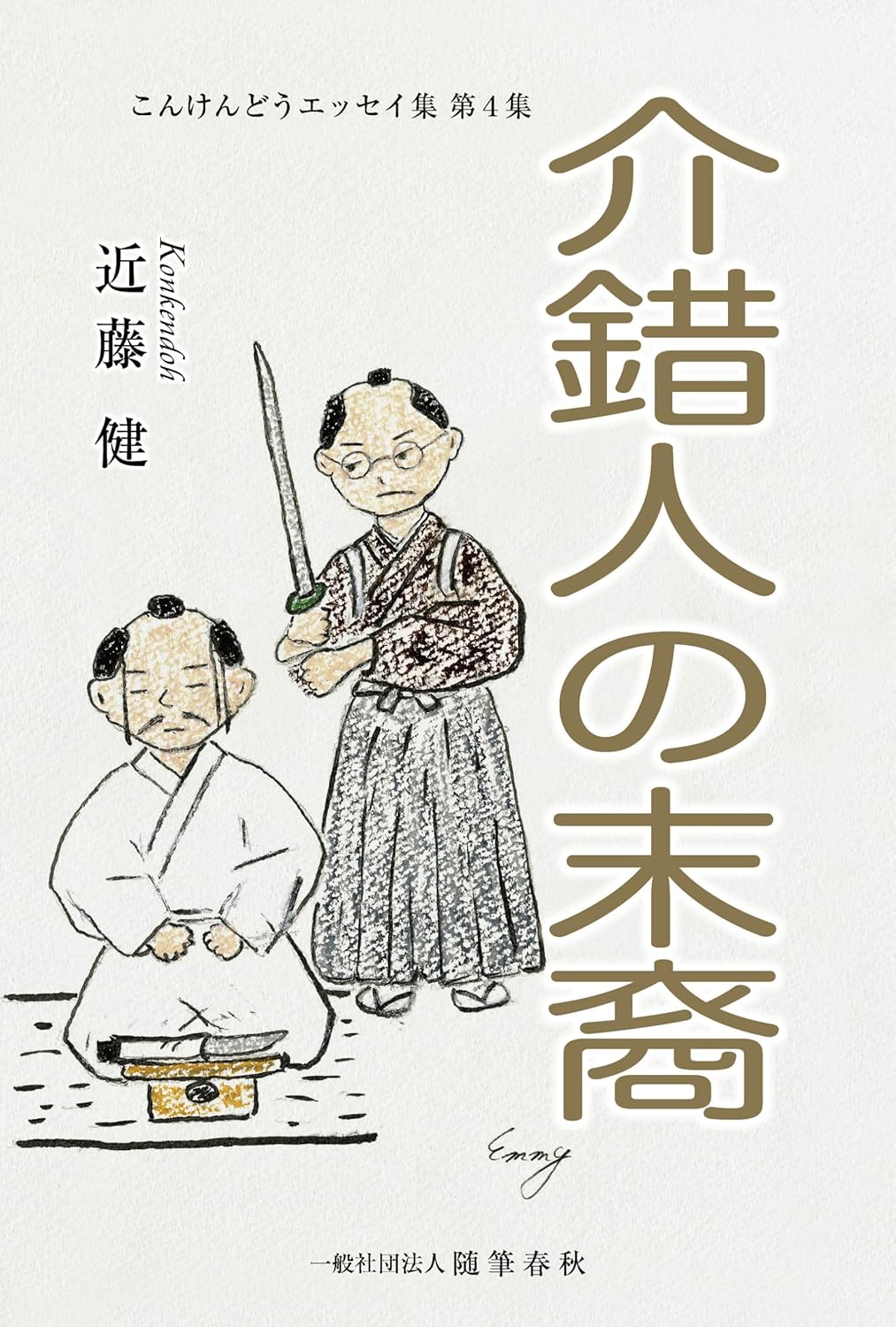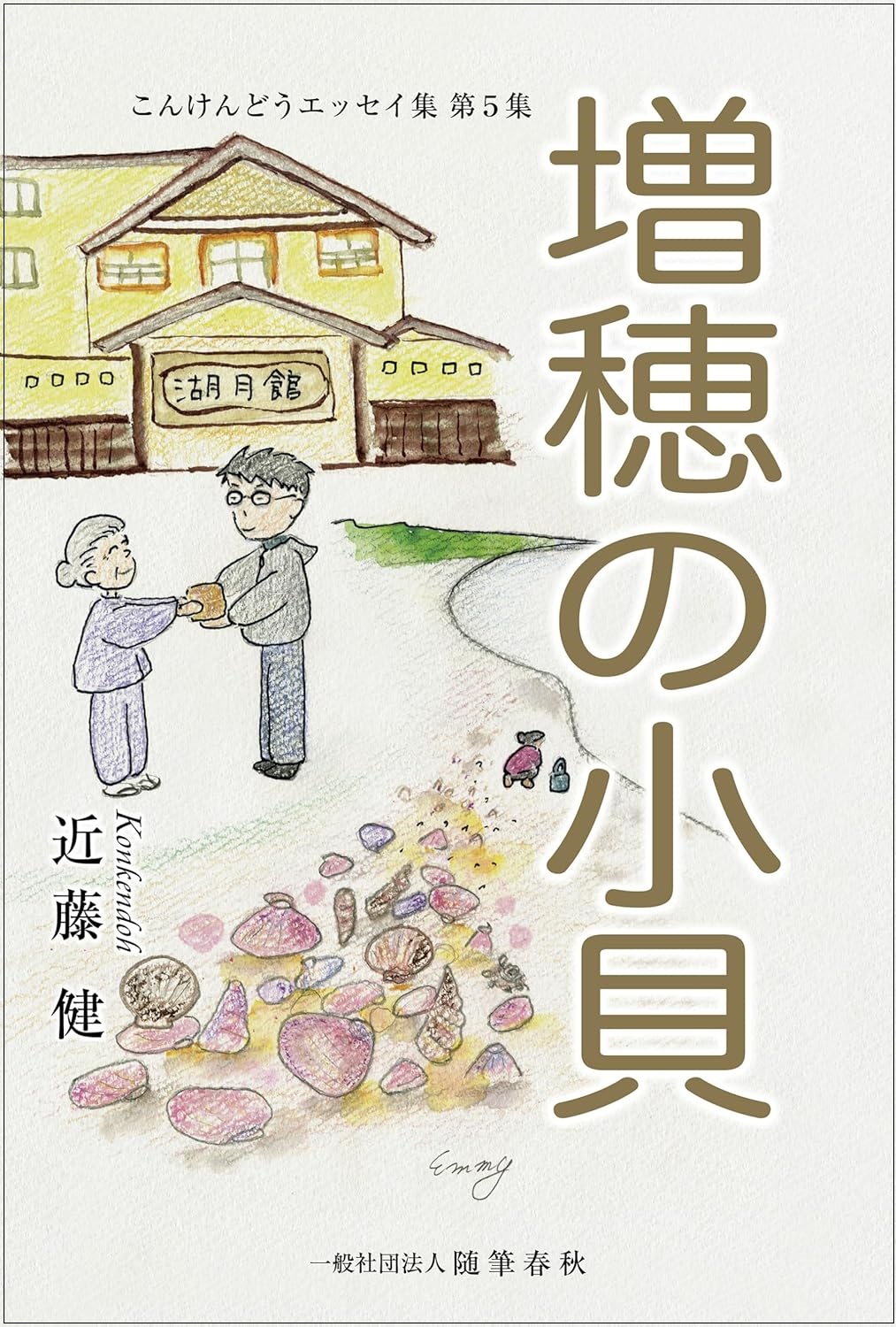第21回・池田元のエッセイ教室
佐藤愛子先生 熱血指導付き
1. エッセイ紹介
2. 状況説明
3. ご指導内容
(※各タイトルをクリックすると当該セクションへjumpします)

佐藤愛子先生が「随筆春秋始まって以来の秀作」と高く評価された作品!
1. エッセイ紹介
母と子と
熊澤 依子
下車客が降りると同時に車内に飛び込み、ドアに一番近い空席に腰を下ろした私は、足下近くにきちんと置かれた大きなスニーカーに気付いた。しかも、座った私のすぐ脇には、真白な木綿の靴下を履いた、これまた大きな足の裏が上を向いているのではないか。
つまり、私の隣の若い男性は、幼時がするように靴を脱ぎ、窓の方向に体を向けて外を眺める格好で座席にいるのだ。
しっかりしたチノパンをはいた長い脚部を折り曲げ、半袖ポロシャツの太くたくましい腕を、開けた車窓の上部にかけて、しきりに窓の外を見ている。しかし地下鉄である。窓を開けているケースなど見たことがない。第一、駅と駅の間は窓の外の風景が見えるわけでもなく、見るものといえば着駅ごとのホームの雑踏くらいのものだろう。この人、いったいどうしたのだろう、私は首を傾げた。
そういえば車内の空気が少々重苦しい。と私が違和感を強く意識し始めた時である。突然、
「次は桜木町、桜木町でございます。JR根岸線は乗り換え、みなとみらい方面においでの方はこちらでお降り下さい。左側のドアが開きます。次は桜木町、桜木町でございます」
と、その若者が大声で叫んだのだ。窓側に向けたままの姿勢で、堂々と、はっきりと。
彼のその声の後、間もなく、本物の車内放送が流れる。彼の大声と寸分の違いもない内容だ。桜木町駅に入った電車は、乗客が入れ代わり発車した。
するとまたもや青年の声があがった。
「市営地下鉄には優先席がありません。お年寄りや体の不自由な方に席をお譲り下さい」
「お客様にお願い致します。車内での携帯電話はほかのお客様のご迷惑になります。電源を切るかマナーモードにして……」
彼の声が途切れると同時に、今度もぴったりと同じ車内放送である。ただし、彼の、
「窓から、顔や手を出すと危険です……」
だけは、彼以外の誰一人窓など開ける人はいないから車内放送は入らない。
次の駅は関内である。彼の案内が始まると、
「まもなく関内、関内でございます。JR根岸線乗り換え、市庁舎へおいでの方はこちらでお降りください。お出口は左側でございます」
続いて、ぴったりと同じ車内放送……
関内駅を出ると間もなく、予想通り、
「次は伊勢佐木長者町、伊勢佐木長者町でございます……」
青年が言い始めた、その時だ。
私の向かいの席で、先刻からじっと後ろ向きの若者を見つめていた四、五歳の坊やが大声で叫んだ。
「ママ、あの人、すごーく上手だねえ!」
愛らしい感嘆の声音だった。私は思わずほほ笑んだ。坊やの並びの大人たちも、柔らかい笑顔になった。
「そうねえ、上手ねぇ」
ちょっと気恥ずかしげに、男児の母親が優しい声で応答した。
親子のやり取りは、車内の空気を一変させた。私はほっとして、
『おばちゃんも、先刻から感心しているのよ、本当に上手ねぇ』
という、共感の笑顔を坊やに送った。
本物の車内放送が流れた。
「次は伊勢佐木長者町……」
とたんに青年はくるりと向きを変え、私の足下近くに揃えてあったスニーカーに足を入れると立ち上がった。一八〇センチを超すような大男だった。
下車する予定の何人かが動きを見せ始めた。その中に、前の座席に座る不似合いなほど大きな黒いリュックを膝に載せた初老の婦人がいた。彼女も下車の様子である。
白髪混じりの髪をさっぱりとしたショートカットにし、Tシャツにジーパンという軽装だが、頬には隠しようのないやつれが見える。彼女が立ち上がろうとした時、その細い柳腰が軽い電車の揺れに少しよろめいた。その瞬間、私は彼女が青年の母親だと直感した。
先刻からの、幼児と母親のやり取りにも他の人も同じように笑顔を見せていたその女性。二十余年、いや三十年以上かも知れない長い年月、特殊な行動を見せ、周囲の眼を集めるわが子に寄り添い続けてきたのであろうひと。穏やかな表情で、静かに耐えることを身につけてきた女性、それが青年の母親だ。
彼女は息子のそばに行くと、抱えていたリュックを彼の広い背に当てた。青年は黙ったまま、機械的にリュックの紐に腕を入れて背負った。
「伊勢佐木長者町、伊勢佐木長者町」
再び放送が入り、下車客がドアの方に動き出し、青年も一歩踏み出そうとした瞬間、母親が息子に向かって一声発した。
「窓!」
小さいが、きっぱりとした一言だった。彼ははっと気づいて、窓ガラスをぐいっと閉めた。電車は伊勢佐木長者町のホームに滑り込んだ。
息子のリュックの背を庇うかのように、後ろから手で支えている母親と、堂々たる体躯の青年とが、ホームの人の流れを歩く姿が窓越しに見える。私は、不思議な、別離の哀感のようなものを感じつつ二人の姿を見送った。母の背と、息子の大きなリュックとが共に雑踏の中に消えた。

2. 情況説明
佐藤愛子先生のご自宅へ
池田 元
2013年6月4日午後2時。随筆春秋事務局員五人は、斎藤信也先生に率いられて佐藤愛子先生のご自宅を訪れた。応接間には高級なソファーが置いてある。しかし広い方に三人、ひじ掛けに二人の合計五人しか座れない。佐藤先生のご指示で、背もたれのない、低いスツールを二つ運んできて、なんとか七人分の座席を作り、小さなテーブルを中心に皆で車座になった。
佐藤先生は誰がなんと勧めても聞かず、座りにくいであろうスツールにお掛けになった。
事務局最年長の熊澤依子先輩も、もう一つのスツールに座った。ソファーにゆったり座った人影が五つ、スツールに背筋を伸ばして座っている人影が二つできた。二人ともそういう性格の人であった。
広いほうのソファーに斎藤先生を真ん中に、上木啓二先輩と三人並んで座るように言われた私は、素直にその通りにはしたものの、緊張して尻がどうも落ち着かなかった。
ひと通りの挨拶と近況報告が終わって、斎藤先生が「随筆春秋も次号で40号を迎えます。豪華な記念号にしたいと思いますが、佐藤先生からお祝いのメッセージを貰えませんか。またそのページには、先生の写真も掲載したいのですが……」とおっしゃった。佐藤先生はあっさり許可して下さった。
斎藤先生は気持ちが高揚したのか「これから佐藤先生の作品は15ページでも20ページでももっとたっぷり載せて、会員たちを喜ばせたいと思うのですが、よろしいでしょうか」と、事前の打ち合わせにはないことを突然言いだした。
佐藤先生は機嫌よく、それも許可して下さった。しかし、だ。
第39号に掲載された佐藤先生の作品は6ページであった。次号から3倍のページ数が必要となると、その印刷コストは跳ね上がる。毎回横浜の小さな印刷会社と、ギリギリの値段交渉をして出版にこぎつけていた先輩方は青くなった。
斎藤先生からの話は済んで、事務局員らの作品講評を、佐藤先生にしていただけることになった。五十音順で私の作品から始めた。斎藤先生だけは目を閉じて座っておられたが、他の全員は持ってきた随筆春秋誌に目を落とし、書いた人間が自分の作品を、大きな声で朗読する。すでに佐藤先生は少しずつ耳が遠くなってきておられたが、背を丸め、食い入るように随筆春秋の誌面を見つめておられた。
講評は順調に進んで、熊澤依子先輩の番になった。

3. ご指導内容
佐藤愛子先生のご指導
池田 元
先輩が作品の朗読を終えた。しばらく沈黙ののち、
「抜群にすばらしい。随筆春秋始まっていらいの秀作じゃないかしら……」
と佐藤先生がおっしゃった。先輩は目を大きく見開いて先生の顔を仰いだ。
「この電車の中でのできごと、しっかりと対象を観察して心に留めている。この作品を良くしているのは『観察眼』です」
私たちは佐藤先生のご指導を聞き漏らすまいと緊張した。このとき、てっきり寝ておられると思った斎藤先生が、目を閉じたまま、突然大きく二回うなずいたので驚いた。
「特に感心したのはねえ。お母さんの描写のところ。白髪混じりの髪をさっぱりとしたショートカットにし、Tシャツにジーパンという軽装だが、頬には隠しようのないやつれが見える。彼女が立ち上がろうとした時、その細い柳腰が軽い電車の揺れに少しよろめいた。その瞬間、私は彼女が青年の母親だと直感した。の、ここですね」
佐藤先生は続けておっしゃった。
「これはね、私にも、お母さんという人が、目の前にいるかのように見えるんです。まざまざとね。そういうふうに丁寧に、それでいて簡潔に描写されてあるんです。熊沢さんの観察眼が素晴らしいわね」
とうなずいておっしゃったとき、熊沢先輩が答えた。
「私、電車でもどこでも、目の前の人をじっと見るクセがあるんです」
佐藤先生は笑顔になっておっしゃった。
「うん、よく見ています。このあとに書かれたお母さんと息子との関係、おそらく作者の想像通りでしょうね。そして『窓!』これが利いているわね。このひと言で母親の性格がわかるんです。親子関係が浮き彫りになる」
私は下を向いて必死でペンを走らせた。佐藤先生の声が頭上から降って来た。
「ラストで作者は、電車の中で偶然出会った親子が、雑踏の中に消えて行くのを見守る……もう会うこともないだろうと予感させる。終わり方も無駄がないんです。事実もおそらくこの通りだったんでしょう。作者はありのままを正確に描いた。それで読者の心にずしんと残るものがあるんです」
私は顔を上げる暇がなかったが、先生がゆっくりと我々を見回して言っておられる気配を感じた。
「作家の感性……作家脳、と私は呼んでいるんだけどね、それがなくちゃ何を言ってもダメなんだけれど、こう、アンテナを立てなさい、皆さん日ごろから……。そして熊澤さんみたいに、よく細かいところまで観察すること。そうしたらね、エッセイの題材になることなんか、そこらにいくらでも転がっているんです。それをたくさん書いてね。書いたら七転八倒して言葉を磨いて、余分なところを削ってね、良い作品に仕上げていくんですよ」
「熊沢さん、さすがね。良い作品について私は、これ以上言うべきことがないわね」
私は先生のその言葉に、熊澤先輩がどんな顔をするか興味があって顔をあげた。先輩はわずかに微笑んで、佐藤先生のほうではなく、まっすぐ前を向いていた。
熊澤依子先輩は千葉の大きなお寺に生まれ、成人後は幼稚園の教諭を定年まで勤めた。
プライベートでは、ご主人を病気で早く亡くされ娘さんがおられたが、このときは横浜で一人暮らしをされていた。余暇の楽しみでエッセイを始められたとのこと。、随筆春秋の同人になられて十二年目で、佐藤先生の絶賛を勝ち取ったことになる。

制作|事務局 正倉 一文
【広告】