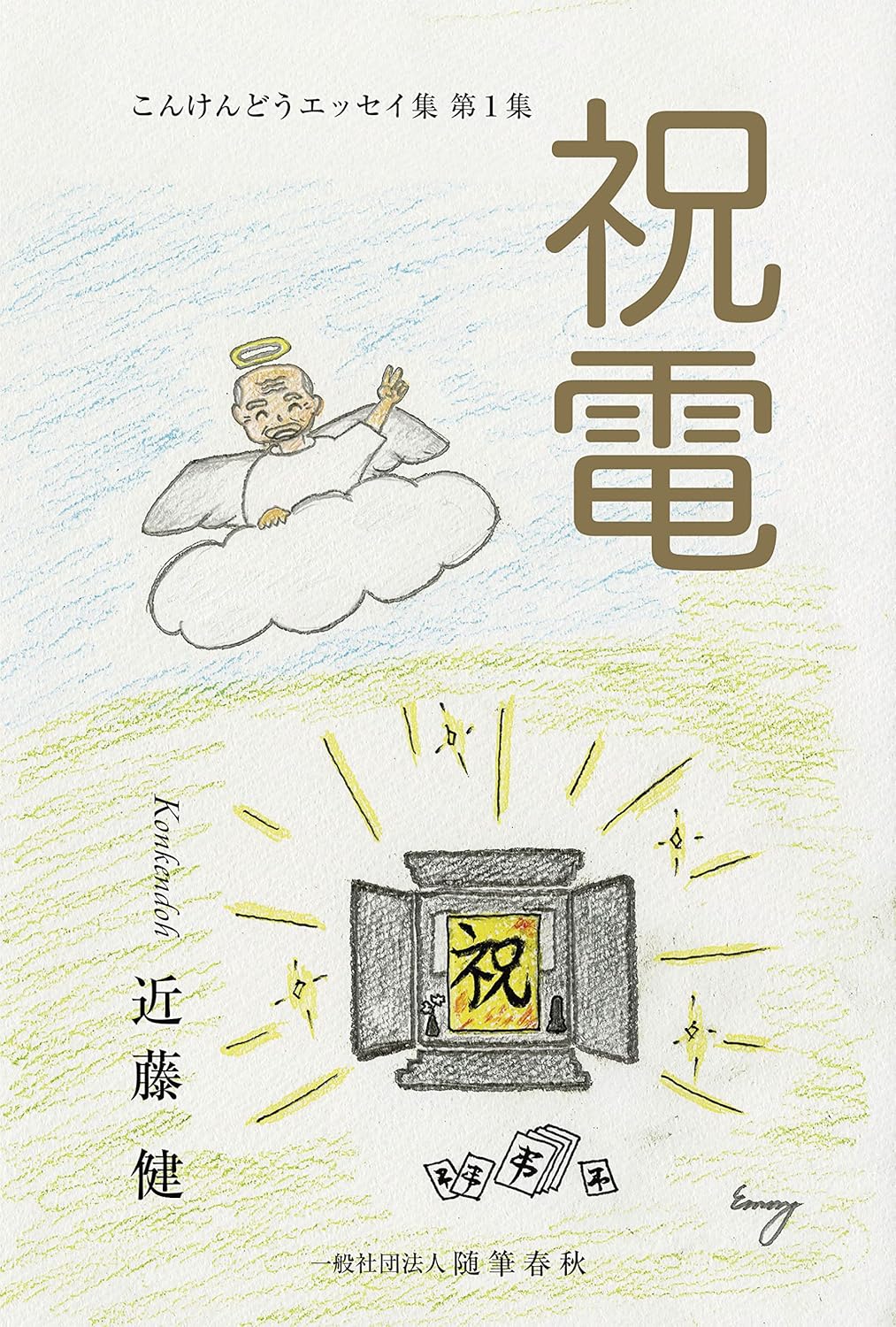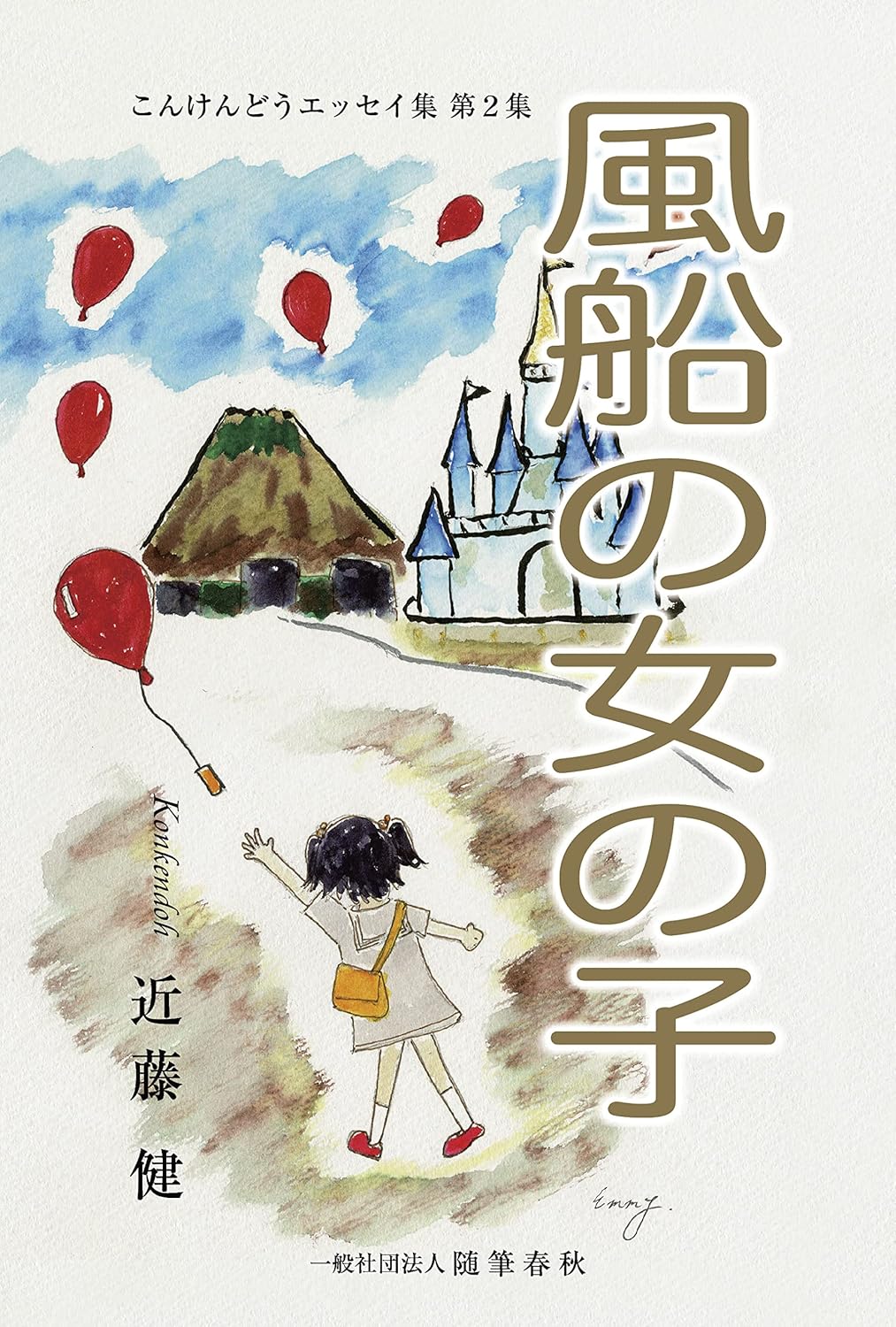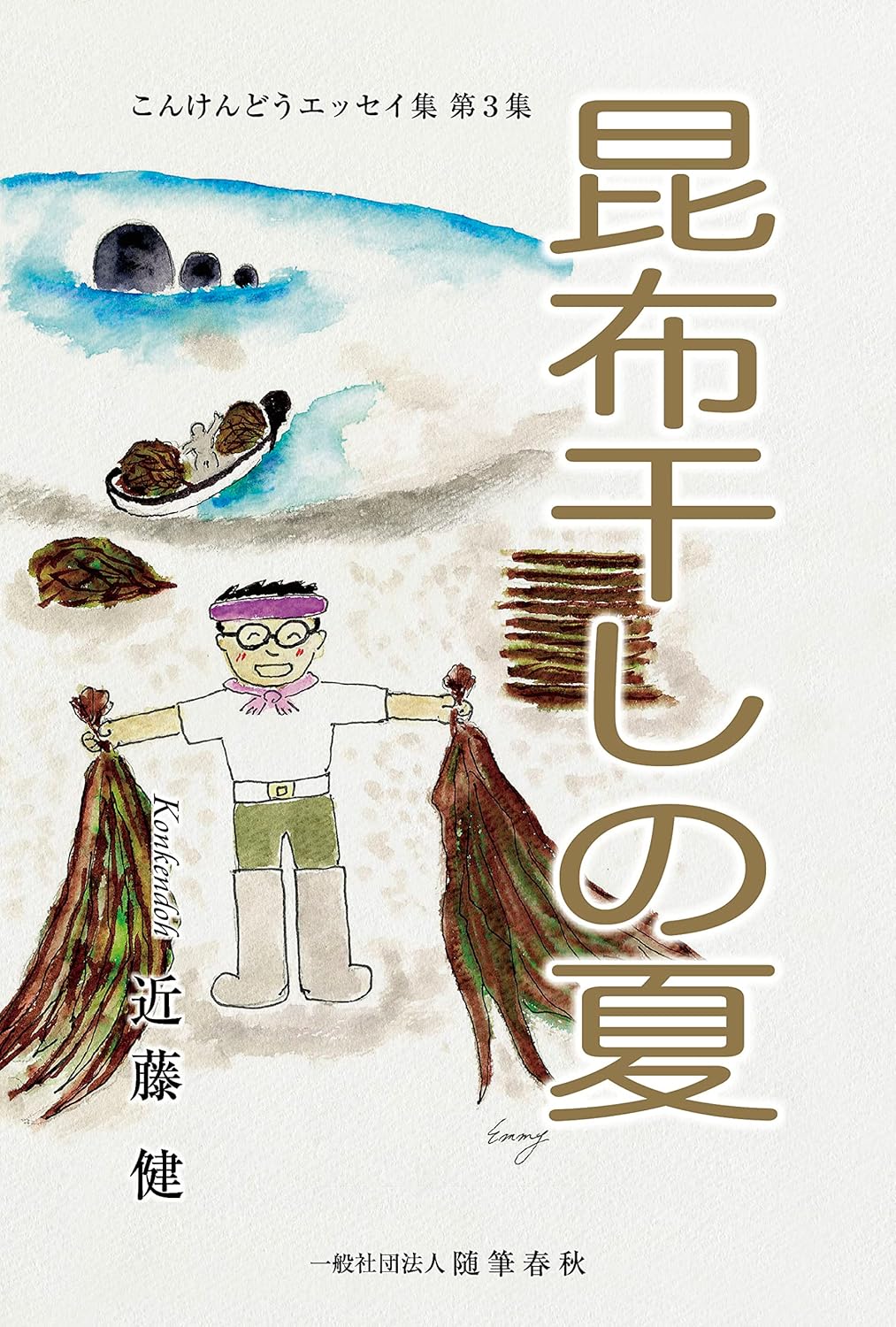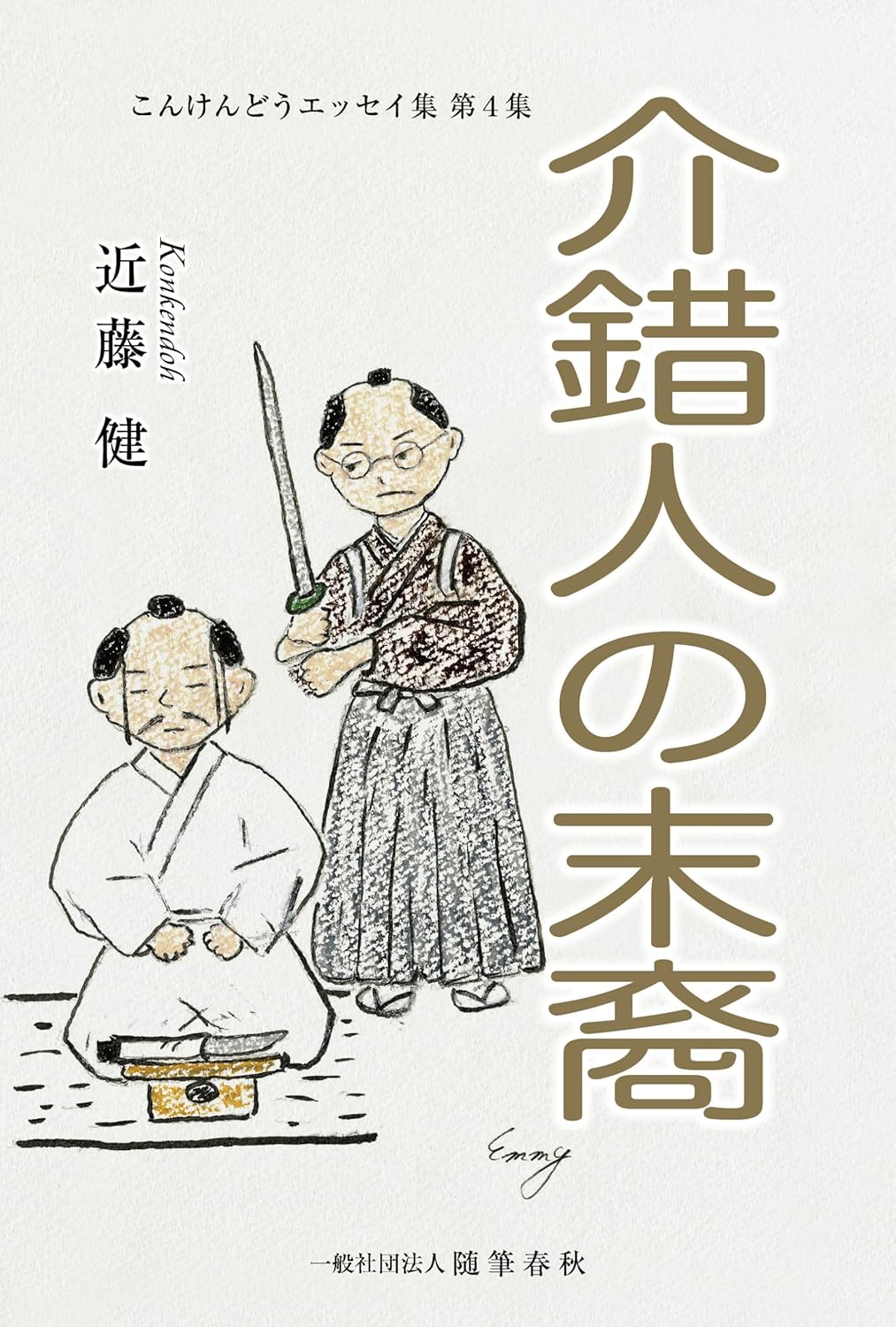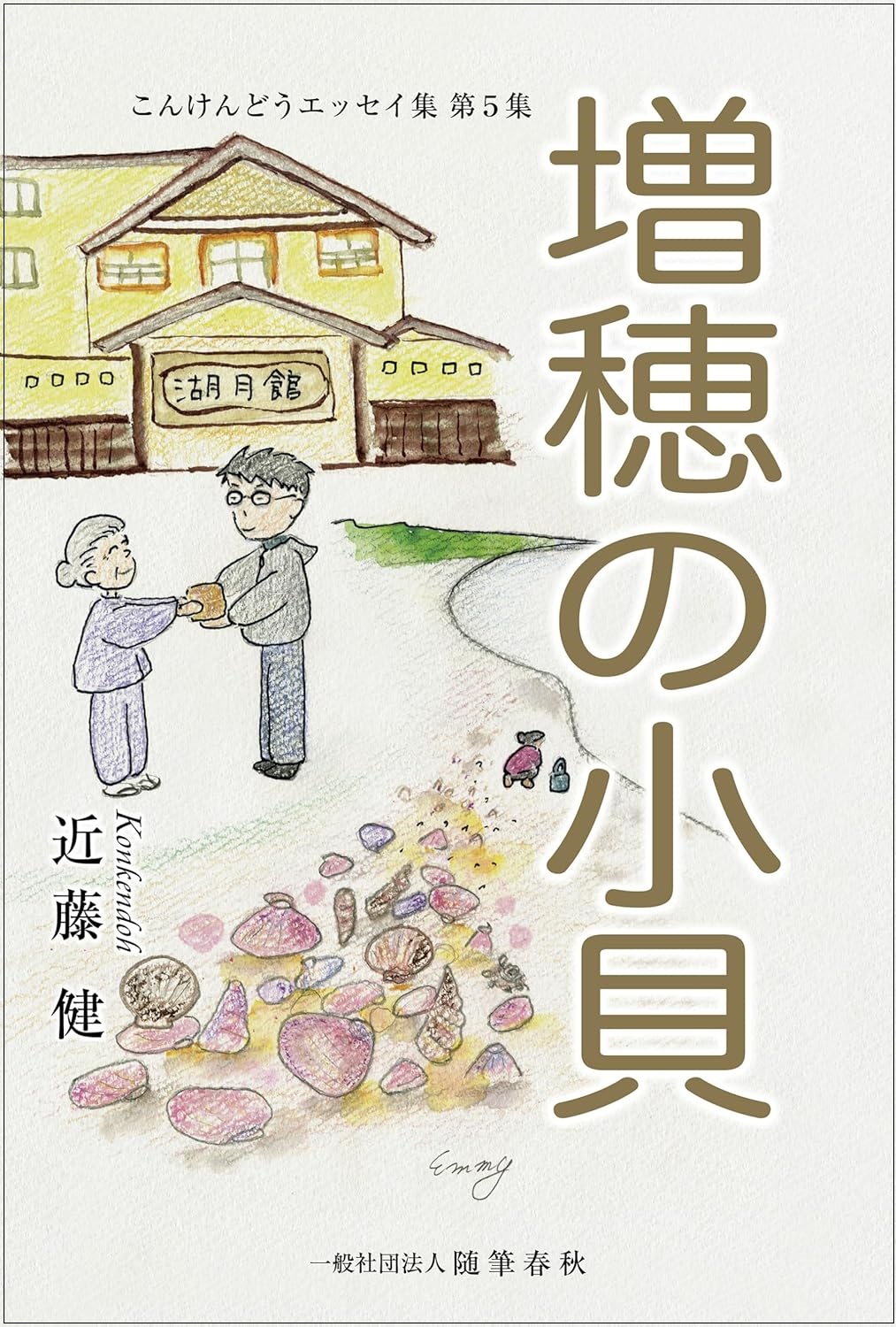第22回・池田元のエッセイ教室
佐藤愛子先生 熱血指導付き
1. エッセイ紹介
2. 状況説明
3. ご指導内容
(※各タイトルをクリックすると当該セクションへjumpします)

佐藤愛子先生が「優れた作品には指摘する言葉がない」と講評された作品!
1. エッセイ紹介
バス停の子
上木 啓二
父が戦死したあと、母は女手ひとつで旭川市のある病院の売店を経営し、私と兄の2人の男児を育てていた。しかし、姑との折り合いが悪く、ある日大喧嘩したのち、兄を連れて婚家を出て、曙町に住む実兄のところに身を寄せた。八歳の私一人が姑のもとに残された。何故、私だけが残されたのか、その理由はわからない。経済的理由で一時的に残されたのだろうと、私は長いこと思っていた。そう思う以外になかった。
しかもそのわけを母に問うのはなんとなく怖くて、聞いたことがない。私がそのことを屈託なく母に問うことができる年齢に至る前に、母は胃ガンに侵され四十一歳の若さでこの世を去った。
だが、ようやく近頃になって、本当の理由が別にあったのではないかという疑問が浮かんできて、私は事の真相を知りたいと思うようになった。
長男である私の父を戦争で失った祖母は、上木家の跡継ぎとして、二人のうちどちらか一人を残して行くことを母に要求したのではないか。それならばなぜ母は兄ではなく、私を残す選択をしたのか。
「母は私を捨てたのだろうか……」
食道ガンが再発した71歳の兄を見舞いに旭川に帰ったのは、平成二十二年の七月であった。やせ細った兄は、自分の最期が近いことを感じながらも、いつもと変らぬ日常を淡々と過ごしていた。
私は兄を見舞ったついでに、同じ旭川の私たち兄弟が生まれた実家に一人で住んでいる叔母を訪ねてみようと思った。私たち兄弟の幼い頃の事情について知っているのは、もはや今年八十六歳になるその叔母一人しかいないのだ。だが、伺う前に電話を入れたところ、叔母はすでに私が誰であるかもわからない状態になっていて、警戒心露わに電話を切られてしまった。
もはや事実を知る術はなくなった。もしかして兄は知っているのかもしれないと思い、私はその夜、話を切り出してみた。
私と二歳しか違わぬ兄も、そのときはまだ小学四年生であったから、本当の事情がどうであったのかやはり知らなかったし、後年になってから母から聞いたこともない、ということであった。
跡継ぎとして残されたにしては、私は祖母から冷たくあしらわれた。ある日、かなり遠くの親戚に徒歩で使いに出され、ようやくの思いで家に帰ったら、すぐに市場に行って配給のパンをもらってくるように言われ、足が棒のようになっていた私はたまらず泣いた。泣いている私に祖母の叱責が飛ぶ。
私は買い物袋を投げ出すと、家を飛び出した。痛む足を引きずりながら、母のいる病院を目指して歩いた。ようやく売店について母の顔を見た途端、私の目からは大粒の涙がとめどなく溢れてきた。母も泣いた。私の涙の理由など聞かなくても、母にはすべてがわかった。婚家に長い電話を掛け、その日から私を曙町に連れて帰った。
祖母のもとに置かれていたのは半年かあるいは一年ぐらいではなかったかと思う。私の中では、辛くて寂しかった当時のことは記憶から消し去りたいという思いが強く、よく覚えていないが、誰もいない八畳間の畳の上に仰向けに寝て、目にはいっぱい涙を溜めたまま、じっと天井だけを見つめていた少年がいたことは忘れることができない。
いま翻って考えてみると、母や兄と別れて暮らしたあの孤独な一時期が、私の幼心に与えた影響は大きかった。吃音癖に気づいたのは、あのころであったと思う。学校の国語の時間が一番辛かった。つっかえつっかえ読み、ときには絶句してしまう。吃音癖は大学を出て社会人となっても続いた。恥ずかしい思いの数々が、いまも私の胸の奥底に潜んでいる。吃音がなかったら、私はもっと別の人生を生きることができたのではないかと思う。
だが私は母を恨んではいない。父の死後十六年間、母はほとんど休まず、子供のために必死に働いて病に倒れた。私を婚家に残して行ったのには、よほどの事情があったのだろう。いまになってはその真相を知る者は誰もいない。私は本当の理由を知ることなく人生終わるのだろうか。
「いや、それでいいのだ」と心の中のもう一人の私が言う。
その夜、兄が当時のことを思い出したと言って、こんな話をした。
「啓二のところにはバスに乗って、よく遊びに行ったよ。でも夕方になって俺が帰りのバスに乗る時、啓二はいつもバス停の近くの縁石に座って、寂しそうに俯いていたのを覚えているよ」

2. 情況説明
佐藤愛子先生のお宅訪問
池田 元
2012年5月29日午後1時半。事務局全員で佐藤愛子先生のご自宅を訪問するので、池田さんも来なさいと言われて、渋谷のハチ公前で皆と待ち合わせた。
しかし斎藤信也先生だけが来ておられない。事務局の先輩に「そこらの喫煙所を探してきなさい」と言われて見に行くと、果たして先生がおられた。私が促すと、斎藤先生はゆうゆうとタバコの煙を吐き出しながら「ちょっと待っていなさい」と言う。吸い終わってから皆と合流し、三軒茶屋まで移動すると、佐藤先生とお約束の2時を少し過ぎていた。
先輩の一人が斎藤先生に「タバコのせいで遅刻した」と、笑いながら苦情を言うと、
「あのな、作家なんてものは2時に約束したら2時をちょっと過ぎてから訪問するもんだ。会社員みたいに5分前に行こうなんて考えるのはダメだ」
と言って平然としておられた。
佐藤愛子先生は、遅刻した我々を上機嫌で迎えて下さった。
私が佐藤先生にお目にかかるのは3度目だった。初回が「晩鐘」の取材のとき、2度目は随筆春秋賞の表彰式、そして今日である。しかし今日は佐藤先生の前というだけでなく、斎藤先生や事務局の先輩方と一緒の訪問なので、緊張して固くなっていた。
佐藤先生は私たちが持参した和菓子の包みを開けて、「おもたせですけど、どうぞ」と出して下さった。お茶も高級品だった。斎藤先生は佐藤先生に、
「先日の表彰式には、ご出席ありがとうございました」
と礼を述べた。佐藤先生は、
「どういたしまして。斎藤さんは、あいからわずハーモニカがお上手ね」
と褒められて、斎藤先生はエヘヘと照れた。私は表彰式のクライマックスで、いきなりハーモニカの独奏が始まったのを見て驚いたのだが、佐藤先生の言葉で、斎藤先生のハーモニカはいつものことだったのだと悟った。
斎藤先生は朝日カルチャーセンターの講師として、全国各地にエッセイ教室を持っておられたが、最近は生徒が減る一方で、いくつかの教室では閉鎖が決まったいう報告をされた。また日本エッセイスト・クラブの「ベストエッセイ選」の選者を長年お勤めであったが、本が全然売れなくて、発行元の文藝春秋社が困っているという話もなさった。
佐藤先生も眉をひそめてうなずいておられたが、この場にいる人たちで有効な対策が思いつくわけでもなく、
「そうは言ってもお互い半端者で、書くことしかできない人間なんだから、せいぜい死ぬまで頑張りましょう」
ということになって斎藤先生の話は終わり、事務局員らの作品を、佐藤先生から講評していただけることになった。五十音順で私から始めるという。
私は「晩鐘」の取材のときも、表彰式でも「苔のテレポーテーション」に対する講評をいただいていたので、今日はもう遠慮しようと思ったが、それはダメだと佐藤先生に叱られて、命じられるままに自分の作品を大きな声で朗読した。
朗読後、佐藤先生からコテンパンに厳しく指導を受けた。私の作品を題材にして、その場にいる全員にも間接的に厳しい指導をなさったのだ。さらには先輩方にも矛先が向き、
「あなたたちも何か言いなさいよ。黙って座っていたんじゃ、わからないじゃないか」
と𠮟咤激励された。かつて先生がおられた同人誌「文芸首都」では、お互いの作品を題材に侃々諤々と論争し、切磋琢磨したものだという話もされた。
「私の作品なんかね。もう目も当てられないほど酷評されるわけですよ。それなりに自信をもって書いた作品もね。そんな中でね、こん畜生、次こそはと闘志を燃やしたのね」
コロナ前には恒例であった佐藤先生の勉強会は、いつもこんなふうに激しかった。
後日のことになるが、勉強会に向かう途中、ご自宅へと続く坂道で、
「ああ、まるでギロチン台に上っていくような気がする……」
と一人の先輩が言ったのを、皆で大笑いしたこともあった。そのころには私も、その先輩の気持ちがわかるようになっていた。
この日の講評は順調? に進んで、上木啓二先輩の番になった。

3. ご指導内容
佐藤愛子先生のご指導
池田 元
上木先輩が読み終わるや否や、佐藤先生はこの作品を称賛された。
「うん、いいですね。作者を含めた登場人物の心象がよく描けている。特に終わりのところ、夕方になって俺が帰りのバスに乗る時、啓二はいつもバス停の近くの縁石に座って、寂しそうに俯いていたのを覚えている、はいいわね。この台詞で、男の子が夕闇の中、ポツンと寂しそうに座っている様子が、私の瞼にも浮かび上がってくる」
佐藤先生は機嫌よく続けた。
「お母さん、おばあさんのことも、よく書き分けられています。上木さん、この作品でひとつの境地に達したわよ。良かったわね」
先生は冷めたお茶をすすった。皆、まだ先生の口元に注目して、指導の続きを待っている。先生は周囲を見回しておっしゃった。
「これで終わりよ。良いという作品には、もう、あれこれいうことがないんだから」
私は上木先輩の顔が、下から次第に真っ赤になって行くのを見た。言葉にならないほど嬉しかったのだ。ありがとうございます、と月並みな御礼の言葉さえ先輩は発さず、ただ深く先生に向かってお辞儀をした。佐藤先生は手を振ってそれを制し、
「いや、良いって言ってもね、まだ所詮はアマチュアですよ。プロの物書きだったら、ここからさらに言葉を選んで行かなきゃならない。文章を磨くということね。余談だけれど、あなたたち、向田邦子さんを知っているでしょう? 彼女は本当に文章がうまかったの」
「たとえば地の文(会話文ではない部分)では、敬語や丁寧語を使う必要がないの。ご飯を食べた、なんて変な言葉を使わないのよ。彼女の書いたものを読んでごらんなさい。無駄がなくてスッキリしている。それでいて、作品を面白くする糸口を逃さないのよ」
佐藤先生は上木先輩の作品を指でなぞって、
「たとえばこの作品ではねえ…………そうそう、ここのところ。もはや今年八十六歳になるその叔母一人しかいないのだ。だが、伺う前に電話を入れたところ、叔母はすでに私が誰であるかもわからない状態になっていて、警戒心露わに電話を切られてしまった」
「ここはねえ、こんな地の文で長々と説明しないで、上木さんと叔母さんとの電話のやり取りを会話文で書くのね、面白く。それが向田作品の特長だった。皆さんも研究してごらんなさい」
上木啓二先輩は成績優秀で、現役で早稲田大学に入学したが、学生運動の盛んな時期で授業がなかった。強制的にデモに参加させられ、機動隊の警棒で前歯を折り飛ばされ失神するという大災厄に遭った。その後、やくざに弟子入りして賭場の管理を任せられるなど、危険な学生時代を送ったが、社会人になってからは人が変わったように真面目になり、このときは高齢ながら損害保険の代理店をやっていた。
ホームページを見て随筆春秋に入会してこのとき四年目。「バス停の子」では佐藤先生に褒められたが、その後の作品で「これはダメ」、と厳しく指導され、「自分はまだまだ精進が足らない」と反省していた。

制作|事務局 正倉 一文
【広告】