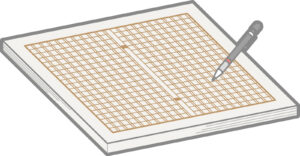近藤 健が校閲とあとがきを担当しました。
「あとがき」全文
この本は、作者の自分史というより、夫婦がともに歩んできた航跡である。他人の半生記などを読んで、何がおもしろい? というのが当初の正直な気持ちだった。だが、読み進めていくうちに、前のめりになっている自分がいた。
波乱万丈、禍福は糾える縄の如し、人生の帳尻は……そんなお決まりのフレーズが頭をよぎる。誰しも人生の起伏の中で暮らしており、波乱万丈とはいえないまでも、それなりの荒波というかウネリと対峙しながら生きている。夫婦生活というのはそういうものである。
だが、この本の読み応えは、幾度となく襲ってくる困難に対し、夫婦が真正面から挑む姿にある。登れぬような山をやっとの思いで這い上がったら、その遥か向こうには渡れぬような河が流れていた。そんな現実を前にして、この夫婦は絶望しないのだ。絶望してもすぐに顔を上げる。その先にある希望を信じて邁進していく。その姿に感銘を受けるのだ。
東京の目黒で生まれ育った夫婦が家業の拡大に伴い、まったく見知らぬ土地である静岡の田園風景の広がる土地へと移り住む。しばらくすると順調に推移していたその建材会社が、石油ショックの余波を受け大きく傾く。結果的に親の負の遺産を引き受けてしまうのだ。それをさほど苦とは思わないのだ。
夫婦が住む静岡県袋井市とその南にある浅羽町は、メロンの産地である。メロンの栽培は、一本の蔓に一個のメロンを実らせるために、生育のよくない幼果メロンを除去していく。この間引き作業を「摘果」というのだが、その捨てられる摘果メロンに目を付けるのだ。こうして誕生したのが「子メロン漬け」(メロンの漬物)だ。
おりしも郵便局の「ふるさと小包」のスタート、さらには全国のグルメブームとも相まって、「子メロン漬け」は静岡県の名産品にまで上り詰める。つまり、全国へ向けて販売されるようになるのだ。店舗数も急拡大するのだが、やがてそれにも陰りが出てくる。
結局、最終的にはお店をたたむことになるのだが、その間にも「赤花そば」や「たまごふわふわ」などの新たな商品が、小さなヒントから生まれていく。その行動力が小気味いいのだ。
とにかくフットワークが軽快である。たとえば、「去年の春、長崎を目的にして九州を旅行したとき、湯けむりのもうもうと立つ別府に二泊した」とある。単なる別府ではなく、「湯けむりのもうもうと立つ別府」なのであって、それだけでもうこの土地が気に入ってしまったことが窺える。作者の筆遣いの巧みさが垣間見られる。旅行から帰ってきたら、すぐに別府の空き家情報を検索し始めるご主人がいる。「夫は思いつくと同時にすっかりその気になる」ところがあり、作者も多少の不満はあっても「人の気持ちにすぐ沿ってしまうのが私の性」ということで、進んで渦中に身をおいてしまう。
この夫婦は、希望の見えない日常の中で、拍子抜けするほどに悲壮感が希薄なのだ。そのタフさは、一体どこからくるものなのか、そんなことを考えながら夢中で読むことになる。
「五十年間、この性癖のある人と一緒に生きてきたために、どれだけ苦労したことか」
アイデアマンのご主人とそれに巻き込まれながらも、楽しんでいる節がある作者がいる。お二人が融合することで大きな原動力が生まれ、事業が展開していったことが窺える。
人が「動く」ことで物事が進んでいく、そんな前向きの姿勢がお二人を突き動かしてきた。このアクティブな姿勢が、子や孫たちに受け継がれていくことになるのだろう。
後半になると、作者ご自信の身辺を題材としたエッセイが配されている。学生時代の想い出や現在の様子などが綴られている。それらは多種多彩で、作者の守備範囲の広さを感じさせる。だが、それらはすべて夫婦の航跡に帰結し、また、そこから発しているもののような錯覚を覚えるのだ。
夫婦にとっては大変な人生だったのだろうが、羨ましい思いが沸き起こってきてならない。それが本書の最大の特徴である。
2019年11月21日 随筆春秋代表 近 藤 健