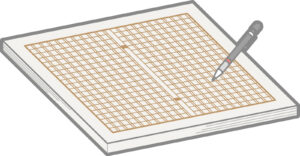近藤 健が校閲とあとがきを担当しました。
「あとがき」全文
私は現在札幌にいて、東京を訪ねるのは随筆春秋賞の授賞式へ出席するときだけになってしまった。式典が終わると、記念撮影の後、懇親会へと移行する。更井さんにお目にかかるのは年に一度、そのときだけである。更井さんをお見かけするようになってどれくらいになるだろうか。
私もユーモア路線であるが、更井さんもまたそうである。私が随筆春秋に入会したころの代表は斎藤信也先生だった。斎藤先生に初めてお目にかかったとき、
「泣かせるものはみなさんお得意。なるほどな、と納得させるものはさらにお手のもの。でもね、ユーモアの書ける人は一〇〇名の会員さんの中でも、わずかに三、四人なんです。だからね、ボクは嬉しいんだよ」
ユーモア路線の仲間が増えたことを素直に喜ぶ言葉だった。斎藤先生がいらっしゃったら、おそらく同じ言葉を更井さんに投げかけたに違いない。
更井さんとはこれまで、簡単なあいさつ程度の会話を交わしたくらいで、一対一でじっくりとお話しする機会はなかった。ただ、更井さんの作品には、もうかなり前から接しており、作品をとおして更井さんとは親しくさせてもらっている。
作中にも頻繁に出てくるが、更井さんには若き日々を過ごした渋谷に特別な思いがある。佐藤愛子先生も若いころ、北杜夫さんら同人誌仲間と渋谷の街に繰り出しておられ、先生の若いころのエッセイにはそんな場面がよく登場する。私の勝手な思い入れなのだが、更井さんが醸し出す独特な雰囲気を遠巻きに眺めていると、佐藤先生らの若い日々と重なる部分を感じる。
世間の流れに迎合するでもなく、本を読み、音楽を聴き、ほとばしる熱い思いを時間を忘れて語り合う。ときおり自分の目指している方向がわからなくなり、いき場のない焦り、将来に対する大きな不安、そんなものを仲間とともに分かち合ってきた。そんな光景が透けて見えるのだ。
私は大学を卒業してから一貫してサラリーマン生活を送っている。二十八年間の東京生活のなかで、長年、渋谷をとおる通勤をしていた。意味もなく渋谷の街を歩き回り、名曲喫茶ライオンで一人の時間を過ごしてきた。ふるさとは? と訊かれると、渋谷だと答えていた時期があった。渋谷にマークシティーなる再開発地域ができて、渋谷は私の街ではなくなった。
「先生、渋谷にはまだライオンがあるんですよ」
何年か前、そんなことを佐藤先生に伝えると、
「そうみたいね。若いころはよくいったわよ」
と仰って目を細められた。そんな情報までご存知だったことに、逆に驚く思いがあった。
更井さんの作中には、何人ものユニークな人物が登場する。描き方によっては、できすぎたシチュエーション、作り物めいたお話になってしまいかねない。だが、きわどいラインでうまく体をかわし、そんな印象を与えないのだ。しかも、頻繁に読者を裏切る。意表を衝くストーリー展開にハッとさせられる。そんな素人離れした筆遣いに、思わず唸ってしまう。
同人誌『随筆春秋』は、年に二度発刊されるのだが、更井さんの掲載原稿が事務局に送られてくると、スタッフの間では待っていましたとばかりに競って読まれるという。更井さんは、すでに特別な光彩を放つ存在でいらっしゃる。
悲しみや不条理、抗しがたい老い、目にあまる今風な若者、いずれも滑稽である。そんなもの一切合切を笑いのオブラートで包み込む。その笑いが大きければ大きいほど、行間から滲み出てくる悲しみの重みがずっしりと響いてくる。笑っていながら、心の中でそっと涙を拭う、そんな珠玉のエッセイ集の完成に、乾杯!
2019年07月28日 随筆春秋代表 近 藤 健