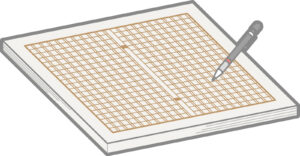近藤 健が校閲とあとがきを担当しました。
「あとがき」全文
この作品集の柱は、冒頭の十一章からなる教員時代のお話である。若さ漲る初々しい娘が、教員採用面接に臨むところから始まる。命じられた赴任先は、北海道・江差町から四十キロほど離れた小さな漁村である。作中、どこの村なのかは明かされていないが、自然豊かでのどかな村である。そこで暮らす純朴な人々との交流が、余すところなく語られている。
作者である瀧沢鈴さんが赴任したのは、昭和十九年(一九四四)三月である。七十六年前のことになる。
「こうして我が家から、職業婦人第一号なるものが誕生したのであった」
この「職業婦人」という言葉が、その時代の気分というか、これから始まる新生活への大きな期待を現わしている。だが、ここまで書いてきて、ちょっと待てよ、と首を傾げた。瀧沢さんは一体、おいくつになられるのだ? 事務局に確認してみると、今年の秋で九十四歳だという。思わずのけ反った。文章が若々しくて、とてもそんな年齢には思えなかったのだ。数年前に一度、東京でお会いしているのだが、それほど年齢を感じさせる方ではなかったので、改めて目を丸くした。
太平洋戦争の終結は、昭和二十年八月である。つまり、瀧沢さんが新人教員として赴任したのは戦争真っただ中、しかも戦況が刻々と悪化していく状況下でのお話になる。だが、本書では、この国家存亡の危機によくある暗いムードが漂ってこない。物資が欠乏する中でのお話だが、そんなことを感じさせないのだ。それは豊かな自然と、そこで暮らす人々のおおらかさがそうさせているのだろう。だが、なんといっても十八歳という作者の若いエネルギーが、沈滞ムードを払拭しているのだ。
ただ、そんな中でも、お兄様の帰還の話は圧巻である。
旭川第七師団に入隊したお兄様が、昭和二十年春に樺太へ向かうとの一筆を残し、音信が途絶えてしまった。終戦を迎え、続々と帰還兵が戻ってくる。
そのころ、よく当たると評判の八卦のお婆さんの噂を耳にし、瀧沢さんは家族に内緒で密かに婆さんのもとを訪ねる。すると、お兄様の写真をじっと見ていた婆さんが、
「この人はとっくに亡くなっております。あきらめなさい。もうシベリアの氷土の中でしょう」
と言われ、言葉を失って帰ってくる。だが、家族にはそのことが言えない。早く帰還したお兄様の同僚や部下たちが、引き揚げ船から真っすぐにご自宅を訪ね、お兄様の消息を知らせてくれる。母親は涙を流しながらその話に耳を傾ける。その姿がいたたまれない。しかし、肝心のお兄様は一年経っても二年経っても戻ってこない。その間にも帰還兵が次々と訪ねてくる。すでに亡くなっていると言われたことを、口にすることもできず、瀧沢さんは身を切られるような日々を過ごす。
「寒い冬になった。いつものように一人の兵隊が我が家を訪ねてきた。汚れて破れた軍服。左右の靴は形も色も違っていた。今まできた人たちの中では、一番みすぼらしく見えた。その姿に私は胸がいっぱいになった。随分と苦労なされたことであろう。しかし、それが待ちに待った兄だったとは。私たち家族は抱き合い、涙も拭かずに声を上げて喜んだのであった」
戦争が終わると、赴任先の小さな村にも復員兵の姿が見られるようになる。その中には元教員もいた。結局、瀧沢さんは地元の復員兵に職を譲る形で退職する。戻ってこいという親からの強い要望もあった。失意のうちに辞めることになるのだが、その別れのシーンは涙なしには読むことができない。
全校生徒に見送られてバスに乗る。どこまでも追いかけてくる子供たち。それに気づいた運転手は、バスをゆっくりと走らせる。自転車で追いかけてきた教頭に制された子供たちは、みな肩を震わせて泣いている。そんな子供たちに瀧沢さんは後部座席で手を振っていた。やがてバスは峠を上り子供たちの姿も見えなくなる。
「はっと我にかえり、前の席に戻る。車内の人にありがとうございました、すみませんでしたと頭を下げる。そして運転手にありがとうございましたとお礼をいったら、運転手は頬に水滴をつけながら、にこにこして何度も頷いた。乗客の四人も皆涙を拭っていた。村の人々の優しさにふれた私は、改めて涙を流したのである」
とにかく、この地域の人々は、だれもが底抜けに心優しい。厳しい自然の中で、歯を食いしばって暮らさねばならない土地である。互いに助け合わなければ生きてはいけない。そんな中で暮らしていると、心がどんどん純化されていき、汚れのない純朴な人間ができあがる。いや、違う。これが人間本来のあるべき姿で、都会生活に浸っている人々の生き方がいびつになってしまったのだ。
函館生まれの瀧沢さんがこの村で暮らしたのは、わずかに三年である。そこで築き上げてきた人々との太い絆が、別れの辛さの描写となってラストを飾っている。
瀧沢さんご自身は、本書の「はじめに」で、自身の若き日の教員生活を、夏目漱石の『坊ちゃん』の愉快さに似た体験と記されている。だが、私には、壺井栄の『二十四の瞳』を彷彿とさせるものがあった。
『二十四の瞳』は、師範学校を出たばかりの若いおなご先生が小さな漁村の教師として赴任してきて、そこで繰り広げられる十二人の子供たちとの物語である。やがて戦争、そして終戦を迎える。時代の波に翻弄されながら描き出される師弟愛。この『二十四の瞳』は、昭和二十七年(一九五二)の刊行で、空前のブームが巻き起こり、のちに不朽の名作と称される。
瀧沢さんはその前年の昭和二十六年に結婚され、そのころは函館の小学校で再び教壇に立たれていた。当時は、この『二十四の瞳』にご自身を重ねられる部分も多かったのではないだろうか。
瀧沢さんは、平成二十二年(二〇一〇)、八十四歳で執筆を始められた。本書はその十年間の集大成である。本書には、ほかに数編の作品が収録されている。なかでも、「ゆずり葉の花咲く村」は、前作同様、戦中・戦後の地域社会における学校の立ち位置を知る貴重な資料となろう。
私は昭和三十五年(一九六〇)に北海道の小さな漁村様似で生まれ育っている。小学校の運動会が地域社会にとって最大の年間行事であり、誰もが心待ちにしているものであった。本書は遥か彼方に忘れ去られていたそんな光景を、目の前に思い起こさせてくれるものであった。
2020年5月23日 随筆春秋代表 近 藤 健