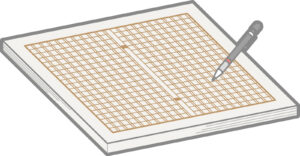近藤 健が校閲とあとがきを担当しました。
「あとがき」全文
今年、二〇二〇年は記録的な暖冬だと言われていた。確かに北海道の降雪量も例年に比べ極端に少なかった。だが、二月に入って季節はきっちりと帳尻合わせをしてきた。今季最強といわれるシベリア寒気団の南下により、一週間足らずで例年の降雪量を上回る積雪となった。
二月九日、この日最も寒かったのは北海道内陸部の北寄りに位置する江丹別で、氷点下三十六・〇度。ほどない距離にある幌加内は氷点下三十三・五度と、全国四番目の寒さを記録している。しかもこの辺りは、寒いだけではなく内陸部ゆえ、夏場の気温は三十度を優に超す。つまり、年間の寒暖差が七十度近くになる。
作者の黒木恵美子さんは、この幌加内で生まれ育っている。大正五年(一九一六)、祖父母(父方)の代に、十二家族が開拓移民団として岐阜から入植している。北海道への入植としては、後発隊になる。過酷な土地があてがわれたのは、もうそのような場所しか残っていなかったのかもしれない。
私も生まれは北海道である。私は一九六〇年生まれなので、黒木さんは五歳上のお姉ちゃんになる。私の古里は太平洋に面した温暖な漁村、様似である。いくら寒くても氷点下十五度を下回ることはなく、積雪量も十数センチ程度である。夏の最高気温も、二十八度を上回ることはない。家に電話がきたのは小学五年のときで、その年、町に初めて信号機がついた。山奥からかよっていた山形友子さんの家に電気がきたのも、五年生のときだった。私は学生時代を京都で、その後就職した東京で二十八年を過ごし、二〇一一年から再び北海道に戻り、現在は札幌に落ち着いている。
私の父方は秋田、母方は熊本と徳島から北海道へ入植している。いずれも明治中期で、曾祖父母の代である。入植当時のことを調べたことがあるが、やはり並大抵の苦労ではなかったようだ。
季節が厳しければ厳しいほど、それとは裏腹に自然は美しい姿をみせる。
「妖精が魔法の杖で野山にふれると、片端からパァーンと色がはじけて、木々が芽吹いて葉が萌えたち、花が咲いて花びらが舞い散り、北国の春は駆け足でやってくる」
「古里の春はいつも真上からやってきた。まだ村全体も、それをぐるりと取り囲んでいる山々も雪景色で真っ白なとき、何日か続いて空に柔らかな霞がかかるようになって、冬はもう終わったよ、春がもうそこまできているよ、と風が優しく教えてくれるのだ」
長い冬が明ける喜びが、行間から迸る。光輝く季節の到来は、子供たちをじっとさせてはおかない。
「透明に澄んだ雨竜川の水はとてもきれいで、水面がキラキラ輝き、細かく揺れながらサラサラと音を立てて流れている」
「アイヌ語で雨竜川と呼ばれるこの川の名前をつぶやくと、今でも目頭が熱くなる」
黒木さんが目を細めて、かつて遊んだ幼い日々に思いを馳せる。だが、北国の夏は短い。
「北海道の秋空はひたすら青く広がっている」
「前の晩に冷たい風がビューッと吹いて、冷たさの中に雪のにおいが混じっていると、翌朝には、あたりが真っ白になっている」
黒木さんの自然描写は、行間から溢れ出す古里への思慕へとつながる。
古里での生活は、にぎやかなものだった。黒木さんは五人兄姉の末っ子で、加えて祖母、叔父、叔母を含め十人の大家族であった。そのほか自宅には番犬が一匹、ネズミを捕るネコが三匹、農耕馬が一頭、食肉用のブタが八匹、搾乳用のヤギ一匹、綿羊六匹、玉子を産んでくれるニワトリが三十羽、ウサギが六羽にハトが五羽、さらにミミズクまで飼っていた。その賑やかさはどれほどのものだったか。
生活は自給自足である。自宅に一頭だけ農耕馬のアオがいた。農耕馬がいる家は、村にも数軒しかなかった。アオはおとなしく農作業を一手に引き受け、実によく働いた。家族にとっては、かけがえのない宝物であった。そのアオが突然死んだ。
家族の悲嘆は言葉にならない。だが、しばらくすると大人たちはアオを縛って吊し上げ、解体を始める。アオの肉は切り刻まれ、近所にくまなく配られた。「きれいに食べてあげる」それが供養なのだ。自給自足の生活とは、生きていくということは、そういうことなのである。同じ子供でも、都会のマンションの一室でゲームに興じる小学生とは根本が違う。本書を読んでいると、人間本来のあるべき姿を垣間見ることができる。
五人兄姉の中で高校に進学できたのは、黒木さん一人であった。営林署に就職が決まった長兄は、
「『父さん、俺はこれで公務員になって一生働く。高校にいく夢は叶わなかったが、せめて完二とえみこは高校にやってくれ。俺も頑張って学費を稼いでくるから』父は目を閉じて何も答えなかったが、母はエプロンの裾でそっと目頭を押さえていた」
明治や大正の話ではない。昭和四十年代半ばのことである。
本書には幌加内町共和で繰り広げられる様々な出来事が描かれている。往時を彷彿とさせる描写に深い共感を覚えた。そして、本書のグランドフィナーレを飾るのが「腕時計」だ。圧巻の筆致に胸を打たれる。
随筆春秋の代表理事である池田元と黒木さんは以前からの知り合いである。そのことを今回初めって知った。黒木さんが書いたものを目にしていた池田は、黒木さんの古里への思いを知り、エッセイ集の執筆を促した。
黒木さんはパソコンをおやりにならず、この作品はスマホで書いたものだという。スマホに入力したものを池田に送信し、池田が原稿用紙の書式に直して、黒木さんに確認・修正してもらう。そんな作業が延々と続けられた。二年を要したという。黒木さんの執念には脱帽だが、池田の熱意にも驚嘆の思いを禁じ得ない。池田は常日頃、三、四人分の仕事を一人でこなしている。
「古里を書きたいという思いの結晶が『雨竜川』です。その気があれば、誰でも書けます」
池田はそう言い切る。
極寒の地で、想像も及ばないご苦労をされたおじいさん、おばあさん。そこで二人は九人の子をなし、長男であるお父さんのもとに、お母さんがお嫁にきた。末っ子の黒木さんを含め五人の子がここで暮らした。どんな思いでこの地を切り拓いてきたことか。助け合いがなければ生きてはいけない。
今、この土地にはかつて入植された十二家族に繋がる人たちは、一人もいない。この地の過酷さを物語る現実である。ここで暮らした人たちが確かにいた。祖父母がいて、父母がいて、家族があった。それぞれの人生があったのだ。
この書を書き上げた執念は、そんな人たちの思いが背中を押したということもあっただろう。書くべき人が現れて書いたのである。この書によって、一族の足跡、生きた証が刻まれた。そして、ここに生きた人々すべての魂を昇華させた。本書を読んでそんな思いを強くした。
2020年2月24日 随筆春秋代表 近 藤 健