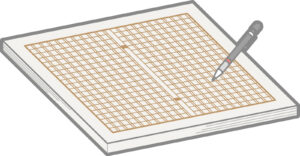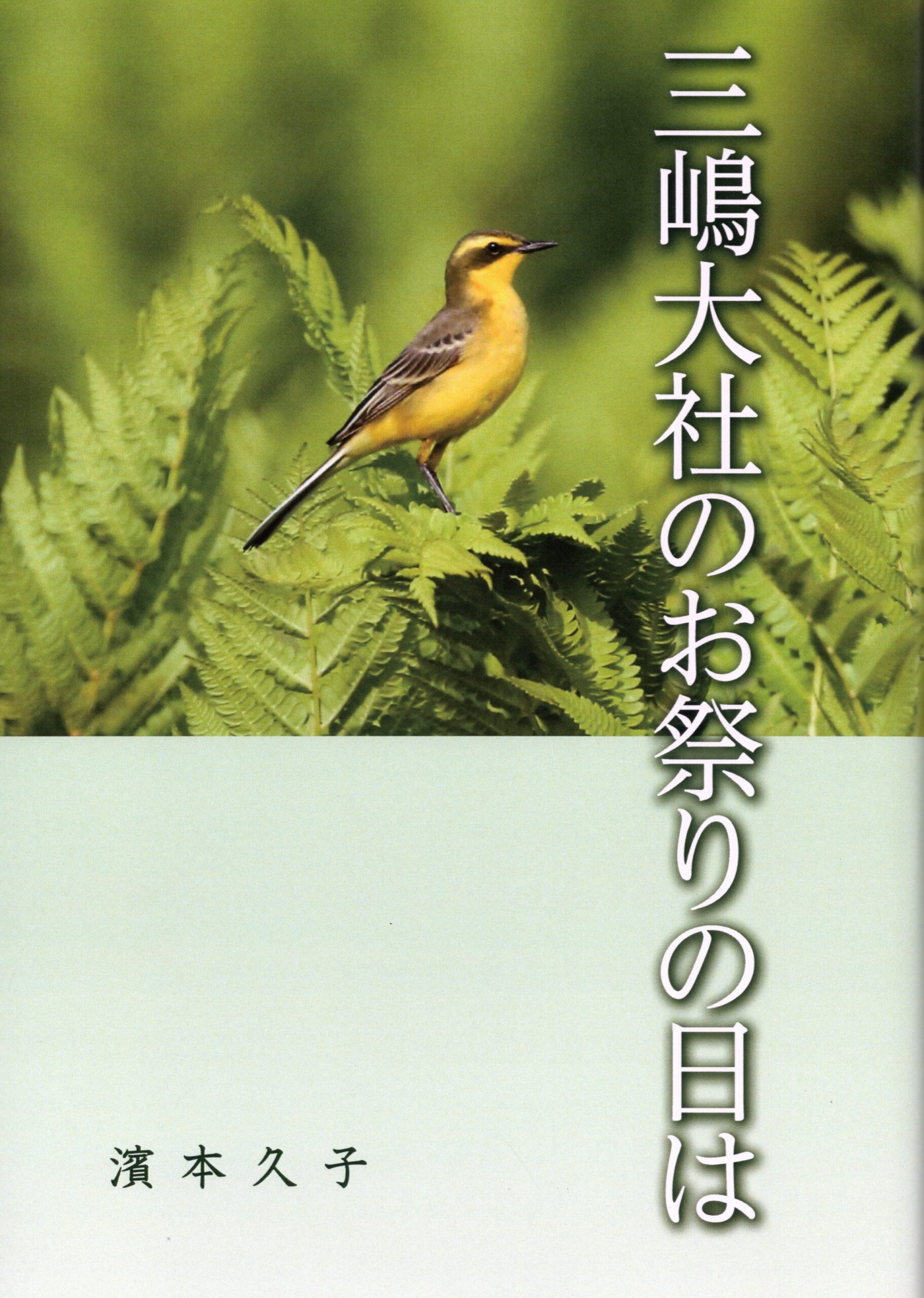近藤 健が校閲とあとがきを担当しました。
「あとがき」全文
草野心平詩集『絶景』の中に、「窓」という詩がある。
窓
波はよせ。
波はかへし。
波は古びた石垣をなめ。
陽の照らないこの入り江に。
波はよせ。
波はかへし。
(後略)
「波はよせ。波はかへし」というフレーズが詩の中で何度も繰り返される。この心地よいリフレインが実際の波の寄せ返しを想起させ、作品のリズムを作り出している。
今回、濱本さんのエッセイ集の校閲と「あとがき」の依頼を受けた。分厚いゲラを読んでいると、草野心平の「窓」が浮かんだ。この作品集の全編にわたって繰り返されるのが、濱本さんが胸の奥に秘めている、寄せては返す悲しみのリフレインである。
濱本さんは、二歳のときに母親と別れている。「拭いきれない母親のいない寂しさ」の体験が、八十代になった今でも、ときおりさざ波のように濱本さんに押し寄せる。
母親との離別は、次のような経緯である。
昭和十年代、中国東北部で大叔父が旅館の経営を始めた。その経営が軌道に乗り出すと、深刻な人手不足が生じ始める。そこで大叔父は、郷里の沼津郊外の漁村の人たちに声をかけた。その呼びかけに応じた若い女性の一人が、のちの濱本さんのお母様である。その旅館でご両親が出会うことになる。やがて身重になった母親が、濱本さんを産むために郷里に戻る。その間に中国に残っていた父親が、腸チフスで亡くなってしまうのだ。
その後、父方の祖母が赤ん坊の濱本さんを引き取るためにやってくるのだが、母親は頑として応じなかった。そんな母親が、周囲の強い勧めで、妻を亡くし二人の子供がいる男性と再婚する。その時、濱本さんは、母方の祖父母の実家に引き取られた。一九四一年の真珠湾攻撃の翌年のことだった。
母親にとっても望んだ再婚ではなく、やむにやまれぬものであったことを長じた後に知る。濱本さんが高校生になったある日のこと、叔母が話してくれたことがあった。
「ネエちゃんは他人の子を負ぶって、家にたまに帰ってくるんだよ。それでもあんたは大喜びだった。でもネエちゃんが帰るときはそりゃ大変だった。泣いて追い縋るあんたを、ネエちゃんは振り払って帰っていくんだもの。でもあんたのことが気がかりで途中からそっと戻ってきては、背戸から家をのぞいて、泣き寝入りをしたあんたを見届けてから、帰っていったんだよ」
叔母は目を潤ませながら語った。
濱本さんは中学生、高校生のころには、母親の婚家に居候していた時期もあった。だが、遠い日に、母に置き去りにされたと思い込んでいる濱本さんの心は、時が解決してくれることはなかった。
母親の思いや当時の状況を後に理解しても、それはまた新たな苦悩の始まりでもあった。「なぜ、あの時(母親に対し)もっと優しい言葉をかけてあげられなかったのか」という、悔恨の思いが胸を塞ぐのであった。
濱本さんにはもう一つ、大きな側面がある。一九七九年から二十一年間、生命保険会社に勤務している。それは三人のお子さんの子育てが一段落した三十九歳から六十歳で定年退職を迎えるまでの期間となる。
自宅を訪ねてきた営業マン(セールスレディー)から、保険の勧誘を受けたのがきっかけだった。ここまではどこにでもある話である。
「中学時代にお人形さんのあだ名だったあなたが、生命保険会社の営業マンを二十年あまりも勤め上げたなんて信じられない」
彼女を知る誰もが一様に口を揃える。早熟な文学少女で、人と付き合うのをなによりも不得意としていた。いつも恥ずかしそうに照れたように俯いている、そんな濱本さんの姿からすると、生命保険の営業マンは対極にある職業だった。
そのことに誰よりも驚いたのは、当の本人だった。濱本さんは入社数年で、トップセールスマンにまで上り詰める。そしてそれを退職まで維持した。彼女は上司に見いだされ、お客様に育てられたという。だが、それに応えた本人の努力は並大抵のものではなかった。
彼女は、退職するまでに一五〇冊を超える営業マインドなど仕事に関する本を読んでいる。知識武装で、お客様のニーズにより応えられる、そんな感触を得た結果のことだった。だが、そんな知識もさることながら、彼女の心の置き所が他の人とは違っていた。
お客様への気遣いや誠意をもった対応は、お客様からの厚い信頼となって戻ってきた。彼女にとって仕事は、単なる営業活動を超えた部分があった。お客様からの助言や何気なく発した言葉は、彼女の知的好奇心を強く刺激した。それが結果的に彼女の営業活動に加勢する。井上靖に傾倒するのも、盛んに中国などへ旅行に出かけるのも、彼女の強い探求心の発露であった。そんな相乗効果が「結果」となって実を結んだ。結果的に「向かない仕事」を「自分に向かせる」ことになっていたのである。濱本さんは、常に自分の中の弱さと闘っていた。それが彼女を強くした。彼女の歩んできた姿は、そのまま人材育成や社員教育などのお手本である。
本書は、母親に置き去りにされたと思い込んでしまった悲しい心とトップセールスマンとして奮闘してきた日々の思いが糾われている。それらが混然一体となって読み応えのある作品になっている。
二十一年在籍した生命保険会社を退職し、今年はちょうど二十一年になる。退職後の二十一年は本格的に文芸活動を始められた年月と重なる。随筆春秋のスタッフとしても組織を支えてきてくださったことに心から感謝申し上げたい。その間にも濱本さんは母親を亡くされ、ご主人を看取られている。
濱本さんは自分の中の弱さと闘い、結果としてマイナスをプラスに転じてこられた。これからも息の長い文学活動を続けられることを願ってやまない。八十代でなければ書けない境地を、ぜひとも私たちに示していただきたいものである。
2021年7月21日 随筆春秋代表 近 藤 健