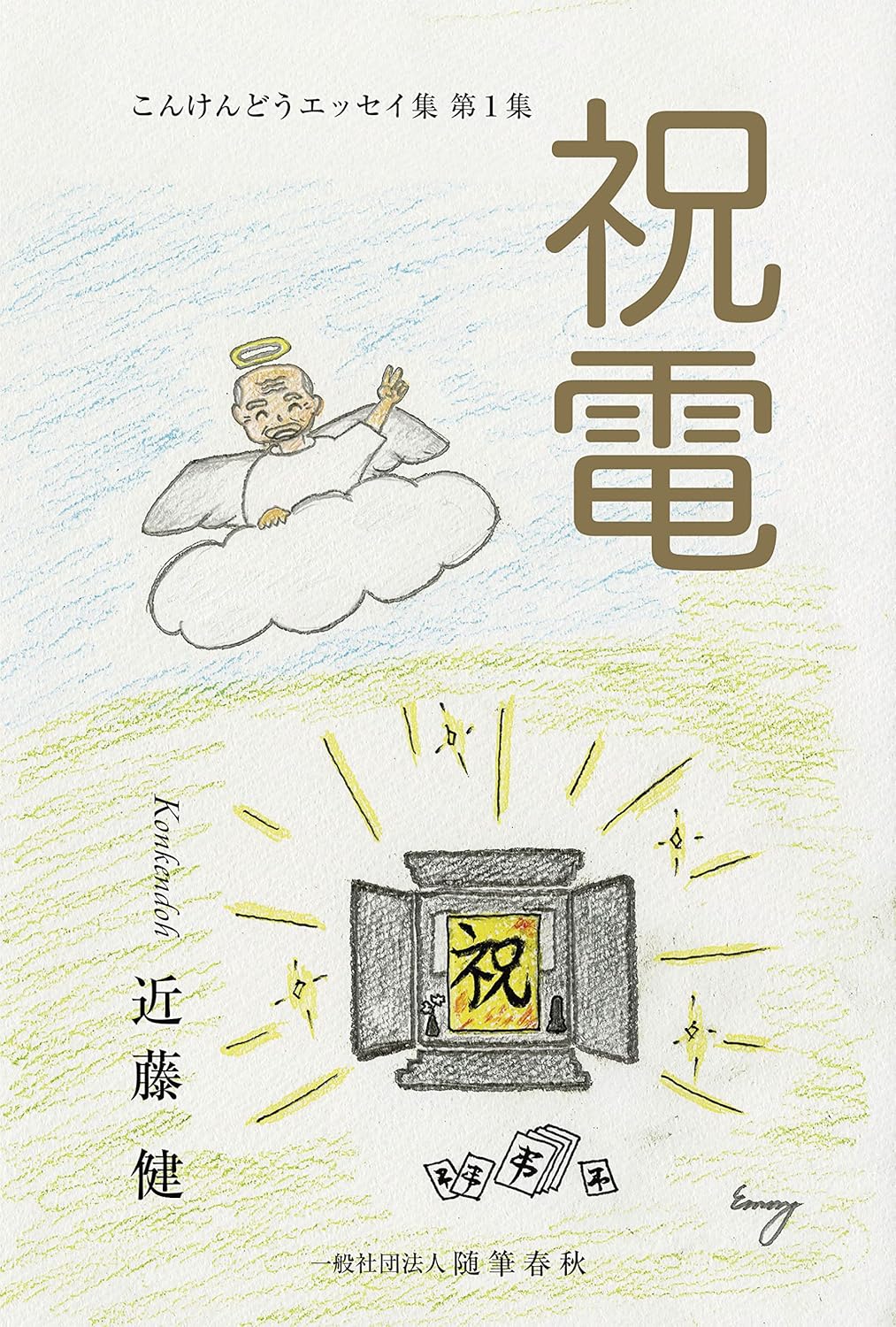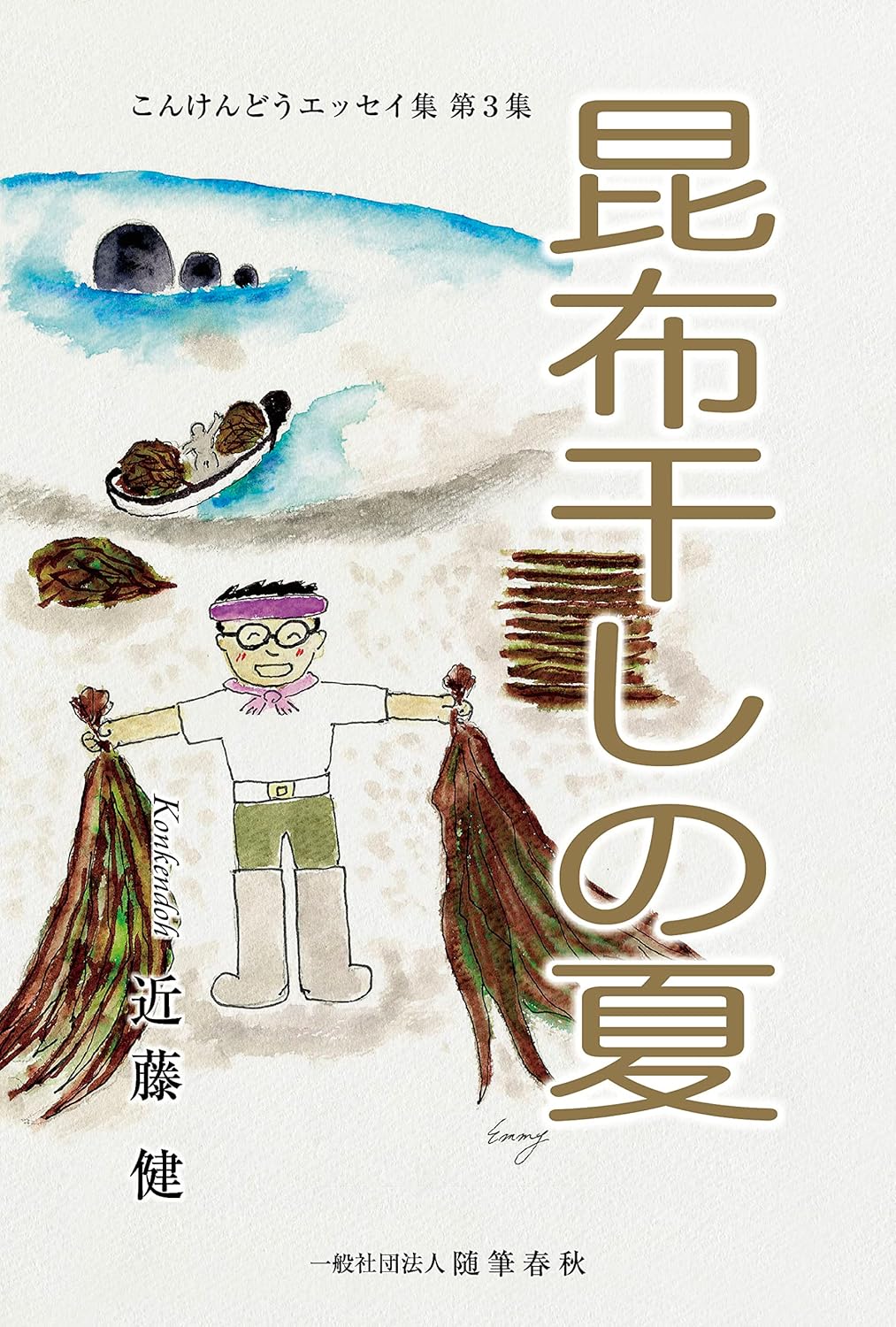三億円のおひたし
契約書の読み上げが終わりに近づいていた。会議室の窓からは、林立する新宿の高層ビル群が見渡せる。その上に初夏を思わせる明るい空が広がっていた。
二十五年(一九八八年)前、会社が遊休地を売却した。その売買契約が、相手方の会社で行われた。土地の売買は、私にとって初めての経験だったが、売る側の立場だったので気軽に構えていた。
「それでは決済を行います」
司法書士の言葉で、土地の権利証と小切手が交換された。権利証に疑義がないか、また小切手に不備はないか、張り詰めた空気が会議室に流れた。これがマフィアの闇取引なら、買った側が懐からピストルを取り出し、現金もろとも車で逃走する場面だ。くだらぬ空想を巡らせているうちに、あっけなく売買は成約した。
やれやれというところだが、問題はその後であった。我々は、一刻も早くその小切手を安全な場所に確保しなければならない。つまり、自社の銀行口座に入金しなければならなかった。小切手の額面は三億円だった。
会議室を早々に辞し、ビルの出口まできたところで、上司が鞄から小切手を取り出した。オレが持っているより、お前の方がいいという。確かに、二人並ぶと明らかに私の方が貧相である。暴漢の裏をかくという算段だ。そこで封筒に入った小切手を背広の内ポケットにしまい、さらにしっかりとボタンをかけた。黒革の鞄は上司が持った。入念なカモフラージュというわけだ。
外へ出ると、新緑がまぶしく揺れる日差しの強い午後だった。背広を着ているので額に汗が滲む。私は持ったことのない金額にひどく緊張しながらも、内心「オレの値打ちは今、三億円だ」とワクワクしていた。
歩き出してすぐに、銀行が目に入った。さっそくそこから小切手を送金することにした。往来の多い通りを、過剰に警戒して歩く。私は頻繁に背広の胸に手を置いて、封筒の存在を確認した。
振込用紙に小切手を添え、窓口に出したとたん、
「あのー、お客様。小切手では直接振込みができませんが……」
窓口の女性がほがらかに微笑んだ。私と上司は顔を見合わせた。小切手は手形と違い現金と同じもの、という認識しかなかったのだ。
仕方なくその銀行を出て、辺りを見回すと、支店は違うが我社と同じ取引銀行があった。ほっと胸をなでおろす。念のため行員に尋ねると、当座預金の入金帳を用い、預金口座のある支店で入金しなければならないという。そんなバカなと思ったが、押し問答している余裕はない。時計はすでに二時を回っていた。
近くの公衆電話から会社に連絡し、入金帳を持って、銀行の前で待機するよう同僚に伝える。会社の銀行は日本橋にあった。電車に乗るのは危険だと、タクシーに乗り込んだ。二十分もあれば着くと踏んだのだ。
だが、ほっとしたのもつかの間、タクシーはすぐに渋滞に巻き込まれた。時計を睨みながら、次第に焦りが募る。このままだと三時までには銀行にたどり着けない。運転手に急ぐ旨を伝え、他に道はないのかと尋ねると、
「お客さん、今日は五十日〔※〕だから、どこ走っても同じですよ」
と、にべもない。
やむなく地下鉄の入口が見えたところでタクシーを降りた。地下へ続く階段を駆け下り、折りよく滑り込んできた電車に飛び乗った。変な妄想を起こさず、最初から電車に乗っていれば、何ら問題はなかったのだ。
汗が額を流れ落ち、ワイシャツも汗ばんでいる。電車に乗ってすぐに、上司は背広を脱いだ。私は小切手を持っている手前、じっと暑さに耐えるしかない。流れ落ちる汗とは裏腹に、焦りがジリジリと首筋から上がってくる。三時まであと十分しかなかった。
電車が目的の駅に着いたのは、三時ちょうどである。とにかく銀行に電話を入れなければ、と改札を出て公衆電話に飛びついた。
「今、××駅にいるのですが、これから小切手を入金しにいきたいのですが……」
今からですか、と銀行員の冷淡な声が返ってきた。
「三億円の小切手なんです」
というと相手の態度が一変した。
「たいへん失礼しました。お待ちしております」
弾む心をムリに抑えたような声が返ってきた。通用口のインターホンを押してくれれば開けるという。金額の多寡によって、銀行も融通が利くのだ。
地下鉄の階段を駆け上がり、走りに走った。途中まで一緒だった上司は、
「おまえ、先にいけ!」
とあえなく脱落。もはやカモフラージュどころではなくなっていた。
やっとの思いで銀行にたどり着くと、シャッターの閉まった入り口の前で、途方に暮れた犬のような顔で同僚が待っていた。入金帳を受け取った私は、すっかり安心した。走りながらも幾度となく胸の封筒は確認していた。その点はぬかりなかった。
「いやー、ご苦労様です。どうぞ、どうぞ」
汗を拭き拭き肩で息をする私を、中年の銀行員がにこやかに迎えてくれた。
「金額が金額だけに、どうしても今日中に入金したくて……」
と口にはしたが、内心、どうだ、約束どおり持ってきてやったぞ、という上ずった気持ちになっていた。中年の銀行員も、揉み手をするほどの低姿勢で、
「いや、いや、ごもっとも、ごもっとも。さあ、さあどうぞ」
と言いながら、女子行員に冷たい麦茶を命じた。
挨拶が一段落したところで、小切手を取り出そうと背広の懐に手を入れ、ギョッとした。私の背広の中が、熱帯雨林のような高温多湿になっていた。恐る恐る封筒を取り出すと、汗を吸った封筒が変色している。濡れた封筒に小切手がピタリと貼りつき、封筒と小切手が三位一体を呈していた。しかたなくそろりと封筒を破ると、ホウレン草のおひたしのようになった小切手が出てきた。湯気を発していないのが不思議なほどだった。大変なことを仕出かしてしまったと青ざめた。冷や汗が流れ出た。
「ワアー……こういう状況の小切手は初めてですな」
行員が身を乗り出した。行員と私の立場は完全に逆転していた。こんな小切手ではダメだ、と言われたら一巻の終わりである。祈るような気持ちで行員の表情を窺った。まあ何とかなるでしょうと言いながら、麦茶を持ってきた女子行員に、受け皿に乗せた小切手を手渡した。女子行員の顔が、一瞬曇った。実際大変だったのは、アイロンがけをさせられた女子行員だったかもしれない。
かくして三億円のおひたしは、無事預金口座に入金された。遅れてやってきた上司も、小切手並みにクタクタになっていた。その日はもうそれ以上仕事にならなかった。
2004年12月 初出 近藤 健
😯 電子音声朗読 (← CLICK!)
※ 五十日とは、毎月五と十のつく日(五の倍数日)。企業などの決済日に当たり、金融機関の窓口はもとより、道路交通も渋滞するといわれている。

【広告】