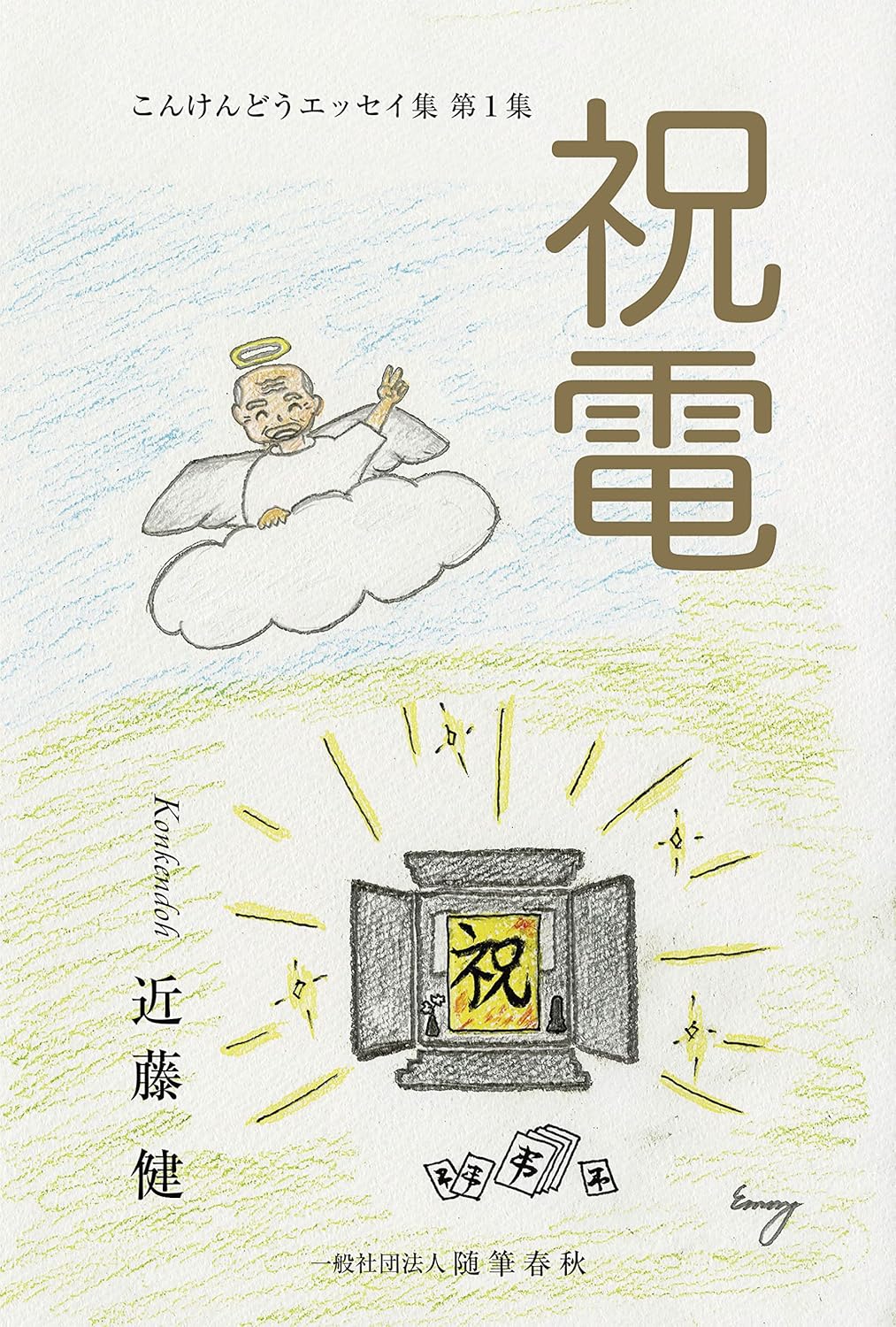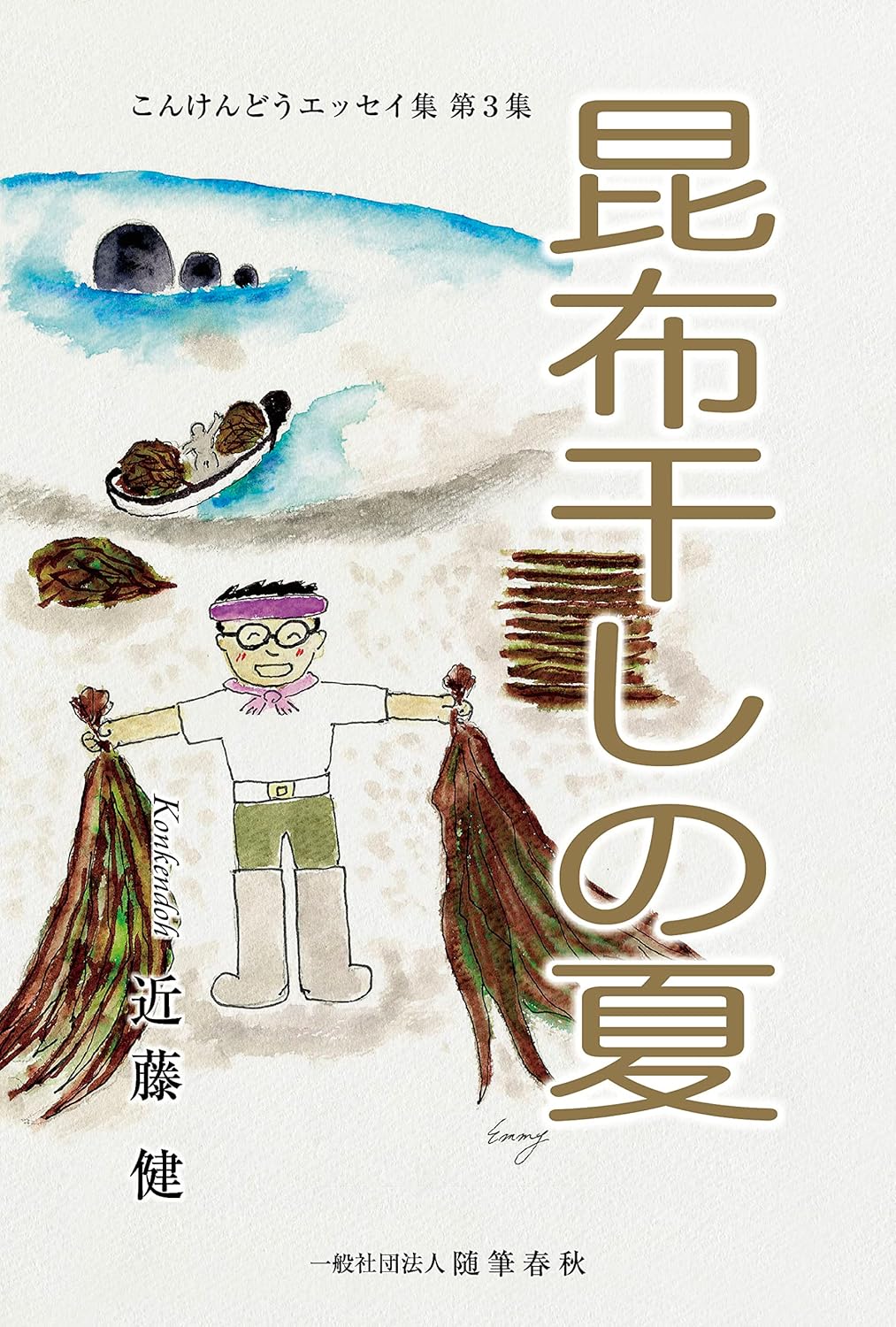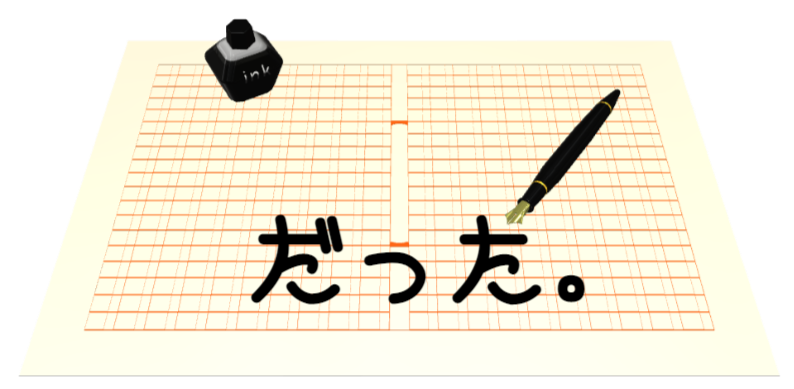
「だった」の呪縛
先日、ある方からメールをもらった。その中に、
「『だった考』については賛否両論のあるところですが……、どう思われますか」
とあった。何だ? 「だった考」とは、と思いつつ読み進めると、私の文章の「……だった」という言い回しが気になったとある。メールの主は私の高校の先輩で、現在、大学の非常勤講師のかたわら文筆活動をしているという。ネットで私の文章を読み、近づいてきた方である。
「だった」のどこがいけない。私は「だった」を「……だ」「……た」「……である」「……であった」のひとつの選択肢と考え、文章の中にちりばめていた。ただ、同じ言葉の連続だけは避けねばならない、とは思っていた。そこでもっともらしく、
「特にユーモアエッセイの場合、その場の雰囲気で『だった』でなければそぐわないものがあります。『であった』ではかしこまりすぎ。特に、読者の意表を衝くような〝落ち〟の場面では、『実は、私、○○だった』などと用いております」
言い訳めいた返信をした。だが、後になって次第にその「だった」が気になり始めた。
「ダッタ、ダッタと安物の機関銃を撃つような文章は、いただけませんね」
というどこかで聞いた話を思い出していたのである。
そこでインターネットで「だった考」を検索したところ、作家阿川弘之の対談が出てきた。
阿川 文章には一応神経質に気をつけているつもりです。近頃、日本語がずいぶんいい加減に扱われていると思うものだから。
鈴木 これもつい最近出された『人やさき 犬やさき』でも、「べしは正しく使うべし」とか「だった考」とか、日本語の問題を書いていらっしゃいますね。尚之さんや佐和子さんの文章まで引き合いに出して具体的に書かれていて、勉強になりました。
阿川 いや、僕も偉そうなことは言えないんで、若い頃のものを必要あって読み返してみると、結構「だった」を使ってるんですよ。だけど「だった」「だった」「だった」というのは安物の機関銃を撃っているようだからやめろと、娘なんかには言うんですけど。
ダッタ、ダッタ……、安物の機関銃……、私は、アッ! と言葉を呑み込んだ。さっそく『人やさき 犬やさき』(文春文庫)を購入してみると、確かに『だった考』なるエッセイがあった。
大正初年、東京高等師範学校で教鞭をとっていた岡倉天心の弟由三郎は、学生の使う日本語にとてもうるさかったという。阿川氏は、当時高等師範学生であった福原麟太郎氏の随筆を引用している。
「学期学年の試験の前になると、先生はわれわれに注文をつけた。『国語は正しくかいてほしい。堅書きにする。何々だったという言い方はやめてほしい。ちゃんと、であったと書く……』」、と。
岡倉由三郎氏には、とりわけ「だった」を使うなという強い戒めがあり、それと同様な考えを井伏鱒二ももっていたという。阿川氏は、
「鷗外はだつたを一度も使っていないね」
という井伏の言葉を引き合いにし、
「その、鷗外が嫌ひ岡倉由三郎が嫌ひ、福原さんも井伏さんも嫌つた『だった』を、今の文筆家たちは平気で、而も頻々と使ふやうになつた」
と嘆いている。日本語の著しい誤用や乱れを憂慮し、
「それでも『だつた』の頻出くらゐ未だましな方、眼をつむつて置かなくてはならぬ時世なのかも知れぬ」
と諦念を述べている。
やはり「だった」はダメなのか……、私は少なからぬショックを受けた。そこで、私が以前に書いた文章の中に「だった」を探してみると、ザクザクと出てきた。会話文ならまだしも、地の文にあるのだ。連発は避けていたが、かなりの頻度である。
そこで、私の「だった」探しが始まった。
手元に素人のエッセイや創作の短文を寄せ集めた本がある。その167人中、100人に「だった」が見られた。さらに、『2004年版ベスト・エッセイ集』(文春文庫)では59人中、28人。その中には誰もが知る高名な作家も含まれていた。
さらに、第137回芥川賞を受賞した諏訪哲史氏の『アサッテの人』に至っては、日記の引用部分が含まれていたこともあるが、73か所も「だった」があった。これだけ「だった」があっても芥川賞だ。私の中で「だった」の許容が優勢を占めてきた。
だが、多数意見が真実とは限らない。さすがに「だったのだった」という表現は論外だが、「……だったのである」「……だったからである」「看護師だった○○さんの話も衝撃的だった」などを「であった」、またはほかの表現に置き換えることができるか、と思い悩み始めていた。「だった」が、文章全体の気品や品格といったものを壊しているのではないか、という思いが頭をもたげ始めたのである。
いささか神経質になった私は、「だった」のよしあしの判断がつかなくなったばかりか、「だった」に対する過剰反応をし始めていた。「我輩は猫だった」、「木曽路はすべて山の中だった」はやはりダメだ。「である」で終わる文章に対しても、「だった」を当てはめ考え込んでいた。前川清とクールファイブの『長崎は今日も雨だった』は、『雨であった』とすべきなのか、もはや混乱の極みである。
「だった」は、文末だけに登場するいわゆる「だった止め」だけではない。「いったいそれは、何だったのだろう」「私がまだ○○だったころ」「○○の好きだった彼は……」など数え上げれば切りがない。
そんななか、例の御仁から再びメールが舞い込んだ。
「……『だった』を意図的に使わないと、読み手に不快感を与える可能性がある、ということです。『だった』を極力使わなくてもいいように文章を仕上げるということで、宜しいのではないでしょうか」
ごもっともである。
実は、「だった」に苦言を呈していた阿川氏も、
「いまでも此処を『であつた』としては固苦し過ぎるかナと思ふ時、前後勘案しながらだつた止めにすることがある」
と吐露している。現に『人やさき 犬やさき』に収録されていた『べしは正しく使うべし』の中で、
「実はさつき、家を出る直前、『気に入らぬ』日本語の用法を二つみつけて、而もそれらがうちの娘と息子の文章で、困るなアと顔をしかめた矢先だつたから、あまりの偶然に……」
と「だった」を使用する部分があった。私は「だった」の束縛から解き放たれた思いがした。
「だった」は場合によっては避けられない言葉である。だが、意識して使わなければならない危険な言葉「だった」のである。
「ああああーあー長崎―はー今日もー雨だったー」
でいいのであって、
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」
でなければならないのである。
一時期「だった」の使用制限を自らに課していた私も、最近、疑心暗鬼ながら、恐る恐る「だった」の使用を再開している。
平成19年(2007)11月 初出 近藤 健

【広告】