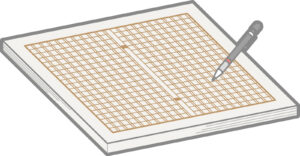近藤 健が校閲とあとがきを担当しました。
「あとがき」全文
編集部から岩崎さんの初校ゲラができた、という連絡を受けたのは、昨年十一月下旬のことでした。現在、札幌で暮らす私と東京の編集部とのやり取りは、もっぱらLINE(ライン)です。LINEとは、スマホやパソコンなどで利用できるコミュニケーションアプリです。ゲラは郵送されてくるのではなく、クラウド上に置かれます。それが「ゲラができました」という意味です。
連絡を受けた私は、インターネットを介してサーバー上に保管されたデータをコピー&ペーストで自分のパソコンに取り込むのです。今回のゲラをプリントしてみると、ずっしりとした原稿の束になりました。初校はイラストなしの文字原稿で、三〇〇ページ。人生の重みを感じさせるものでした。
原稿を読み進めていくと、これまでに私が観てきた日本映画のいくつもの場面が、断片的によぎっていきます。セピア色に染まった、懐かしい昭和のシーンです。
岩崎さんは昭和二年(一九二七)のお生まれです。昭和元年は一週間という短い期間でしたので、まるまる〝昭和〟を生きてこられたことになります。昭和は六十四年まで続く、とても起伏に富んだ時代でした。前半の三分の一は、戦乱を伴う激動の時代でした。岩崎さんは、幼少期から成人までの人生の輝かしい期間を、そんな時代の中で過ごされたのです。
私の目の前には、令和五年の日めくりカレンダーがぶら下がっています。そのカレンダーには、小さな字で「昭和九十八年・平成三十五年」と記されています。ご丁寧に昭和と平成での換算年数が記されているのです。つまり岩崎さんは、今年の秋には、九十六歳になられるわけで、まさに〝昭和の語り部〟にふさわしい方なのだなと、改めて感じた次第です。日めくりカレンダーは二センチを超える厚さがあります。岩崎さんの生きて来られた年月分のカレンダーを積み上げると、三五〇〇〇枚、高さは二メートルに達します。岩崎さんが過ごされてきた日々の積み重ねです。
人生九十年といわれて久しいのですが、その年齢も限りなく百年に近づいています。単純に百年といっても、百年後の世界を想像できるでしょうか。百年前、誰が冷蔵庫、洗濯機、テレビ……そんなツールの出現を想像できたでしょう。各家庭に電気が普及しているなど、夢の話です。蒸気機関車の登場に驚いていた世代にとって、新幹線の出現は驚天動地であり、何年か後にはリニアモーターカーが走り出します。誰が電話を持ち歩く時代を想像したでしょう。百年とは、そんな歳月です。
百年後には、自動車は空を飛びまわり、現在の歩道・車道という概念はもちろん、交通事故という言葉自体がなくなっていることでしょう。AIの目覚ましい発達は、私たちの想像を超越した世界を出現させているに違いありません。百年を生きるとは、そういう変化を目の当たりにすることなのです。
私が回りくどく長々と申し上げてきたのには、理由があります。岩崎さんがその百年を生きて来られたからです。身をもって体験してこられたことを著書として残される意義が、いかに大きいかをこの作品集を通して改めて感じました。
私たちの共通の先生である佐藤愛子先生は、今年、百歳になられます。二〇二一年の春、佐藤先生は断筆宣言をされました。九十七歳のことでした。しかしながら、翌年の秋、九十九歳を目前にし、再びペンを取られています。つまり、この年齢に到達した、そんな高見からでなければ見えない景色があるのです。高齢の方は数多くいらっしゃいます。ですが、実際にペンをとってそれを表現できる方は、ごくごく少数で、選ばれた方のみがなし得ることなのです。岩崎さんは、そんなご指名を受けた方です。
この作品集を通して感じることは、目に見えるモノ、物質の変化はもちろんのこと、そこで暮らす人々の心の持ちようが、しっかりと描かれていることです。「ああ、そんなふうだったか」「そうだよな、そうだった、そうだった」といったものです。それは〝懐かしい〟という感情とともに甦ってくるものです。私は昭和三十五年(一九六〇)生まれですので、岩崎さんとは親子ほどの年齢差がございます。ですが、この作品集を読みながら、すっかり忘却の彼方に葬り去られていた昭和という〝時代の気分〟が、何度も立ち昇ってくるのを覚えました。
印象深いのは、岩崎さんが見つめる昭和の母子の姿です。とりわけ母親の振る舞いや考え方が、今ではお目にかかれないものなのです。それは、「奥ゆかしい女性」であり、ひかえ目でありながらも「逞(たくま)しい母親」の姿です。昭和の一場面が見事に切り取られています。それは、岩崎さんが、当時としては極めて稀だった〝女医〟だったことによります。小児科医としての目線の温かさが、得も言えぬ心地よさとして作品から滲(にじ)み出ているのです。
二十代のころをつづった作品の中で、
「私は、小児科の病室で医師の勉強よりも、母親の覚悟を教えられた気がする」
と述べられています。不治の病に翻弄(ほんろう)される人の運命や不幸というものを、誰よりも身近で視てこられた。「それは医学ではどうにもならないことばかりであった」と吐露されています。
時代の流れの中で世の中は大きく変わりました。そんな中で、
「昭和、平成、令和と生きてきて、一番変わったのが世の中の母親だと思う」
母子の在り方を見てこられた医師ならではの視点を感じさせる言葉です。
誰よりも「奥ゆかしさ」と「常にひかえ目」な部分を持ち合わせていらっしゃるのが、いさんご本人にほかなりません。
そんな岩崎さんの作品は、力みのない、肩の力がスッと抜けた作品が数多くあります。ゆえに、読んでいて微睡(まどろ)むような心地よさがあるのです。あっさりとしていながらも深みがある、本書は、そんな枯淡の境地ともいえる作品集です。星霜に耐え、努力をされた方だけが許される静かな到達点ではないか、そんな思いを強くしました。
岩崎さんは、現在も月に二、三度、市町村の乳幼児健診に出かけられているといいます。
「泣く子、笑う子、怖がる子。赤ちゃんに接しているときが一番の幸せ」と仰る。
ますますのご健筆を願ってやみません。
2023年1月 随筆春秋代表 近 藤 健