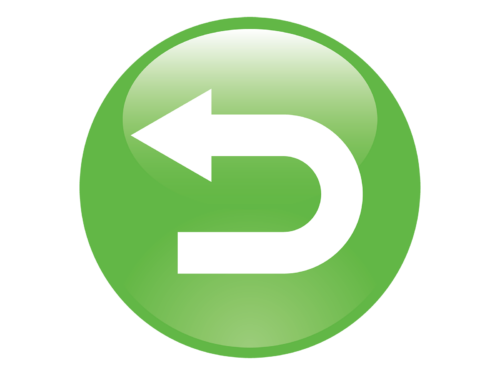道しるべ
七十五歳になる私にエッセイや小説を発表できる「随筆春秋」という舞台が与えられたのは幸運の極みだとつくづく思う昨今である。
しかし振り返ってみるに私は書くことは苦手だった。日記も付けない、若いころ必要に迫られて書く親への手紙も箇条書きだった。しかし読書家ではあった。読むと書くは私の中では別物だった。
そんな私が四十六歳のときだったか、友人J子に誘われて京都新聞社が主催する「文章講座」を受講することになった。しかし、土壇場になって誘った方のJ子が家庭の事情で行けなくなったという。独りか、という不安が募る中、私は車で片道二時間の道のりを半年間通うことになった。
三月から始まった講座は八月までだ。月に二回、計十二回。一回の講座に要する時間は百八十分だ。うち九十分は文章一般に関する講義で後の九十分は、受講生たちにその都度与えられる課題の、創作文に対する講師の講評である。受講生は男女合わせて総勢七十数人。平均年齢は六十歳くらいだったと記憶している。
文章一般に関する講義はただ聞いていればよかった。問題は課題に出された各人の創作文に加えられる講師の講評であった。講師は七十過ぎの小柄な方で、羽織袴で壇上に現れた。彼は辛口だった。歯に衣着せぬ批評は受講生の心臓を縮み上がらせた。
まともな文章など書いたことのない私がくる場所ではなかった。そんな私に対する初回の講評は意外なものだった。私が提出した原稿を手にこちらの顔を見ながら
「おや、女性だったのですね、てっきり男性かと思いましたよ。センテンスも短くて文章の切れがいい」
しかし、褒められたのはこれ一度だけ。次回からの講評は辛辣を極めていった。素直じゃない私は内心(こっちは四十六歳にもなっているんだからそんなに熱心にならなくてもいいのに)と、妙に白けた気分になっていった。
講評が辛辣なのは私にだけ向けられたものではなかった。彼にしてみれば七十人からいる受講生を毎回、メリハリをつけて料理していかなければならないのだから、テクニックも必要だったのだろう。みんなは自分の番が回ってこないかと、ハラハラドキドキの九十分だった。
九十分のうちで講評を受けることができるのはそう多くはない。中でも決まってやり玉、血祭りにあげられるのは七、八人だった。私はその中に入っていた。優秀だからではなく、文章に何か特徴があったのだろう。
まるで火の玉でも飲み込んだように真っ赤な顔で気勢を上げる講師。あるとき、彼は私が提出した創作文の原稿を壇に叩きつけて
「あなたね、本を読みなさい。女性作家の本をね。あなたの作品を読んでいると私はね胸が痛い。文章には骨組みがあって、その骨に沿って肉があり、血が通っているのですよ。あなたの文章には骨しかない」
と言われて私は途方にくれた。そう言われ私は内心、(読書なら子供の頃から貸本屋ができるくらいしましたがな。そやけど、書けへんからここにきてるんやおへんかいな。でも、確かに女性作家は少のうおしたわ)と反論する。
例題でも掲げ、文章の過不足を指摘する場面でもあれば直観的な効果が期待されたと思えるのだがそれはない。受講生の原稿に目を通しているのは講師だけである。自分の創作文が取り上げられない人たちには退屈な時間だったと想像する。
不思議なことだが、胸に針差す強烈な言葉も、受けているのは自分だけではないと思いからか私は耐えられた。
そんな血も涙もない私の創作文に対する熾烈な講評は回を重ねていった。そうこうするうちに講座もあと余すところ三回になった。周りの人に聞いてみると、この講座に何年も通っている人たちが意外に多いのに驚かされた。
講座も後半に差し掛かったころから講師の炸裂する様子が、打ち上げ花火から線香花火に変わった。私も考えるところにきていた。心の何処かに、自主卒業を唱える声と、もう少し叩かれてみようかという奇妙な考えが同時に湧いてきていた。
このとき、ふとある考えが頭をもたげた。志賀直哉の長編、『暗夜行路』の一部を抜粋して私の創作文として提出したらどうなるだろうかと。何故、暗夜行路かと問われると、分からない。盗作になるのかな? でも、ばれたら打ち上げ花火どころではないかもしれない。
そんなことを危惧しながらも、原稿用紙五枚だっただろうか転写して提出した。講師からの校正原稿が戻ってくるのは講座最終の日になる。
そしてその日がやってきた。講師は私に例の原稿を手渡しながら
「あなた、あと一講座お受けなさい」
と言うではないか。こんな不出来な生徒をあと半年間引き受けようというのか。私は更新手続きは据え置き、とりあえずその場は殊勝な顔をして、はい、お願いしますと言って頭を下げた。腹の中に狸が騒いでいた。
そして帰りの車の中で、朱色に染まった「小説の神様」、志賀直哉の作品に私はごめんなさいと手を合わせた。卒業がこの瞬間に決まった。
その後、私は何も書かず読まず暫く時を過ごした。しかしあるとき思い立って、新聞のコラムや社説、気に入った作家の短編などを原稿用紙に転写した。一年間は続いただろう。主婦であり、夫の家業を助ける私には余分な時間などしれたものである。ペンを置くことは難しいことではなかった。しかしそれはできなかった。
数年後、スーパーで再びあのJ子に会った。今度は、長崎に事務局を置く同人誌「コスモスの文学の会」に入会しようと誘われた。
J子と私は同い年である。彼女は地元で「児童文学の会」を立ち上げて十年になるらしい。「コスモス文学の会」に入会するには同会が主催するコンテストで佳作以上の受賞力が求められた。
私はダメもとで六十ページほどの短編小説で応募した。分からないものである、佳作を受賞できたのは私だけだった。
入会後まもなく、事務局の代表からメッセージをいただいた。正確には覚えていないが、こんな内容だったと思う。
……あなたは独特な文体をお持ちのようですので、その部分には触らないようにします。ですが、文章は未熟です。推敲を重ねて、作品は発表してください。発表することは必ず後々のあなたの力になります……
そして私の作品への丁寧な校正が繰り返された。私は推敲の過程で気づかされること改めて学ばされることが多かった。
こうして私は五年間、「コスモス文学の会」に在籍して育ててもらった。しかし、二十年の歴史を持つ同、同人誌も諸般の事情により閉鎖に追い込まれていった。
その後、私はブログを立ち上げたり、公募ガイドから下手な鉄砲を撃ち続けた。そして、そんな浪人的な書き方にピリオドを打って四年前から同人誌、「随筆春秋」に入会させてもらった。
代表の池田元先生をお訪ねしたときの氏の礼儀正しさには感服した。そして、書き手に対する感化指導にも素晴らしさを感じずにはいられない。褒めて伸ばす、書き手をその気にさせてくれる。
振り返ってみればその都度、様々なステージで色々な方々の教えを頂き今この場に私はいる。最初の熱血漢の講師もあまりにも過激であったために私は学んだことを脳裏に閉じ込めてしまったが、書くことの下敷きをくれたのは彼だったと思う。
私は書きながら、書くことは自分自身の心の解放につながっていることに気づいた。
了