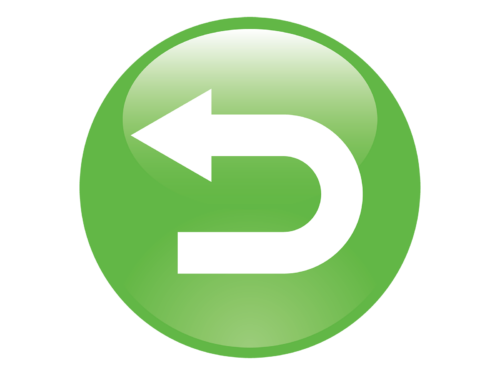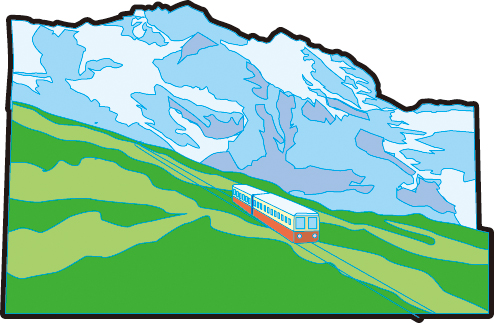
七十歳・私のバイブル
私は今年、古稀を迎えた。生きていれば様々なことがある、あった。七十歳少し前くらいから何故か自分の死について考えるようになった。それまでにはなかったことだ。暗いイメージはない。頭が自然にそれを受け入れている。
今のところ、幸い持病もなく足腰もまだ丈夫だと自負し登山を楽しんだり、他府県に嫁いだ娘の家に遊びに行ったりしている。そんな私が死を感受する心の動きは、多分無意識のものなのだろう。木の実は自分が大地に還るときを知っている。私もやがて来るそのときを悟り始めているかのようだ。そして私の本能は人生の後始末という仕事にとりかかったのかも知れない。
そろそろ、旅立ちの心構えをもちなさいよと、誰かが私のこれからの行く道を示しているのだ。誰が? それは私の中のもう一人の私。なぜか、七十歳という言葉の響きが好きだ。
人生の美学を感じるのも語れるのもこの晩年になってからではないだろうか。どんな生き方をしてきたのか、真価が問われるのは晩年になってからだとこの頃つくづく思う。
もちろん、美学は晩年にだけあるわけではないし、人によって晩年の時は違うだろう。長寿の人もいれば、短命に終わる人もいる。また同じ年ごろを生きたとしても気持ちの持ち方で、その姿かたちや生命力の強弱は違って見える。
綺麗な響きを持つ晩年の美学という言葉。抽象的な表現かもしれない。私的には、来し方の体験や知恵を生かしながら人生の終焉への道を究めたい。孤独の自由を愛し楽しみ私とは何者かを突き詰めたい。
人は舞台役者のように幾通りもの生き方はできないのが普通だ。人生は一度きりだ。でも若い頃、私はこんな風に考えられただろうか? その時々を生きるのに精いっぱいだったと振り返る。結婚、出産、子育て、そんな生活の営みの中に自己の時間が埋没してゆき、足元をじっくり見据える余裕などなかった。様々なことがあったが、若かった時間はまたたく間に過ぎていった。
自分に寿命があるという明確な認識すら疎かった。命は永遠に続くような錯覚すら覚えたものである。今、考えてみると笑えるような話だが、近くで銃撃戦があったとしても、自分だけは被弾して落命することはないような気さえしたのである。
人生は洋々としていながら不透明でなんの保証もないのに、希望に満ちた夢のような道のりだと考えてはいなかっただろうか。でもそれでいいのかも知れない。先が見えすぎても生き辛いものがある。素晴らしい将来が約束されているものばかりではない、反対に辛いことばかりが山積していたのでは、生きる望みがなくなってしまう。
そんな私が五十二歳で初孫を抱いた時、初めて命の交代という実感を味わった。暖かく柔らかい新しい命は、無言のうちに私に命の限りを教えてくれた。いずれ私も土に還る時を迎えるのだという意識を初めて素直に受け入れたのを思い出す。
私が五十九歳の時、夫がそれまで営んでいた商売を他人の過失で突然、止めざるをえなくなった。そろそろ晩年へと緩やかに舵を切ろうとしていた矢先だっただけに戸惑いは大きかった。
事業を続けるために八方手を尽くしたが、駄目だった。私たち夫婦は財産を整理した。手放すものは手放し借金を返済した。子供たちに負の遺産を残さないために。幸いだったのは四人の子供たちが独立していたことだった。
人は様々な変化を受け入れながら生きて行かなければならない。どんなに努力してもあがいてもどうにもならないこともあるということを知った。
生きるということはそういうことなのだろう。それが人生の始末をつけてゆく過程でもあるのかもしれない。だが十一年前の生活の突然の変転を当時はたやすく受け入れることはできなかった。
人は予期せぬ憂き目に遇うようになっているらしい。力量を試されたのかもしれない。その後、歳月が私を育ててくれたのだと思う。七十歳になった今、ゆっくりそしてじっくり足元の現実を見つめながら残された時間を生きようと思っている。去年、足腰の丈夫な今のうちに一度は行ってみたかったスイスに行こうと夫婦の間で話が決まった。
六月半ば、スイスの山野は百花繚乱の様相を呈していた。色とりどりの花々に囲まれた町や村。そして車窓から見える民家は、カラフルなミニチュアのおとぎの国が再現されたようだった。青空の下、緑の絨毯を敷き詰めた広大な大地をひた走る赤い観光列車。
絵のように美しくも雄大荘厳な景色が連なる中で、私が一番大きなカルチャーショックを覚えたのは3,970mの標高を誇るアイガーの北壁の前に立ったときだった。感動の言葉を探せない。
地球の壁を突き破って出現した巨大なアイガーの北壁は天を突こうとしていた。まさに驚天動地の自然の力が創り出した絶景であった。猛々しい造山運動の鼓動が伝わってくるのかと思っていたら、静寂そのものだった。(山には神さまがいらっしゃる!)、私は生まれて初めてそんな敬虔でおごそかな気持ちになった。
一陣の風が頬を撫でた。雲の流れが眼前にはだかる黒く鈍く光る巨大な壁に一瞬の明暗を作った。私はよくきたね、と言われたような気がした。全てを受け入れるとはこんな瞬間を言うのかも知れない、そう思った。心の中を幸せが満たしていった。人間って、自然の中にあっては何とちっぽけな存在なのかとも。
スイスの旅の余韻はしばらく続いて私の心を豊かにしてくれた。七十歳になったいま、もう死という現実が透けて見えるようになった。ちっぽけな私、でもやりたいことをやろう。せずして悔いを残すより、やって結果を楽しもう。それが、私の七十歳のバイブルになりそうである。
了