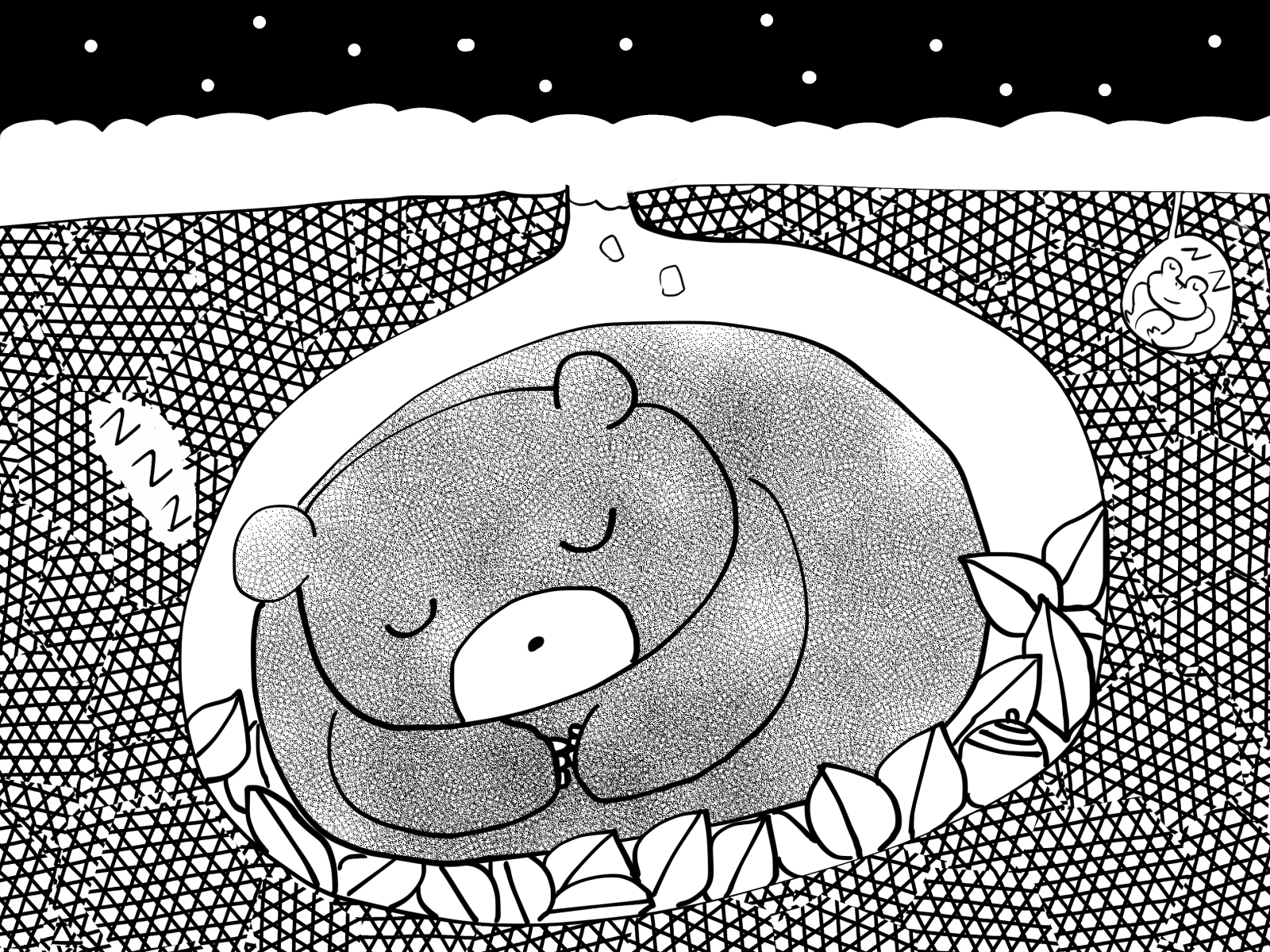
第3編 思わずこだわってしまった泡沫話
―――たまたま知った関心事についつい深入りしていました――
05. 蜂蜜とミツバチの話
05-1. 「虻蜂取らず」ってどんなこと?
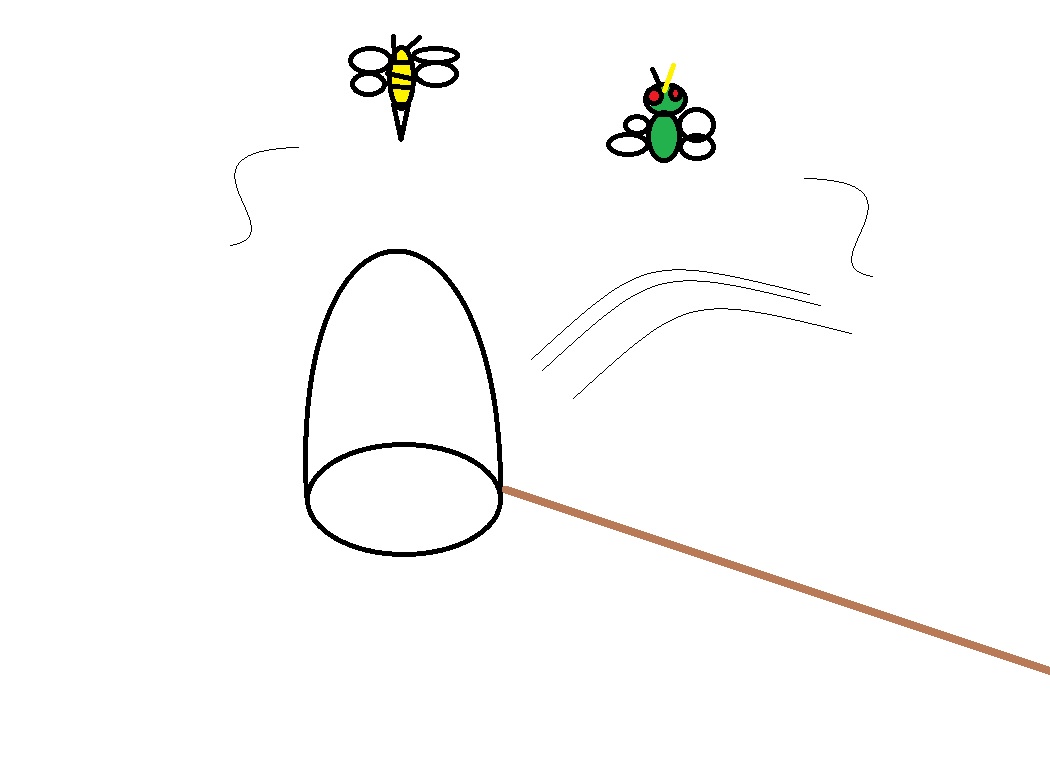
ふと蜂に関することわざ・格言類を調べてみたくなった。知られているものには、次のものがある。
「虻蜂取らず」(虻蜂とらず、虻蜂捕らず)
「泣きっ面に蜂」(泣きっ面を蜂が刺す)
「蜂の巣をつついたよう」
「蜂起」
他には、「蜂誇り」「蜂払い」「石地蔵に蜂」「牛(鹿)の角を蜂が刺す」などもあった。
ついでにいえば、類似語には、「二兎を追う者は一兎をも得ず」「一も取らず二も取らず」「花も折らず実も取らず」「欲は身を失う」などがある。
また、対義語には、「一石二鳥」「一挙両得」「一発双貫」などがあげられる。
目新しいものに「蝶のように舞い、蜂のように刺す」というものもあった。これは、かつての偉大なボクサー、モハメド・アリのファイトスタイルの代名詞で、「ヘビー級でありながらも華麗なフットワークで相手の攻撃をかわし、一瞬のスキをついて強烈なパンチで仕留めるさま」を言い表した言葉だそうだ。
私には「蜂の一刺し」がまず思い浮かんだが、格言に入っていなかった。これは「蜜蜂が一度差したら死んでしまうことから、自分の命をかけて相手に致命傷となる一撃を与えること」を意味する。
意外に思ったので、入っていない理由を探ってみた。自分なりの結論を先に言えば、故事というほど歴史的に古くないからだろう。この言葉が生まれるきっかけは、1981(昭和56)年10月28日と新しい。
このころ、有名なロッキード事件で世界が揺れた。田中角栄元首相が賄賂受領疑惑で問われていた。被告側が必死に無罪を主張している中、検察側証人として出廷し、有罪に追い込んだ女性がいた。首相元秘書・榎本敏夫の前の妻だった榎本三恵子氏である。
裁判で、彼女が田中被告の5億円受領を裏づける重要証言をした日が10月28日。11月4日の記者会見で「真実を述べるのは、国民の義務だと思います。……蜂は一度刺すと命を失うと申しますが、人を刺す行為で、私も失うものが大きいと思います」と発言した。
このことから「蜂の一刺し」の言葉が生まれ、当時、流行語にもなった。心に残る言葉だった。
蜂が人を針で刺すと死んでしまうのは事実である。ただし、蜜蜂に限られ、実際に刺すのはメスに限られる。人と接触する機会が多いのは働き蜂=メスだから。針が釣り針型(逆棘)である独特な構造にある。
人などの皮膚を刺すと、逆棘が引っかかってしまい、蜜蜂の針は抜けなくなる。蜜蜂の方も、針が抜けなくなってしまい、無理に針を抜こうとするので、蜜蜂の腹部の末端はちぎれてしまう。腹部がちぎれてしまえば、いったんは自由になった蜜蜂も、しばらくして命を失ってしまう。
一方、針には腹部の末端も残っているので、腹部の末端にある毒をためている袋から針に向かって毒が送り続けられる。皮膚を刺されたままにしておくと、人体に毒が注入され続けることになる。
蜜蜂は、蜂蜜の生産や植物の受粉など、私たちの生活に貢献し、見た目も可愛らしい。おとなしいから、人間から刺激をしなければ刺しに来ることはほとんどない。このことに注意し、ずっと仲良く付き合っていきたいものである。
「蜂の一刺し」は、歴史に残り、やがて格言の一つに加わる日がくると思われる。
さて、古くからよく知られていることわざに「虻蜂取らず(アブハチとらず)」がある。短文で何となく語呂がよく、一度聞くと頭に残りやすい。語源や由来は不明で、人の行動から生まれた教えの一つだと説明される。
明快なようで、表現にこだわってみると、知らないと「何を言っているの?」となりそうで、必ずしも容易な理解とはならない。
意味を知らない人に聞くと、文字通り「虻、蜂取らず」や「虻は蜂を取らず」と理解し、「虻は同じ虫であるから蜂を取らない」「虻は蜂が恐ろしいから近づかない」などの解釈をするそうだ。
そこで、こだわって探究を試みたくなった。この後の文はその探究の経過を綴ってみたものである。
「虻蜂取らず」は西洋のことわざ「2兎を追う者1兎をも得ず」と同じ意味を持つとされる。このことわざの意味するところは誰にもわかりやすい。
よく体験することを言い表している。元は猟師の話だが、2羽(匹)の兎(ウサギ)を同時に追いかけて、両方を捕らえようとすると(それぞれ方向を変えてばらばらに逃げられてしまい)2羽ともつかまえられず、失敗してしまう。
このことわざは一般化すれば、「欲張り過ぎるな」「やり始めたことを途中で変えるな」「物事を始めるにあたっては、準備と決断が必要だ、目的や方向を明確に一つに絞ったほうがよい」という教えや戒めである。
「虻蜂取らず」は、元の表現は「虻も取らず蜂も取らず」であったのが簡略化されたそうだ。意味は「あれもこれもと狙って、一物も得られないこと」「欲を深くして失敗すること」などとされる。
「虻と蜂」が登場する理由は、一般的に「虻」も「蜂」も生活の中でなじみの深い昆虫だからだそうだ。
身近な昆虫を例示するのであれば、「蝶と蠅(チョウとハエ)」でもよかったのではないかと思う人もいるだろう。「虻と蜂」とされたのは、「小さいが攻撃力のあるものの代表」として採用され、熟語「虻蜂」の表現もあり、「容易には捕まえ得ない(手ごわい、困難な)ものは、手堅く対処しなさい(取り組みなさい)」という教訓も暗に含められたとみなされる。
このことわざは主体が不明である。「虻蜂取らず」の「虻と蜂」をつかまえられない主が人間だと考えると、「2兎を追う者1兎をも得ず」と同じ解釈になる。ただ、その前に「なぜ、人が虻や蜂を取ろうとするのか」と素朴な疑問が生じ、説明が説得力に欠ける。
虻や蜂を取り食べたがるものに「蜘蛛(くも)」や「小鳥」が想定される。ことわざの話の筋も通るので納得がいく。
「蜘蛛」だとすれば、網を張って獲物を待ち受けていたらまず虻がかかった。食べに行こうとしたとき、同時に蜂も網にかかった。そこで蜘蛛は先に蜂を食べようと向かった。その間に虻は逃げてしまい、あわてているうちに蜂にも逃げられてしまった、という話になる。
ただ、この解釈は理に適わない? 粘着性のある蜘蛛の巣にかかると、昆虫は脱出不可能では? 蜘蛛はあわてないでも2匹を食べる余裕があるはず? などと疑問符が付く。
「小鳥」だとすれば、「2兎……」と全く同じ意味で、つかまえて食べようと、小鳥が虻と蜂の両方を追いかけたが、どちらにも逃げられてしまった、という話になる。
同類に「虻蜂取らず鷹の餌食」(虻も蜂も取れず、なおかつ鷹の餌になる)ということわざもある。「鷹の餌食」が省略されたので、意味がわかりづらくなった。この説のほうが説得力はある。
虻と蜂の両方を追いかけていた小鳥が、追いかけるのに夢中になって警戒を怠り、自分が鷹の餌食になってしまったとなる。「欲張って2つの事柄に夢中になると落とし穴が待っている。どちらも達成できないばかりか、周囲が見えなくなり、危険に陥り、果てには身を滅ぼしてしまう」という教訓である。
ところが、「虻蜂取らず蚊の餌食」ということわざもある。虻蜂が蚊の餌食になるのは考えづらい。主人公は人間で、虻や蜂を取ろうと草むらに分け入ったら、蚊に刺されて散々な目に遭うという解釈が妥当だ。そうすると、また前にあげた疑問に立ち返ってしまう。
これらについては、失敗した上、更に損することを強調するため、後に言葉を続けたものである、とされる。
ことわざ「虻蜂取らず」の初出は江戸時代の人情本とされ、理解の容易さからは「小鳥説」が、発想の面白さからは「蜘蛛説」が選ばれる。他にも説があるが、国文学者の金子武雄が「蜘蛛説」で説明し、この解釈が主流となっているようだ。
だが私は、やはり主人公は人間で、人や家畜にまとわりつき危害をも加える「虻と蜂」を両方とも一緒に退治しようする人が、どちらかの一つはおろか、両方とも取り逃がしてしまう、というのに親近感を持つ。
なお、「虻蜂……」と「2兎を追う者1兎をも得ず」とは意味が異なるという説もある。
別説の「虻蜂……」では、簡単に手に入りそうな物があるのに、少しだけ良さそうな別の物に手を伸ばし、簡単に手に入るはずだったものさえ失ってしまうようなことをいう。
別の「蜘蛛説」によると、蜘蛛は決して「両方を欲しい」と思ったわけではない。別の虻が網にかかったとしても蜘蛛はおそらく気に留めることはなかった。より美味しそうな蜂がかかったので迷いが生じた。つまり、「虻蜂……」は「高望みをして手近なものさえ失う」や「目移りしているうちにすべてを失う」という意味で使われる。
とすると、「虻蜂……」と「2兎……」は必ずしも同義ではない。
複数といっても虻と蜂の両方が欲しいわけではなく、蜂が手に入れば虻は取れなくても構わない。欲を出すという意味では同じでも、「虻蜂……」は質に関する欲であり、「2兎……」は量(または異なる複数目的)に関する欲である。
「目標を絞りきれていない」という意味では同じでも、「虻蜂……」は明らかに片方を「容易に取れる」とし、より良い方を求めている。これに対し「2兎……」は同等の両方を欲しいのである。虻と蜂では価値が違う。2兎には価値の差はない。
「虻蜂……」は、わかりやすさからか、明治期に入り一気に西洋の翻訳「2兎……」に主流を奪われてしまった。含蓄のある意味合いを含む「虻蜂……」も末永く残したいことわざである。
以上に、ことわざ「虻蜂取らず」については、意味や解釈がいろいろあることを紹介した。
その直後、その存在をほとんど知られていなかったと思われる専門家の記述を偶然見つけた。参考になり、裏付けの資料にもなると判断されるので、追記しておきたい。
蜘蛛研究の専門誌『KISHIDAIA』(東京蜘蛛談話会の会誌で同会が発行)第72号(1997年10月発行)収録の追悼文「大熊さんに送る言葉」(新海栄一記、13~15ページ掲載)の中で述べられていた。新海は、蜘蛛の分類等を専門とする研究者で、蜘蛛の生態写真撮影では世界の第一人者といわれる写真家である。
ことわざ「虻蜂取らず」は蜘蛛の行動から出たものらしいという話題が学界であり、当時、蜘蛛学者間でも関心が持たれていた。この経緯を述べ、新海自身が調べてわかったことを記している。以下の引用文は、新海の文章そのままではなく、筆者が内容を整理して紹介したものである。
「虻蜂取らず」の言葉の初出は、江戸時代後期の1820~30年ごろに活躍した為永春水等の人情本の中。「花の志満台4ノ19回」の中に出てくる会話「悪くすると虻蜂取らずにならうもしれねーや」(日本国語大辞典、小学館)である。
意味は「あれもこれもとねらって一物も得られない」(広辞苑、岩波書店)。この意味だけが、江戸、明治、大正、昭和と受け継がれ、肝心のことわざができた理由については全く伝わっていなかった。
1959(昭和34)年、ことわざの研究者である金子武雄が次のように発表した。
「人間が虻や蜂をわざわざ取ることは考えられない。これはクモが網にかかった虻を取ろうとしたところに、今度は蜂がかかり、蜂を取ろうと向かったすきに虻が逃げ、さらに蜂にも逃げられた状況を、だれかが見ていて言ったものである」(筆者注:出典不記載)
この説については賛否両論あったようだが、現在(同:1997年ごろ)では主流を占め、『成語大辞苑』(主婦と生活社。同:大辞典とあった誤記を訂正)など多くの出版社(同:記載7社名は省略)の「ことわざ辞典」にとりあげられている。
私(同:新海)も、蜘蛛が取り逃がした2実例を観察している(同:要旨。詳細具体例は省略)ので、金子説は十分信憑性があると考えている。
以上を手掛かりに、筆者も更に確認追究をした結果、新海の記述を補充・明確化する必要のある事項が判明した。
「虻蜂とらず」の由来は……と、図書館通いをしているうちに、山深く分け入る探検のようなわくわく感にとらわれてしまった。新海の転載ミスや引用不足についての修正・補充にとどまらず、視点を由来考究に切り替えて、資料探しを試みることにした。
このことわざに蜂(と虻)が出てくるのには理由があるのでは? 遠い昔、このことわざを生んだ逸話があるのでは? 蜜蜂絶滅の危機説とつながってくるのでは? などと想像がふくらむ。
あまりわかっていない由来を少しでも明らかにしたいとの思いが募る。由来の解明は「物事の起源とするところや物事が今までたどってきた経過」を明らかにすることである。
「虻蜂取らず」は、今のところ、そもそもの起源がまったくわかっていない。だから、言葉(文字表現)そのものからは、意味が今1つピンとこないのである。
ただし、少しずつかも知れないが、たどってきた経過はわかるはず。使われた用例を見つけ、比較検討することで、過去にさかのぼることは可能だ。頂上に至る裾野の探索はいっぱい残っている。新海の記述の確認の過程で、このことに気づかされた。
ともすれば、用例の1つにすぎないものが、思い込みで起源(源典、初出)扱いにされがちになる。わかった気が更なる追究の気力を弱める。
「虻蜂取らず」の場合にも、そんな一面があり、その時点の資料を説明に使い、わかったつもりや語源や由来は不明と割り切る気持ちにつながっている。
読み返すと、筆者(私)が書いた「『虻蜂取らず』の意味」もその例に漏れない。
これから取り上げる資料も、素人の思い付きでやることだから、高が知れている。すぐに底を突くかも知れない。だが、少しでも何かがわかり、検討の材料や刺激となって一歩前進に貢献できたら幸いだ。そんなささやかな希望を込めて踏み出したい。
「虻蜂とらず」にならないよう、まずは新海の記述の検討に限定してやってみる。改めて、先にあげた新海記述「大熊さんに送る言葉」の一部を直接引用する(以降「新海記述」と略す。句読点と記号類は変更)。
「虻蜂取らず」の言葉が最初に出てくるのは、江戸時代後期の1820~30年頃に活躍した為永春水等の人情本の中の、花の志満台4ノ19回中に「悪くすると虻蜂取らずにならうもしれねーや」という話しが出ています(日本国語大辞典、小学館)。
国立国語研究所所蔵の筆耕木版印刷本の出典に直接当たってみた結果、該当部分の記述は「悪るくすると虻蜂とらずにならふも知れねへやス」(漢字には振り仮名あり)であった。
小学館発行『日本国語大辞典』の1972年第1版と1979年第2版の第1巻は、人情本・花の志満台・4・19回「悪くすると虻蜂取らずに、ならうも知れねえやス」であった(2006年精選版第1巻では、人情・花の志満台(1836-38)4「悪くすると虻蜂取らずに、ならうも知れねえやス」に修正)。いずれも、「虻蜂」には片仮名で振り仮名あり。
引用元本の書名は、正式には『比翼連理花廼志満台』で、略称なのか、表紙が『花の志満台』の場合もある。全4編で、初編は1836(天保7)年、2編は1836年、3編は1837年、ことわざの書かれている4編は1838(天保9)年の刊行である。
ことわざの収載部分は『比翼連理花廼志満台第4編巻之上第19回、松亭金水編次』となっている。
繰り返しになるが、新海栄一の記述にも『日本国語大辞典』にも明記されていない事項を含めて整理すると、ことわざ「虻蜂とらず」の収載本は次の書誌となる。
松亭金水作、歌川国直画『比翼連理花廼志満台(花の志満台)』第4編の上第19回、1838年刊(国立国語研究所などが所蔵し、画像公開もしている。板元は江戸の丁子屋平兵衛または不詳)
なお、作者の松亭金水(しょうてい・きんすい、1797~1863年)は江戸時代後期の人情本などの作家。新海栄一のあげた為永春水の弟子である。
これで確認できたことは、1838年には「虻蜂とらず」の用例があった(初出とは言い切れない)こと、いま主流の「取らず」の漢字書きは、昔は「とらず」の平仮名書きだったこと、の2点である。
新海記述は、前の引用に続いて次の文が載っている。
虻蜂取らずの意味は「あれもこれもとねらって一物も得られない」(広辞苑、岩波書店)ことですが、この意味だけが、江戸、明治、大正、昭和と受け継がれ、肝心のことわざが出来た理由については全く伝わっておりませんでした。
意味は、最も権威ある辞書とされる岩波書店の『広辞苑』の説明を採用している。この辞典は、第1版を1955年5月に、最新の第7版を2018年1月に発行(筆者注:投稿当時)。全版に見出し項目「虻蜂取らず」があり、説明の「あれもこれもとねらって一物も得られない。欲を深くして失敗するのにいう」は一貫して変わらない。(第1~2版では「失敗するにいう」と「の」が抜けているが、誤植による欠落と推測される)
1997年10月の新海記述は、2つあげられている意味の1つを省略しているが、後者の「欲を……」も重要な意味である。
伝承については、その後の平成、令和も含めて、そのとおりであり、意味理解の不十分さや違和感などはこの点にあると思われる。
続く文は、次のとおりである。
ところが昭和34年(1959年)にことわざの研究者である金子武雄氏「人間が虻や蜂をわざわざ取ることは考えられない。これはクモが網にかかった虻を取ろうとしたところに、今度は蜂がかかり、蜂を取ろうと向かったすきに虻が逃げ、さらに蜂にも逃げられた状況を、だれかが見ていて言ったものである」と発表したのです。
この部分は重要で中心をなす記述であるが、唯一、引用元が記載されていないので、文献等の確認ができない。先に書いた「『虻蜂取らず』の意味」でも「(筆者注:出典不記載)」とした。
国文学者で元東京大学教授の金子武雄(1906~83年)が、国文学の深い学識を背景に、多面的に日本のことわざの研究に取り組み、画期的な総括的業績を残した当時の第一人者であることは、周知の事実である。「虻蜂とらず」の蜘蛛(クモ)説を唱えた最初の人であろうことも、ほとんど疑う余地のないことである。
にもかかわらず、肝心の最初の文献が示されていない。当初、出典不記載は記載漏れと思ったが、実は、当の新海栄一が該当文献等を確認できなかったから不記載とせざるを得なかった、と判断するに至った。
筆者は、出典を明らかにしたいと思い、ネット検索でキーワードを変えていろいろ試みた。いくつも同様な記述がでてきても、肝心の引用元が判明しない。
現れるのは「昭和34年(1959年)、国文学者の金子武雄氏の発表により、虻や蜂を取ろうとしているのは、蜘蛛(くも)だと解釈するのが主流」と記す酷似の説明ばかり。2019年11月中旬(筆者注:投稿当時)でも大同小異である。
最近のことわざ研究の第一人者・北村孝一でさえ、1986年刊の当該本の朝日文庫版末尾「解説」で「最初に上梓されたのは1959年から62年にかけて……」と書いている。
推測されるのは、掲載した文献のどれかが早い時期に発表年の間違いをし、他の文献はその誤記にとらわれて、孫引きを繰り返したのではないかと思われる。
こだわっていた「1959年」をはずすと、検索結果の様相は一変した。
結果的にたどり着いたのは、1958(昭和33)年6月1日初版発行の金子武雄著『日本のことわざ(一)評釈』大修館書店刊、23~24ページ掲載の「虻蜂とらず」である。(全5巻の完成は1961年9月20日。この名著は、1982年に再刊、1969年と1986年に文庫版も発行)
わずか1年、文献の発表年を間違っただけなのに、出典の明記がこれほど長期間混迷した例は珍しい。
金子の著書の説明は長いので、まず、冒頭の部分を引用する。
虻蜂(あぶはち)とらず
「虻もとらず蜂もとらず」が原形である。このことわざは2つのものを共に手に入れようとして、結局どちらも手に入れられなかったような時に、批評のことばとして用いられる。ところで、このことわざの原義はどういうのであろうか。虻や蜂を人間がとろうとしたものだとは考えられない。……
この記述を読むと、新海記述は金子記述の直接引用ではないと判断できる。
ここで推測した変化は、あくまでも大筋においてであるが、「あぶもとらずはちもとらず」→「虻もとらず蜂もとらず」→「虻蜂とらず」→「虻蜂取らず」と、短小化・漢字化の流れである。
なお、同類の「虻蜂取らず鷹(蚊)の餌食」については、後半が省略されて「虻蜂取らず」になったというよりも、他のことわざとの混同で、逆に「虻蜂取らず」に後半が加えられたものと推測される。
直前に、金子武雄の著書から、このことわざの原義についての引用「……虻や蜂を人間がとろうとしたものだとは考えられない」を示した。さらに部分的に省略して、本文を引用する。
……これは蜘蛛(くも)のことではなかろうかと思われる。蜘蛛が網を張っていた。そこへ蜂がかかった。蜘蛛はこれを捕らえようとして、糸を出して巻きつける。しかしまだ完全にその自由を奪ってはいない。またそこへ虻が網にかかった。(一部略)蜘蛛はひとまず蜂をそのままにして虻に向かって糸を巻きつける。しかしこれもまだ充分に自由を奪わないうちに、蜂が逃げ出しそうになった。あわてた蜘蛛が虻から離れて再び蜂に立ち向かおうとした時、すでに遅く蜂は糸から逃れて飛び去った。しまったと思った蜘蛛が虻だけは逃がすまいと思ってこれに向かって行った時、これもすでに遅く、虻ももがいて逃げ去ってしまった。
この部分の新海記述を引用する。
金子武雄氏は「人間が虻や蜂をわざわざ取ることは考えられない。これはクモが網にかかった虻を取ろうとしたところに、今度は蜂がかかり、蜂を取ろうと向かったすきに虻が逃げ、さらに蜂にも逃げられた状況を、だれかが見ていて言ったものである」と発表したのです。
二つの文章を並べてみて気づくのだが、蜘蛛の網に先にかかったのは、元の金子の著書では「蜂」なのに、引用の新海記述では「虻」になっている。新海記述が「ことわざ辞典」からの引用だからであろう。
筆者(私)を含めて、ことわざ辞典なども、このことわざを述べるとき、金子の蜘蛛説に基づきながら、網に先にかかったのは「虻」だとしている。私が調べた文献類で「蜂」が先にかかったとするのは金子の文献だけであった。
「虻蜂とらず」の語順が「虻、蜂」となっているので、先にかかったのは「虻」との思い込みがあるからか。前後の順は虻と蜂のどちらでもいいのかも知れない。
だが、虻と蜂では価値的に差異があり、より良い方を求めた(欲を出した)という解釈もあることは、既に「『虻蜂取らず』の意味」で述べた。蜘蛛説において、欲深さの結果起こる失敗を説明しているとすれば、説得力は「蜂」を先に置く方が強い気がする。
基にあったのではないかと想像される逸話の存在と共に、今後の追究課題として、あえて指摘しておきたい。
新海記述は次のように続く。
この説については賛否両論あったようですが、現在では主流を占め、成語大辞典(主婦と生活社)はじめ、小学館、成美堂出版、梧桐書院、あすとろ出版、集英社、ナツメ社、日本文芸社他、多くの出版社の「ことわざ辞典」にとりあげられています。
蜘蛛説について「賛否両論」があったとする具体的内容は不明であるが、虻や蜂をとろうとした主体は蜘蛛のほかに小鳥、蛙、人間だとする説もあるので、そのことを指しているのかも知れない。
新海は1997年当時に発行されている多数の「ことわざ辞典」を調べ上げ、蜘蛛説が主流であることを確認している。
新海記述は、次のように述べ、この話題を結んでいる。
私も大磯高麗山でアシナガバチとツクツクボウシを逃がしたジョロウグモを、八王子市小下沢ではガガンボとガを逃がしたコゲチャオニグモなどを観察しているので、金子説は十分信憑性があると考えています。
蜘蛛研究の専門家であり、蜘蛛の生態を撮影している写真家でもある新海は、複数の獲物を蜘蛛が同時に捕り逃がした現場を実際に観察したことがあり、実体験に基づいて金子の唱える蜘蛛説は信用できる、としたわけである。
ついでに加えれば、金子の記述には、次のような説明も書かれている。(一部分省略)
どちらか一方だけに専念すれば、一つだけは捕らえることができたのに、両方をえようとしたばかりに、どちらも捕らえることができなかった。こんな情景を見た人間が、人の世の同じような事象に思い当って生んだのが、このことわざなのではなかろうか。
どんなものでも、力を2分すれば、1つ1つの力は弱くなるにきまっている。数多くの事物を望み過ぎて、結局、獲得のところが少なくなったり、無になったりする例は、世の中にしばしば起こることである。
……人間の世の中は複雑である。虻も蜂も共にとることのできる場合もある。だからそれにひかされて、人間はなん度も失敗を重ねるのである。こうして「虻蜂とらず」ということわざは、永遠に生きて行くであろう。
新海栄一は、このことわざを追悼文の中で触れた。蜜蜂の絶滅と人類の滅亡の予言が脳裏をよぎる。「虻蜂とらず」の由来の探究は、藪に一歩踏み入った段階でいったん終了する。
追記
その後の状況を追ってみると、2021年8月11日更新の『ウィクショナリー日本語版』は、「虻蜂取らず(あぶはちとらず)」は「同時に複数のものを手に入れようとすると一つも手にすることができないということ」とし、次の例をあげている。
「いくらよい品を作っても、そう急に認められるものではないし、相当永い間の辛抱を要する。だからたいがいの人が辛抱しきれなくなって最初の方針を破ってしまうのだが、そこで方針をかえるということは、結局今までの犠牲が虻蜂とらずに終るばかりでなく、かえって信用をおとす結果となる。(相馬愛蔵『私の小売商道』)」(この本の初版は、1952年11月25日、高風館から発行された)
インターネットの『語源由来辞典』には、「虻蜂取らずの類語・言い換え」が多数記載されている。
(2018年11月1日、2019年10月7日~11月14日、ウエブ掲載欄『蜂蜜エッセイ』第3・4回掲載分合作、一部加除)
05-2. 公募エッセイの穴場

だいぶ前のことだが、各種公募の情報を提供する雑誌『公募ガイド』の2019年10月号に「優良公募なのに応募は多くない穴場公募」という記事があった。応募数に影響する要因として、賞金や賞品の魅力、テーマのしばり、権威ある著名人の審査などをあげ、読者に穴場公募への応募を奨励する企画であった。
記事の中に「エッセイ、体験記、作文」の類と思われる「応募数少ないランキング」の第1~5位も示された。「蜂蜜エッセイ」が第1位で、応募数は36(ちなみに、2位70編、3位88編、4位111編、5位199編と記載)とあり、「賞品がアカシア蜂蜜2.4キログラムだけなのが原因か」との説明も付記。つまり、同エッセイは優良公募ではあるが、魅力を感じるだけの賞品が贈呈されないから応募者が少ない、という見解のようだった。
応募数36という少なさに疑問を抱いた。早速、実数を確かめるために、公表されている「蜂蜜エッセイ」の各年度の作品を数えてみた。第1回の2017年度は213編、その後は2018年度99編、2019年度133編、2020年度は途中の2019年8月末の時点(締切日は次年2月20日)で63編であり、どの年度の応募作品数も36を大幅に超えていた。
同誌の趣旨のようなデータ比較は、通常は直近年の確定数値でおこなうはずである。1~5位が同じ19年度のものだとすれば、蜂蜜エッセイの場合は公募ガイド掲載数の3.7倍の133であるから、実際のワースト順位は4位だったことになる。
別の算出方法による数値なのであろうか。どんな基準や起算によったのか興味津々、着眼点に好奇心をかきたてられた。これは関係者に直接聞いてみなければわからない。そこで、何を根拠にした数値か、『公募ガイド』の編集者と「蜂蜜エッセイ」の広報担当者にメールで問い合わせてみた。
両方にメールで照会をしたのだが、後で送った方の回答が先にきた。鈴木養蜂場はちみつ家のWEB担当者からで、概要は次のようなものだった。
「応募数少ないランキング」に掲載されているとは全く知らなかった。公募ガイド側からは何の連絡もなかったので、おそらくその編集部の判断で掲載したものと思われる。当方が応募数をお知らせしたという経緯は全くない。そして「当方では特に苦情を言うつもりはありませんし、そのまま放っておくつもりです」との付記も。
先にメールし、1週間後にも再照会をして、回答を得たのは公募ガイド編集部からだった。メールでの応答を繰り返えして知った内容から推察すると、おおよそ次のようなことだったらしい。
真相はWEBサイト「蜂蜜エッセイ」に載せられている(募集中の)公表作品数を数えた結果が36だったという。2019年3月下旬に募集を開始し、2020年2月20日が締め切りなのを確認しなかった(?)。開始から3か月後の6月下旬までに公表された分を7月ごろ数え、それを掲載した。応募数は、募集初期は少なく、締切日間際が多いのが通例。締め切り後の確定数を使うのが常識と思うのだが……。
応募数少ないランキング第2位に挙げられた体験賞は3年も前の資料だった。回答を寄せた責任者は「応募の少ない穴場を紹介するという趣旨でした。少ないほうが応募者にとってはいい面もあります。もちろん、少ないからだめとも思いません」と言い訳にもならない釈明。興味津々で調べたが、結果はお粗末な凡ミスとわかり、がっかりした。『公募ガイド』2019年11月号は、末尾の「INFORMATION」で「お詫びと訂正」を載せた。
「本誌10月号特集P21にて『蜂蜜エッセイ』の応募数を36編と記載しましたが、これは133編の誤りでした。お詫びして訂正します」
私の照会に対して、責任者から「誤記ですので、次号にて訂正文を出す予定です」との回答があり、それは実行されたが、記述はこれだけで釈明はない。「応募数少ないランキング」の第1位が「蜂蜜エッセイ」であるとした見解に対する修正も、記事の補正もなかった。しかし、愉快なことに、誤り記事の宣伝効果抜群だったのか、同エッセイの応募数はその後大幅に増えた。そして、思わぬ形で一石を投じた。
なぜその後も大幅に増え続けたか。この事実は、応募数に最も影響する要因とされる「賞金や賞品の魅力」とは異なる反響である。作品募集にはオリンピック同様に参加することに意義があり、入賞作に限らず、ほとんど全作品がWEB上で応募順に無料で公表されることが、この募集の最大の魅力と認められたからだと、私は受け止めた。
高額賞金、有名作家賞、高文学水準などを標榜し、最高賞該当なしを繰り返す募集もある。何百、何千もの応募数のものもあって、多くの場合、駄作として日の目を見ることがない募集がほとんどである。質の高い作品を目指すことは当然のことであろう。
それはそうとして、特に高齢者の健康維持と豊かな精神生活を送るために、身体を動かし楽しむ場が求められるとともに、脳を働かせ楽しめる場があっていい。それはひとえに様々な気軽な作品発表の場である。多くの人に読んでもらいたいとの希望もあるが、たとえ稚拙な文章であっても書いて残しておきたい事柄があり、その願いがかなうことが応募者の本音の場合もあると思われる。それは満足感が満たされる掲載の穴場であろう。
ついでに余計な話を付け加えれば、私が「応募数少ないランキング」の第1位を挙げるとすれば、『公募ガイド』の「webおたよりコーナー」である。
これは同誌が新企画・大募集とうたって募集した「【テーマ】公募や創作に関することであればなんでもOK、【文字数】400字~600字程度、【採用】毎週、数名採用。採用者には公募ポイント100Pを進呈。(その他の記載省略)」である。
募集は2018年4月に開始。掲載文は、4月17日に2編、5月2日に3編、6月12日に2編、6月15日に1編、合計8編。受付期間を明示していないのに、確か3か月経過後の6月末だったと記憶するが、突然「おたよりの受付は終了しました。沢山のおたより、ありがとうございました」となった。
毎週、数名採用のはずが、13週で8編とはこれ如何に。まさに「同第1位、賞品が公募ポイント100P(自社商品購入代金100円引き)だけなのが原因か」にふさわしい。
そんな経験があって企画された記事だったのかもしれないが、たぶん、この第1位は将来にわたって揺るがないだろう。
(2022年2月18日、個人仮想作品集『無意根山を望む窓』収録)
05-3. 師匠と尊敬された元養蜂家

蜂蜜や蜜蜂のことを知りたくて、いつものようにネット上で新聞の読み漁りをしていた時、ある話題に目が止まった。2019年11月15日付の佐賀新聞の記事であった。その見出しは「佐賀と札幌をミツバチでつなぐ/亡き父の養蜂まちづくりを発信、多久島さん/実家で活動紹介、蜂蜜試食も」とあり、写真も添えられていた。
話題に出てくる地域、南の九州佐賀県神埼市と、北の北海道札幌市とは、ずいぶん距離が離れている。このことも興味をそそられた。記事には、「佐賀にルーツを持ったミツバチたちが札幌の街中を元気に飛んでいる」とあり、話題の主人公、主婦の多久島和子さんは、「北海道開拓の父」として知られる佐賀藩士になぞらえて「札幌では父(城島常雄さん)のことを『平成の島義勇』と言ってくれた人もいる」と語ったとある。
札幌市民の私は、直感的に「これは面白い物語になる」とマークした。早速、記事の内容を手掛かりに資料で詳細を追究する深読みに着手した。
物語は蜜蜂と蜂蜜をこよなく愛する、佐賀を故郷とする親子(父娘)を中心に進行する。舞台の主な場所は札幌市都心部ビルの屋上。主な時期は平成の後期、平成22年(2010年)3月からの約10年間。物語を始める前に、親子の、出身の誇りと望郷の念とを支え続けたであろう佐賀藩士の島義勇についてふれておこう。
2018年4月、北海道神宮で営まれた島義勇の顕彰祭の集いで、「北海道は佐賀の夢と志が花開いた大地です」と、佐賀県知事が述べている。札幌では、島の銅像を建て、開拓の先覚者・父として慕い、偉業を称え、慰霊祭を毎年開いており、同年は明治維新・北海道命名150年だった。
明治維新での貢献は、薩摩等3藩の武力に対して、肥前佐賀は知力であった。西欧の情報に精通した佐賀藩は対ロシア防衛で北海道の重要性に気づき、藩主が自ら初代開拓長官に就き、島を初代主席開拓判官に任命した。島の仕事は北海道本府としての札幌の建設。整然とした札幌市の碁盤目状の区画を構想するなど、島義勇は都市整備の基盤を築いた。
城島常雄さんが「平成の島義勇」と言われたのは、こうした歴史的由縁を指していると思われる。
物語は、2010年3月に始まる。城島常雄さんの娘・和子さんは結婚し、姓を多久島と名乗り、札幌市で暮らしていた。2007年、母の他界を機に故郷の佐賀県神埼市から父を呼び寄せ、同居していた。それから3年、知り合いもおらず、慣れない土地で暮らす老父を気遣う日々だった。
そんなある日、多久島さんは地元の新聞で市民団体による「さっぱち」の始動を知った。城島さんは60数年にわたり、佐賀で養蜂業を営んでいた。養蜂を知る多久島さんは、父が「ミツバチを見て元気になれば」と思い、早速、86歳の父の常雄さんを誘って養蜂現場を訪ねた。地元の新聞とは北海道新聞で、「さっぱち」とは「サッポロ・ミツバチ・プロジェクト実行委員会」のこと。北海道新聞、2010年3月21日、見出し「札幌都心/ミツバチ飼育/五月からビル屋上に巣箱……」の記事だった。
佐賀新聞によると、親子が「訪ねると、ミツバチも養蜂道具もない状況だった」そうだ。 これを裏づける談話が残っている。現在、同会の流れを引き継ぐ団体「特定非営利活動法人サッポロ・ミツバチ・プロジェクト」で理事長を務める酒井秀治氏が、当時を語ったものである。語り種のように何度も同様な内容があちこちで話される。(引用は部分引用)
同実行委員会を発足させる運びとなったが、「養蜂については誰も知識がなく、始めは何もかも全く手探りの状態でした。札幌近郊の養蜂家にも相談しましたが、活動に賛同を得られるも忙しいと断られており、誰から養蜂に関するアドバイスを受けるかだけが決まらずにいたのです。そんな時、さっぱちが新聞記事で取り上げられ、転機が訪れました」。
新聞記事が縁結びとなり、「神様がやってきた」と語り継がれる酒井氏と城島さんとの奇跡的な出会いとなった。別の記事では次のようにも語られている。
「新聞にさっぱちの記事が載るとすぐに、『父が養蜂をやっていた。養蜂をやっているところを見学させてもらえないだろうか』という問い合わせがきた。城島さんは『娘がボケ防止のためにやらせようと思った』と言うが、城島さんの養蜂への熱意に特別なものを感じた」「『ハチのことが忘れられない、力になれたら』という想いから、活動に協力してくれることになりました」
前に、「誰から養蜂に関するアドバイスを受けるかだけが決まらずにいた」と語られていたが、実は具体的な養蜂の準備は何ら整っていなかったようだ。親子は何もない場所と状態を見学して、現状を知った。普通なら、がっかり、あきれて帰るところだが、親子はむしろ養蜂への郷愁に駆り立てられたようだ。その場でさっぱちを救う決心し参加を決めた。
佐賀新聞の記事には「2人はすぐに使い慣れた養蜂道具を取りに神埼の実家に戻り、ミツバチも佐賀の養蜂家に手配した」とある。2人とは、もちろん、多久島和子さんと城島常雄さん。
このことを、「さっぱち」の酒井秀治氏は、次のように述べている。「さっぱちへの参加を決めると、城島さんは佐賀にもどり、かつて使っていた養蜂道具を北海道に送った。足りないものは地元の養蜂仲間に頼んで調達してくれた。ミツバチも城島さんの知り合いである佐賀の養蜂家から取りよせた。養蜂業は素人がやるには難しい業種と言われている。素人が頼んでも、健康なミツバチが届くとは限らない。5月26日に佐賀を出発したミツバチは船に揺られ、4日後の30日に札幌へ到着。翌日、太陽ビルの屋上に3つの巣箱が設置された。ふたを開けた巣箱からは、ミツバチたちが元気に札幌の空に飛びたった」
本格的な養蜂活動は2010年6月にスタートした。以上からわかるよう、すべて城島さんの経験に基づく配慮と手配で実現した、と言っても過言ではなかろう。「神様がやってきた」とは、決してオーバーな表現ではなかった。
急ごしらえの発足だったが、サッポロ・ミツバチ・プロジェクトは順調に進んだ。当初の様子は、5月下旬から6月下旬にかけて、朝日新聞(北海道内版)の記事、HBCとHTBとNHKのテレビニュース、北海道新聞の特集記事などで広く市民に知らされた。
佐賀新聞の記事は「常雄さんは『師匠』『お父さん』と慕われながら、メンバーに養蜂や採蜜の方法を1から指導した。ビルの屋上で制約があり、すぐにミツバチの様子を見に行けないなど苦労もあったが、試行錯誤しながら、都市型養蜂を確立した」と続く。
実行委員会発信のホームページを見ると、関連の各種の文章に添えられる養蜂作業の実際場面の写真には、麦わららしい登山帽に面布を被り、しゃれたピンクのワイシャツを着て慣れた手つきで巣板を扱い、説明している様子の人物がしばしば登場する。その方が城島常雄さんだった。
「すべてゼロからの出発だった」と述懐されるように、城島さんを取り巻き、熱心に養蜂のイロハを教わる会員の姿はまさに弟子。「師匠、あのー」と真剣に質問する眼差しは、尊敬の念で見詰める。うなずきながら聞き入るのはいい歳をした大人だが、年齢的には親子の開きがある。親しみを込めて「お父さん」と呼ぶ人もいた。
フリー百科事典『ウィキペディア』には、「養蜂技術は、立ち上げ時の新聞報道を偶然目にした元養蜂家の城島常雄に指導を受けつつ、北海道のビル屋上に適した飼育方法を探っている」とある。酒井氏らは、巣板の扱い方、蜂蜜の溜まり具合、燻煙器の使い方、分蜂を防ぐ方法など、城島さんの作業姿を見ながら1つ1つ学んだという。
城島さんの指導法は、1度自分の作業を見せた後に酒井氏らにやらせ、口出しをしないで見ているだけという厳しさを含んだものだった。これは1日も早く自立できるようになってほしいという城島さんの親心だった。「歳だからいついなくなるかわからんでしょう。だから早く覚えてほしい」との切迫感もあった。
そんな想いを物語るエピソードを探して紹介する。屋上養蜂が始まって2か月を少し経過したころの取材レポートが残されている。ポータルサイト「北海道人」に載った記事の1場面である。城島常雄さんの作業をじっと見つめる酒井秀治氏の写真。実際の作業姿を見せて、孫ほど離れた素人に、プロの技と知恵を1つずつ伝授されていく場面。
「ある日の2人のやり取りはこんな内容だった。『お父さん、この巣箱のハチだけいつも気が荒くて、蜜の量が他より少ないのはなんでしょう』『品種改良しましょう。気の荒いハチをカットして、おとなしく勤勉なハチだけを残しましょう』これは、おとなしくてよく働くハチのいる巣箱から女王蜂の幼虫をもってきて、気の荒い巣箱に入れて品種改良をする方法で、こんなプロの技を身近で経験している」
始めたばかりなのに、もうこの地に適応する品種改良に着手している。
載った記事のエピソードをもう一つ。ある日のワークショップに参加した中学3年生斉藤君と師匠城島さんとのツーショット。数ある城島さんを撮った写真の中で、これほどにこやかに晴れ晴れしい顔で写っているものはない。年齢差71歳を超えた2人が、蜜蜂への想い1点を見詰める瞬間である。
この日、お母さんと一緒に参加した斉藤君は、将来、養蜂家になりたいのだそうだ。蜂飼いが登場する物語、上橋菜穂子著『獣の奏者』を読んで、その想いを強め参加した。「中学生が養蜂家と会い、直接指導が受けられるような機会はそうあるものではない。斉藤くんは、ワークショップに参加し、城島さんと直接交流することで、夢に向けて一歩一歩前進している。城島さんがこのプロジェクトに参加して一番うれしかったのは、養蜂家になりたいという斉藤くんがいることだそう。酒井さんも同様に、幼い世代が養蜂に興味を持ってくれることがうれしいと語る」
添えられた写真に「さっぱちで養蜂を見学した中学生から届いた夏休みの自由研究のレポート。丁寧でわかりやすく、すばらしい出来。きっと百点にちがいない」と書き添えられている。
城島さんの活躍ぶりは、出身地の佐賀県神埼市の『市報かんざき』2012年6月号に、題名「ベテランの技術でミツバチ飼育のお手伝い」で紹介された。ピンクのワイシャツ姿で頼もしく指導に当たる写真も載った。その一部分を抜粋する。
「平成22年に発足した実行委員会で養蜂や採蜜の指導にあたったのが城島さんです。佐賀での65年間の養蜂経験を活かし、参加者に1から指導を行いました。活動が始まった3年前は3万匹だった飼育数も現在では約12万匹に増え、観光資源開発や緑化推進など様々な効果が期待されています。そのプロジェクトで師匠として活動を支えている城島さんは今年88歳を迎え、後継者の育成にも力を入れるなど、ますます精力的に活動されています」
さっぱちのホームページの報告には、赤いエプロン姿で作業の試技を示す女性も、時折、登場する。城島さんの娘の多久島和子さんは、父に寄り添いながら、実行委員や理事も務め、会の中心人物の1人として活躍し、親子で技術的面の指導に当たってきた。
物語は、一足飛びに現在へ。佐賀新聞の記事で結ぼう。「札幌市在住でNPO法人会員の多久島和子さん(66)が、神埼市神埼町の実家で、札幌のビル街の養蜂によるまちづくりを紹介している。『さっぱち』の取り組みで、亡き父の佐賀での稼業が原点。『佐賀と札幌をミツバチでつなぐ活動を知ってもらい、新しいつながりが広がれば』と話している」
「『師匠』は2016年に91歳で亡くなったが、ミツバチに対する姿勢や技術は引き継がれ、佐賀にルーツを持ったミツバチたちが札幌の街中を元気に飛んでいる。さっぱちの活動は10年目に入った」「実家を開放し、活動の様子を写真や映像で発信。『お茶気分で気軽に立ち寄って。都会の蜂はどこに飛ぶか分からず、採蜜日で味が変わる蜂蜜の試食もぜひ』と多久島さん。ライラックにラベンダー……。いろんな花から集めた蜂蜜を販売している」
実家の玄関で写された掲載写真には、活動を語る沢山の説明や写真、蜂蜜製品などと一緒に、城島さんの表彰状と思われるものが何枚も並ぶ。もちろん、中央には、佐賀と札幌をつないだ主人公、多久島さんの凛とした姿が写っている。
(2020年2月5~13日、ウェブ掲載欄『蜂蜜エッセイ』、第5回掲載分合作。一部加除)
05-4. 蜜蜂に赤色はどう見える?

別稿の「師匠と尊敬された元養蜂家」(05-4参照)を書いていて、ふとひらめいた。
巣箱の巣板を取り扱う際の作業着の話。写真での印象だが、80歳代後半の元養蜂家の城島常雄さんの服装はピンクのワイシャツ姿が多かった。養蜂経験もあるその娘の50歳代後半の多久島和子さんは赤いエプロンを着けていることが多かった。
養蜂活動時に、思い思いの多彩な服装で参加する人たちの中にあって、2人の赤系統の服装は目立った。おしゃれや若作りの服装か、指導者として際立つための配慮かとも思ったが、何度も同様の服装が写真に出てくるので、蜜蜂を直接扱う時の効果的服装、つまり蜜蜂の色覚に関係するのではないかとの思いが強まった。
普通に考えれば、夏場、道具保管室に置いておき、時折着るだけの作業服だから、同じものを着ることになると思えば、気にするほうがおかしいのかもしれない。それでも、もしかして人間とは違い、蜜蜂には赤系統の色が見えていないか、あるいは別の色に見えていて、危険を察して刺しにくるような刺激を蜜蜂たちに与えない効果があるから、養蜂のプロはそのような服装をするのではないかと推理した。うがち過ぎるとは思いながら……。
案の定、販売の養蜂着を調べてみると、まちまちで、登山帽ふうの帽子などを含めて、大多数は白色系統や淡い色物であった。ピンクも有るにはあったが、ごく少数派の部類。取扱店の推奨には「蜜蜂はおとなしい生き物なので、上手に扱えばめったに刺されるものではありませんが、なるべく肌がでないように身をつつみ、蜜蜂から外敵と思われない明るい色の服装が最適です」などとある。これには、やはり白色系統や淡い色物が該当する。
だが、赤色系統と蜜蜂の色覚とは無関係、濃い色に属する赤は養蜂着には不向き、と自ら結論づけるのは悔しい。ヒラメキは捨てがたい。「養蜂伝統の知恵から導かれた服装。不思議、発見!」と喜びたくて、さらに蜜蜂の視覚、色覚や、見え方の人間との違いなどを、専門家はどうとらえ、どう説明しているか追究してみたくなった。
養蜂場の専門家の見解を見てみよう。例えば、鈴木養蜂場の「はちみつ家のブログ」(2012年6月27日)によると、「ミツバチが認識できる色は6色だと言われています。黄色、青緑、青、紫、紫外線、そして黄色と紫外線の混合色の6つで、中でも黄色と紫外線の混合色というのはビーズパープル(ハチの紫)と呼ばれる特殊な色なんだそうです。そして赤が識別できないので、赤い花は黒に見えるのだそうですヨ。人間の感覚でいえば、赤が黒で、あとは黄色と青色だけの世界といったところでしょうかネ? なんか想像しただけで、無機質で幻想的な世界が思い浮かんできます」とあった。
「アーやっぱり!」。図星を突いたとまでは言えないにしても、赤が別の色(黒)に見えているらしい推理は当たっていた。念のため、別の見解にも当たってみた。「セルズ環境教育デザイン研究所」によるもの(2018年6月28日)を要約してみる。
動物は光の波長の違いを色の違いとして認識する。この波長の違いによって、順に「赤外線、赤、橙、黄、緑、青、藍、紫、紫外線」と色分けされる。(他の文献では「藍」はあげられない場合が多い)
この認識の可能・不可能は、あくまでも受容する(見る)側の問題である。人間は、この中の「赤~紫」は認識できるが、「赤外線」と「紫外線」は認識できない。蜜蜂は、赤色を赤色として見ることができないが、紫外線を見ることができるとされる。人間の認識とはずれていて、「橙~紫外線」を見ていることになる。
さらに蜜蜂は、人間ほど正確に認識できないとされ、橙と黄と緑を「黄っぽく」、青と藍と紫を「青っぽく」認識すると言われる。そしてそれぞれは、一様ではなく、混色で微妙な違いをもって見えるらしい。これには、白や黒の見え方の説明がないないが、蜜蜂の視覚例では、赤の部分は暗い灰色で示されている。
他の見解には、「赤」は「黄」に見えて、蜜蜂の「黄、緑、青」の3色だという見解もある。どうやら、いろいろな説があるようだが、問題の「赤」については、多くの見解は「黒く見える」が大半のようだ。
蜜蜂の眼には「赤は見えず、黒に見える」という。とすると、素人には、黒は色なのではないのかと、けげんに思う。本筋から離れるので、結論だけ言えば、白や黒や様々な濃度の灰色は無彩色といい、色がない。彩度がゼロで、色は明度だけで決まり、色相は変わっても色は同じ。やはり、ちんぷんかんぷん。単純に、どんな色でも光の当たらない側の物影を思い浮かべるとわかりやすいかもしれない。
では、蜜蜂があのように正確な行動ができるのはなぜだろう。人間には見えない紫外線を手掛かりにしている。蜜蜂の主な特長は紫外線の認識にあり、これによって、周囲を自由に飛び、蜜源の花を見つけ、仲間に餌場である花の位置を八の字ダンスで的確に伝えることができるわけである。
紫外線は太陽から発せられるので、太陽が沈み紫外線が見えない夜には飛べない。ハウス栽培の授粉などで、昼でも紫外線カットの状態になると、訪花活動が狭まったり、しなくかったりする。
最初に述べたヒラメキに戻って、刺激の強弱から見れば、淡いピンクのワイシャツは蜜蜂をあまり刺激しないと思われるから、「養蜂伝統の知恵から導かれた服装」と言えなくもない。しかし、赤いエプロンは、黒に見えて、蜜蜂に与える刺激は強い方と言えよう。これを「養蜂伝統の知恵から導かれた服装」とみなすのは無理だろう。ということで、私のヒラメキは、残念ながら「的を射た」とは言えない。
ここで、別稿の記述にも言及しておく。「言い伝えとして、蜜蜂は、目線上に黒色で光るものを見つけると、警戒し攻撃する特性があるとされる。天敵の熊が黒いからだ、と。だから、黒いカラスも追いかける……」と、そこで述べた。実績のある事実ではある。
ただ、黒く見えるという刺激だけで狙って攻撃するわけではないようだ。巣に近づいてくるもの、攻撃を仕掛ける(追い払おうとする)ものに、色とは無関係に攻撃し、巣や群れを守ろうと襲いかかる。においに敏感で、嗅覚が鋭い。強い香り、人の体臭、甘いにおいの食べ物などに反応して近づく。大きな音や激しい動きにも敏感だとされる。要するに、蜜蜂が熊やカラスを攻撃するのは、自分たちが「襲われてしまう!」と、防衛本能を働かせるからだろう。
その後偶然、前にとり上げた「はちみつ家のブログ」について、学生が書いたレポートに出合った。先に、そのレポートを紹介する。
「多くの被子植物の花が目立つのは受粉を効率よく行う為だと学んだ。また、花の色は多種多様であり人間と犬の色認識が違うように色認識は昆虫の種によって異なるはずである。本当に花は色によって目立つのかについて考えた。/花粉を運ぶミツバチを例に考えた。調べてみたところミツバチは『黄色、青緑、青、紫、紫外線そして黄色と紫外線の混合色の6つで、……中略…… 赤い花は黒に見える』(参考文献:鈴木袈裟美、鈴木養蜂場はちみつ家のブログ、参照2017・6・20)ということが現在わかっている。/とすればミツバチにとって赤い色の花は黒い花であり、茶や黒は木の幹や土の色と同じであり色によって花を見分けるとすれば花粉を運んでほしい植物に赤い花はあり得ないはずである。しかし日本に広く栽培されているツツジには赤色の花が多く存在し、ミツバチも共存している。このことから花を目立たせるには色以外の要因があると考えた。/まずは蜜の匂いである。しかし蜜の香りは様々な植物が存在する中、際立って目立つとは考えにくい。/次に考えたのは花の形だ。花が大きかったり、小さい花が集まって咲くことで目立つことができる。しかも花の形は視覚、つまり色認識も視覚によるものなので認識可能範囲は色による判別と同じことになる。/したがって私は花が目立つ為に植物はまず形を変化させその後色による多様性を獲得したのだと考える。」
早稲田大学教育学部の園池公毅教授は、様々なことを学生や一般にネット上で公開している。その中には講義に関するものもある。2017年前期の教育学部3年生対象の「植物生理学Ⅰ」の講義では「植物の花の色素と花芽分化」が解説された。
この講義に関して寄せられた学生のレポートが、直前にあげたものだった。レポートに出合って、「オーッ!」と驚いたのは(正直に言えば、ニャッとしたのだが)、参考文献(ブログ)の著者名が「鈴木袈裟美」となっていたこと。引用されたブログは、詳しくは「ミツバチと共に90年♪鈴木養蜂場はちみつ家のブログ」。掲載開始は2011年9月2日、筆名「はちぶん」が担当。「はちぶん」の実名が「鈴木袈裟美」なら適切なのだが……。「鈴木袈裟美」という人物は、同養蜂場の前身「はちみつ家」の創業者。大正時代の中期、信州の松代から50群の巣箱を現在地の須坂に持ち込んで蜜蜂を飼い始めたとされる。創業は1921年(大正10年)、約100年前である。会社のブログの引用は、責任者(社長名)や会社名を示すのが適切であろう。当例の場合は、会社名が別に入っているので、現社長の鈴木健太郎氏。老舗の創業者が解説したのなら、すごい話。実際に、たぶん「はちぶん」の解説も引用だろう。それにしても、著者名が創業者だとは愉快な事実である。
このレポートに対する教授のコメントは、次のとおりである。
「引用された部分ですが、そもそも、人間には紫外線は見えません。それなのに、『赤い花は黒に見える』と断言しているのは変だと思いませんか? 人間には赤に見えても、ミツバチには紫外線が輝いて見えるかもしれませんよね。もう少し、人の話をうのみにしない姿勢が必要でしょう。人の話をすぐに信じることは、一般的には美点ですが、科学の世界では欠点と言ってよいかもしれません。」
学生が引用した部分は、私も引用したものなので、教授からの講評は私自身にも当てはまり、いささか耳が痛い。
園池教授の指摘は「ミツバチには『赤い花は黒に見える』と断言しているのは変だ」ということだった。それでは、蜜蜂の色の認識をどのように捉え、どう表現されるのがよいのか。前に「セルズ環境教育デザイン研究所」の見解も挙げたのだが、さらに別なものを探してみた。
まず、「山田養蜂場ミツバチ研究支援サイト」を見つけた。「眼」の解説には「……複眼は、広い範囲の色(光線の波長)を受光できるが、明確に識別できるのは、黄色、青緑、青、紫、紫外線、および『ハチの紫/ビーズパープル(注:筆者が英語を片仮名化)』と呼ばれる色(黄色と紫外線の混合色)という、6つの色調だけである。ミツバチは赤を識別できないので、赤い花は黒に映る。……」とあった。ふと気づいて比較してみると、学生や私が引用した「はちみつ家のブログ」の記述と酷似。情報源は同一か。
次に、フィンランドにあるという会社「フナヤウフトゥマ」のホームページにある「ミツバチの感覚」を見つけた。「視覚」の解説には「……ミツバチは、スペクトル派長(光線の波長)を受光でき、黄色、青緑、青、紫、紫外線を識別することができます。また波長の範囲内でそれぞれの色と色の間の影―中間色―を識別することもできますが、主な色調ほど明確には識別できません。ミツバチには赤い色はグレーに見えますが、採蜜対象となる赤い花というのは、正確には赤紫色をしているので、ミツバチはそれらをブルー、もしくは紫外線の反射として認識します。……」とあった。
この説明で、教授のコメントの「ミツバチには紫外線が輝いて見えるかもしれませんよね」という示唆の意味がわかる。どうやら、私などは人間の色覚を念頭に、狭く「色」にこだわり過ぎた感があった。それぞれの解説の「……」で省略した部分を含めて、総合的な観点から蜜蜂の眼の構造や感覚の認識の仕組みを、見る側から捉える必要があったようだ。
また1つ、知恵を授かり、勉強させられたような気がした。
(2020年2月14~17日、ウェブ掲載欄『蜂蜜エッセイ』第5回掲載分合作。一部加筆)

