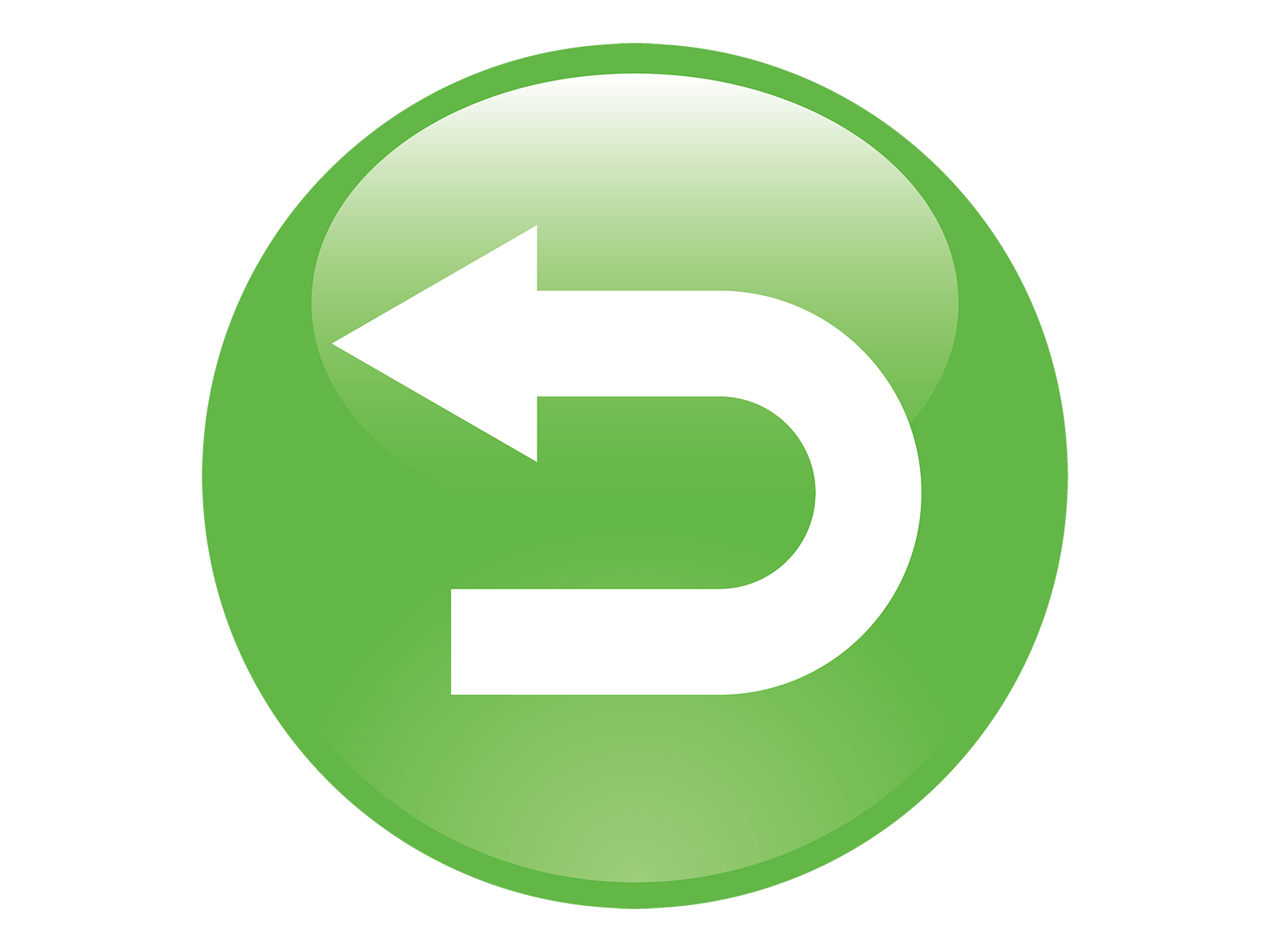霧島山
ミヤマキリシマ 花だより (その2)
「私たちの子育て事情」(by あひる)
私はこの南国の地で生まれ育ち、結婚し、娘と息子を一人ずつ授かった。ふたりの誕生日は三歳と二日違いである。
お産に弱い私は幸奈を千七百グラム、息子は二千三百グラムで産んだ。その当時二千五百グラム以下の赤ちゃんは保育器に入るきまりだったので、ふたりとも生後一カ月の間は保育器と看護士さんに育ててもらった。
幸いふたりともすくすくと元気に育ってくれたが、最初から自分が育てたわけではないので、親としては少々負い目を感じている。
小さく産まれた幸奈であったが、自分自身は結婚して女の子と男の子を平均的な体重で産むことができた。私の孫たちである。
孫娘と孫息子は三歳と二カ月違いだった。もちろん幸奈は自分の子供たちを、自分自身で最初からしっかりと育てた。
保育士だった幸奈は赤ちゃんの世話も完璧。出産後、長々と実家に居座った私に比べ、娘は最初のお産は日があけるとすぐ自宅に帰り、二度目のお産は自宅近くの病院でさっさと済ませた。何だか私の立場はないように思える。
ところが幸奈は、ふたり目の子が満一歳の誕生日を迎える一週間前に大きな決断を下した。こらえ性がないため仕事が長続きせず、収入も不安定な婿に、とうとう愛想を尽かして実家に戻ってきたのだ。
わが家では主人が定年退職して嘱託職員になり、一年前姑の住む町の畑に、夫婦ふたりで住むための家を新築したばかりだった。主人は単身赴任が長かったので、娘は成人してから自分の父親と暮らした時期はほとんどなかった。
みずからも母親になり、主人のことを自分の父としてというよりも、私の夫として見るようになった幸奈は、ある日、主人がそばにいるのに私に向かって、
「お母さん、よくこんなダンナで我慢できたね」
と言った。そう言われた私も、主人に聞こえるかもしれないのに、つい、
「まあね、だけどお父さんは定年まで仕事が続いただけマシだし……」
と思わず口走ってしまった。
薩摩隼人の主人は頑固で口が悪い。
幸奈はぎょっとした顔になって父親を見た。彼が私に何と言って怒りだすか心配になったのだろう。ところがそんなことはお構いなし、まったく何も聞こえなかったかのように、涼しい顔でお茶をすすり、お菓子を食べる主人。
私は久々に冷や汗の出る思いがした。世間では、
『心にもないことを言ってしまった』
とよく言うが、心にもないことを言う、などということは現実にはあるはずがない、心にあるから言葉に出るのだと、私は幸奈に日頃から言ってきた。その手前、突っ込まれると苦しいが、今回だけは例外と言うことで勘弁してもらえないだろうか。ああ、大汗をかいた。

「未熟なママでも子は育つ」(by ゆきな)
実家に帰ってきてそろそろ三年が経とうとしている。帰ってきたばかりの頃は、まだ歩けず、喋ることもできなかった息子も、今では走りまわり口も達者になった。
七年前に娘を出産した私は、保育士をしていたこともあり、育児にも自信を持っていた。しかし現実は甘くなかった。その自信はすぐに溶けてなくなってしまったのだ。
娘は産まれた時から母乳もミルクも自力で飲むことができなかった。トラブルは授乳時だけでなく、抱いてもあやしても、とにかく泣き止まなかった。さらに少しずつ成長していくにつれて、ほかの子たちとは違って、コミュニケーションに遅れが見てとれた。
心配して病院に連れて行くと、医師から「発達障害」と診断された。
「なぜうちの子が⁈」
私は納得がゆかなかった。悔しくて腹が立ったし、悲しくもあった。そのときすぐに母に頼れば良かったのだろうが、プライドの高い私にはそれができず、自分一人で育てると決めた。
夫は全く育児に協力してくれなかった。彼はいつも自分のことだけで手いっぱいで、私に優しい言葉ひとつかけてくれはしない。
そんな理解のない状態を、私はずっと耐えてきた。
しかし第二子に息子が生まれ、ふたりの子どもの育児と家事と、きつい仕事に追い回されるようになった私は、ついに限界を迎えた。私は夫との五年近くにわたる結婚生活にピリオドをうち、実家に戻る道を選んだのだ。
今では両親の手を借り、娘も元気に普通学級と支援学級の掛け持ちと、放課後の療育に通っている。
息子が家の外に出て、私と娘のあとをついてチョロチョロ動き回るたびに、ご近所のお年寄りたちが、
「まあ、可愛いらしい坊やだこと。おじいちゃんの小さいころにそっくりだねえ」
という。父のことは幼いころから知っているのだ。
息子はそう言われても意味がわからず、きょとんとしているが、私は面はゆいような、うれしいような、複雑な気持ちにさせられるのである。
😳 電子音声朗読 (← CLICK!)